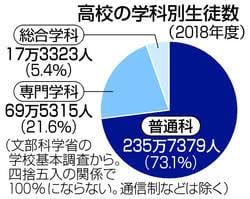今年1月、大阪市の教育委員会が、大阪府や市が実施している独自テストの結果を市内の小中学校の校長の人事評価に反映させる方針を固めたとの報道がありました。
評価に使われるのは、小学生を対象とした「学力経年調査」と中学生を対象とした「チャレンジテスト」の結果で、両テストの学校ごとの結果を校長の人事評価の20%分に反映させ、さらに賞与の約半分を占める勤勉手当の評価材料とするということです。
また、併せて同市では2020年度から、テストの結果に応じて(総額)1.6億円の予算を成績が向上した学校に配分することで学校間の競争を促すとしています。
目の前にぶら下げたニンジンで競争を煽り、順位を上げた学校や校長をお金で報いるという試みですが、(いかに銭・金がものを言う大阪人とはいえ)それで本当の学力向上に繋がるものなのかどうか。
確かに、「競争」や「評価」はモチベーションの源泉となり得るものかもしれませんが、そもそも何のために教育があり、学校があるのかという根本的な議論に欠けているような気もします。
果たして、学力の優劣や順位の比較は子どもたちの育成においてそれほどまでに重要な要素なのか。
そうした疑念のもと、神戸女学院大学名誉教授で思想家としても知られる内田樹氏が5月31日の自身のブログに採録している「文系教科研究会(外国語)」における講演内容の要旨を、参考までに小欄で紹介しておきたいと思います。
内田氏が(大学を退任後)合気道の指導者として神戸市内に自らの道場を構え、300人程度の門人を指導していることは広く知られています。
氏によれば(特に勧めているわけではないが)氏の門人たちの多くは昇段級審査の前になると自主的に集中して稽古をし、より上位の段位を目指すということです。
そうしたハードルを乗り越えようとすることが、ある種の「壁」を超える作用をもたらすことを経験上知っているので、段位や級を出すことの効用自体を否定するものではないと、氏はこの講演で話しています。
しかし、段位の上下を比べたり、誰が早く昇段したのか、誰が遅いかというようなことは一切口にしたとことはないと氏はしています。
門人同士を比べて、この人の方がこの人より巧い、この人の方が強いというようなことは考えたこともない。それは、門人同士の相対的な優劣を比較したりしても、修業上何の意味もないからだということです。
優劣を比較する対象があるとしたら、それは「昨日の自分」だけ。「昨日の自分」と比べて「今日の自分」がどう変化したのか、そこを精密に観察しなければならない。昨日まで気づかなかった感覚に気づいたりできなかった動きができるようになったり、そこに注意を向けなければいけないということです。
他人と自分の間の技術の相対的な優劣など論じても、そんなことは自分の修業に何の役にも立たないというのが、ひとりの武道家としての氏の認識です。
兵法者の心得の第一は、まず勝負を争わないこと、強弱にこだわらないことだと氏は言います。
相対的な優劣にこだわってはならない。それは自分の力を高めていく上で必ず邪魔になる。勝てば慢心するし、負けたら落ち込む。そんなことは修業にとって何の意味もないということです。
武道が涵養しようとしている能力は、どんな危機的局面に際会しても適切にふるまって「生き延びる」力だと内田氏は説明しています。
「危機」とは、その語義からして、それが何であっていつどこで遭遇するかわからないものを指す。天変地異でも、テロでも、パンデミックでも、ゴジラ来襲でも、どんな状況でも適切に対応できる力を「兵法者」は修業するのだと氏はしています。
それは試合に合わせて「ピーク」を設定するとか、ライバルとの相対的な優劣について査定したり、成績をつけたり、それに基づいて資源分配するということとはまったく別の活動だというのが氏の見解です。
さて、(翻って)我々が子どもたちを「格付け」して資源分配をするために教育をしているのか、それとも子どもたち一人一人のうちの生きる知恵と力を育てるために教育しているのか、そんなことは考えるまでもないことだと内田氏はこの講演で指摘しています。
一人一人の生きる知恵と力を高めるためには、他人と比べて優劣を論じることには(有害なだけで)何の意味もない。
でも、現在の学校教育ではそれができない。全級一斉で授業をするので一人一人をそれほど丹念に観察できないという理由はあるにせよ、授業を子どもたちの査定や格付けのために行うことについて(先生たちは)もっと痛みを感じて欲しいというのが氏の見解です。
「日本の学校教育を良くする方法がありますか」と聞かれた時、氏は決まって「それは、成績をつけないことだ」と話しているということです。
それを聞くと教員たちはみんな困った顔をするか、あるいは失笑する。「それができたら苦労はないですよ」とおっしゃる。でも、ほんとうにそれほど「それができたら苦労はない」ことなのか。
内田氏自身、現に武道の道場という教育機関を主宰し「成績をつけない。門人たちの相対的な優劣に決して言及しない」ということをルールにしていても、門人たちは実に効率的にぐいぐいと力をつけていると氏はしています。
道場では査定をしない。寺子屋ゼミという教育活動も並行して行っているが、ここでも(研究の個別的な出来不出来についてはかなりきびしいコメントをしても)ゼミ生同士の優劣について論じることは絶対にしないということです。
内田氏は、なぜ教育の場で教わる者たちは、指導者によって査定され、格付けされ、それに基づいて処遇の良否が決まるということを「当然」だと信じられるのかがわからないとこの講演で述べています。
明らかにそれは教育にとって有害無益なことで、それは40年近く教育という事業に携わってきた者として確信を以て断言できると話すこの講演における教育者としての氏の確信を、私も大変興味深く受け止めたところです。