新スプリアス規格とはWRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われ、国内も関係省令及び関係告示が改正された。
現在免許を受けている無線設備の無線免許状の再免許申請をする場合平成34年12月1日以降はJARD(日本アマチュア無線振興協会)のスプリアス確認認証を受けなければならないならない。
自分と妻の移動する無線局免許状が来年はじめに有効期限となるので、早めに手続きをすることにした。
まず、JARDのホームページでスプリアス確認認証の方法を調べたら、Web申請が便利そうなので、これを使って申請することにした。
無線機の技適番号があれば簡単に申請できると思っていたら大変なことだとわかった。
自分の無線局免許は40年以上前に開局申請をしてからHFの無線機は取り替えの申請をしたが、それ以外は増設申請してきた。
なので、第1送信機がどの無線機なのかがわからない。
JARDのホームページのFAQにこの質問があり、所管の総合通信局に問い合わせるとなっている。
これは面倒なことになりそうだ。紙での変更申請の控えや免許更新の電子申請のバックアップを調べてみた。
更新の電子申請には具体的な装置は記載されていない。紙での変更申請の控えをスキャナーで取り込んで画像としてサーバーに保存がしてあったので助かった。
 第1送信機はアイコムのIC-706(50W改)現在も使用している
第1送信機はアイコムのIC-706(50W改)現在も使用している

第2送信機はナショナルRJX601

第3送信機はアイコムIC-502

第4送信機はアイコムIC-202
倉庫の箱の中から出てきた。とても懐かしい。

第5送信機はマランツのC601これは430MHzと1.2GHzのハンディー機
第6送信機は430MHzのモービル機で付加装置にパケット通信を付けていた。
RJX601、IC-202、IC-502、パケット通信の4台を撤去しても2台を残せば1.9MHz-1.2GHzの範囲での免許になる.
まず第2-4、6送信機の撤去の変更申請をしてからスプリアス確認認証をすることにした。
変更申請をしてすぐに九州総合通信局に電話をして下さいとのメールが来た。何か手違いがあったのかと電話をかけると”430MHzが50Wから10Wになるけどよろしいですか”と確認だった。
10Wに変更してもらい、疑問だった撤去の変更後、送信機の番号について質問をした。
つまり、第1送信機と第5送信機が残るがこれは第1、第2となるのか、第1、第5となって第2-4は空欄なのかが疑問だった。
すると、答えはどちらも希望でできるとのことだった。今回の申請では第1、第5となって第2-4は空欄の申請になっているけど、この電話で第1、第2に変更することもできるとのことだ。
私は申請のままにしてもらったが、九州総合通信局の担当の方はとても感じのいい対応だった。

これはスプリアス認証をWeb申し込みのフォーム。
各送信機の変調方式、終段管の名称、電圧、出力など開局申請と同じように細かく記入する必要がある。
前述のように40年以上前に開局申請をした無線機はスプリアス認証申請は難しいと思う。
今回、比較的新しい無線機に変更申請したことでスプリアス認証申請をし、保証認定料を振り込んだ。

しばらくしてからスプリアス確認保証通知書が郵送されてきた。

その後、再免許申請をし無線局免許場が届いた。
今回の再免許申請は長かった。













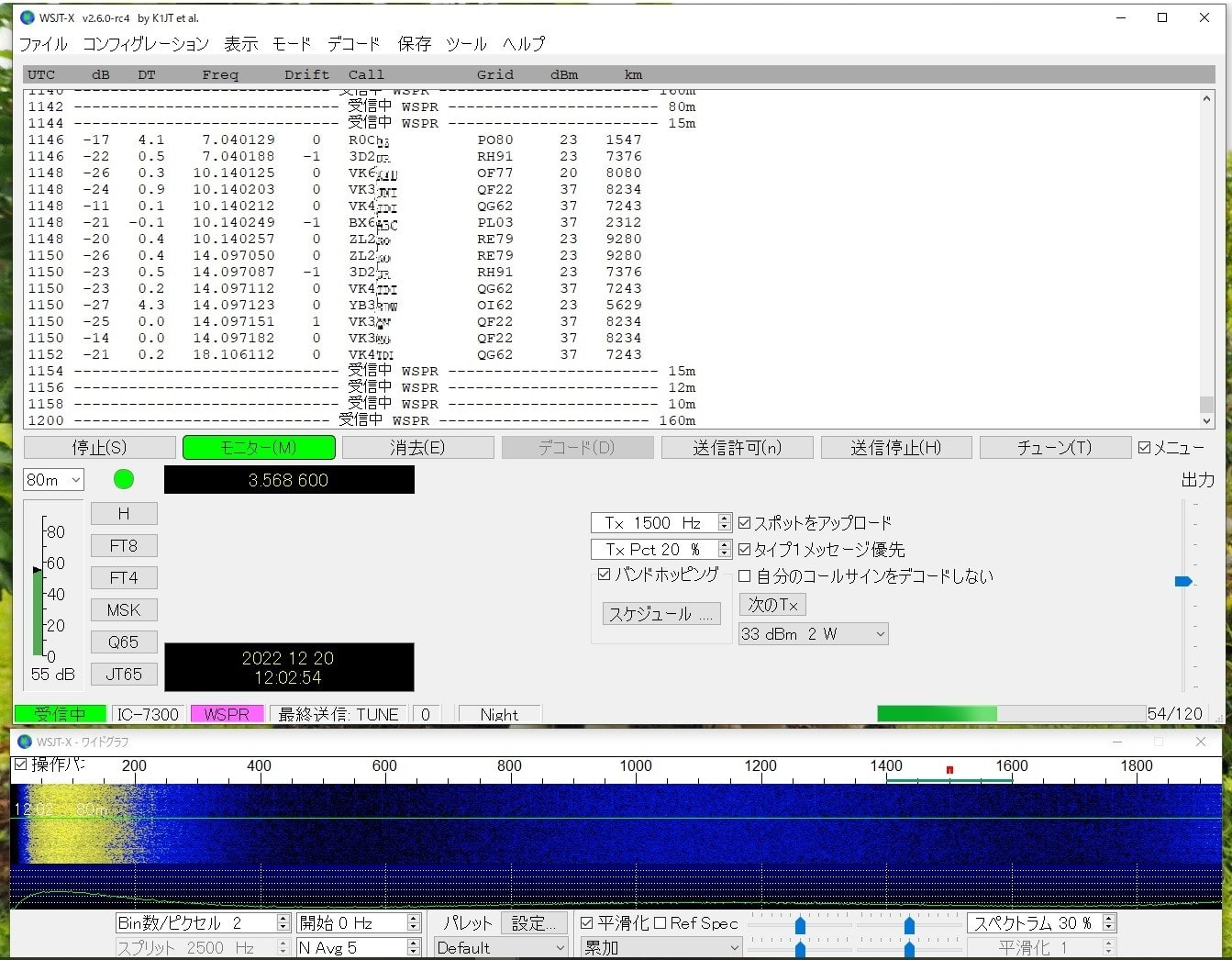







 第1送信機はアイコムのIC-706(50W改)現在も使用している
第1送信機はアイコムのIC-706(50W改)現在も使用している





