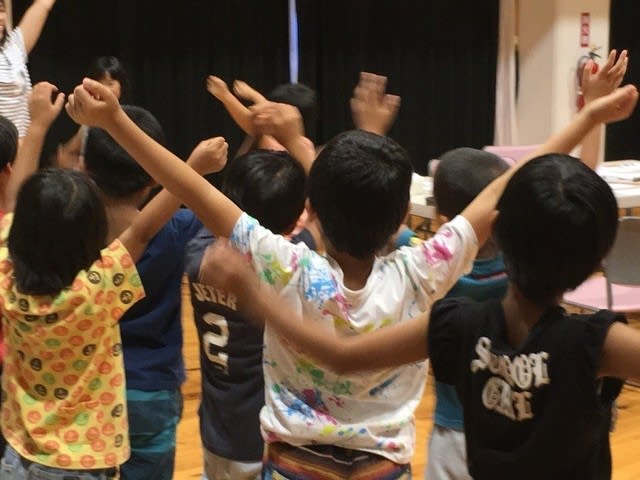浜田市世界こども美術館で行われた、月例鑑賞会のレポートが届きました。


日 時:2017年9月9日(土) 14:40〜15:00
場 所:浜田市世界こども美術館コレクション室
作 品:『コドクナオトシモノ』大谷千恵 染色画 制作年不明
参加者:7名(内みるみる会員4名)
ナ ビ:松田 淳
今回のコレクション展に並ぶ作品を見渡した時に、人それぞれにいろいろな感じ方や考え方ができそうな作品だと思い、この作品を選びました。初めて対話型鑑賞に参加される方もおられたので、自分で見て感じたことを言葉にし、人の話も聞きながらまたさらに見方を深め、この鑑賞の楽しさを味わってほしいと思い、鑑賞会を始めました。
はじめにみるみるの鑑賞会のリピーターである男性が「波や貝があり、海に関係するものが描かれている。でも、この絵はシュルレアリスムの表現であって、おそらく描かれているものや、それぞれの関係に深い意味はないと思う」と発言されました。ナビの私は、「シュルレアリスムという、超現実的な表現だから描いているものに意味はないということでした」と単純に発言を繰り返したつもりで全体に返しました。このことについては、あとの振り返りのミーティングで、シュルレアリスムとは超現実的な絵であり、描かれているものに意味はないという解説にも聞こえ、誤解が生じる可能性のあると指摘を受けました。シュルレアリスムの解釈について、発言された方に聞き返してみるなどして、みなさんと共有できるとよかったかもしれないというご意見もいただきました。
続けて、初参加の男性が発言されました。小学校の教員で、少し前にみるみる会員が、その男性の担任する学級で対話型鑑賞の出前授業をしたところ、関心が高くなり今回参加してくださいました。「右下の溜まって垂れている水が涙に見える。色からも全体に悲しい感じがして、左上の方は過去の良かった頃の自分で、手前が今の悲しい自分の状態を表していると思う」とこの絵に込められた思いの部分を想像して話されました。
このあとに、一緒に参加してくれた同じく初参加の女性が、「ほとんどが貝なのに、ひとつだけ鍵のような人工物が見えるが、何の意味があるのかなあと思った」と発言してくれました。これを何ととらえ、貝などとの関係性を想像することで、さらにトークが盛り上がるかもと期待できるような発言でした。
「このものについて皆様はいかがでしょうか?」と聞いたところ、リピーターの男性が「やはりこれにも深い意味はないと思う」と一貫した考え方で答えられました。そのあと別の方からこれについての発言はなく、結果的に深めていくことにはつなげられませんでした。このことも、もしかすると私がはじめに「シュルレアリスムとは意味のないものが組み合わされて描いてある絵」という誤解を与えるようなナビをしたからなのかもしれないと今は思います。
今回は30分以内で終わろうと考えていて、さらに自分はパラフレーズに課題があり、話した人の解釈とズレが生じることもあるため、今回はパラフレーズを極端に短くして時間短縮を図りました。このことは、テンポよく進んで、軽やかな進行がここちよくて新鮮だったという肯定的な意見と、やはり共通認識を図るためにパラフレーズは有効で、ある意味ファシリテートの放棄にも捉えられるという否定的な意見のどちらもが振り返りであげられました。
そのあとに、みるみる会員が「今、お二人が、描かれているものから想像してお話されたり、描かれているものに意味を考えなくてよいとおっしゃったりしましたが、この絵はそんなふうにそのときそのときで見え方が違う絵だと思いました。体調によっても違う見え方をするのだと思います」と、どちらの見方も肯定されるような発言をしてくれました。その方が振り返りで、この絵のタイトルが『コドクナオトシモノ』であることを途中で示してもよかった(今回は最後までキャプションは隠していた)と思ったと言われました。タイトルを知ると、シュルレアリスムではなく、心象表現としての絵であることが明らかとなり、描かれているものと描かれ方などからもっと話ができたのではとアドバイスをもらい、なるほどと思いました。
後半に入り、手前のブロックの囲いや、真ん中の立方体の枠など、やはり描かれているものの“意味”について想像する発言が続いたところで、シュルレアリスムだから深い意味はないとされていた方が、「波だとみなさんが考えていた連続する曲線が、女性の体に見えてきた。そう思うと貝などの意味も違って考えられてきた」と発言されました。他の人たちの話をじっくり聞きながら考え、ご自分の新しい見方に気付いたのではないかと思います。
20分という短い時間ではありましたが、参加者のみなさんの積極的な発言や、他の方の発言を尊重しての意見によって、充実した鑑賞会になりました。せっかくなので、最後に初参加の男性に感想を言ってもらいました。こんなにひとつの絵をじっくり見たのは初めてで、感じたことをある意味自由に話し合えるので、自分の担任する学級の子どもたちにもできそうだと話されました。リピーターの男性に、この会に続けて参加してくださる理由について聞くと、やはり絵をじっくり鑑賞することがよい、美術館にいったりすると鑑賞時間がすごく長くなってしまうようになったと笑って話されました。とてもうれしい言葉でした。
参加してくださったみなさま、ありがとうございました。

次回の鑑賞会は10月14日(土)14:00~浜田市世界こども美術館にて。
秋のひと時、一つの作品をじっくりとみて、感じたことを話し合ってみませんか?
ご来館をお待ちしております。