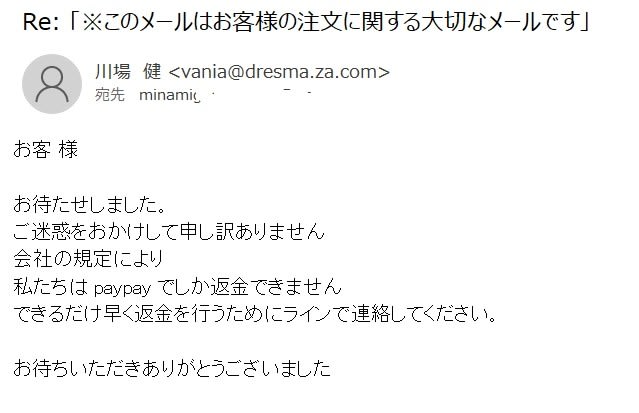今ハマっているテレビドラマに「あきない世伝 金と銀」(高田郁著)がある。あまりに面白いので、原作を全巻揃えた。

私は人間が努力して成功していくこの種の物語が好きだ。主人公の幸(さち)は享保年間に武庫郡(現尼崎市)で生まれ、縁あって大阪天満の呉服屋「五鈴屋」に奉公する。やがてその才が認められ、呉服屋のごりょんさんとなる。
昨日のドラマでは、幸の夫である呉服屋の主人が近江で新しい商売を始めるシーンが描かれていた。その時、先代の番頭が
「人間の地金が試されますなあ」
と言った。五鈴屋が自分だけ儲けようとするのか、それともみんなの幸せを考えて共存共栄を図るのか、それが試されているという意味である。結局、五鈴屋は目先の利益に走り自分だけ儲ける道を選ぶ。その結果どうなったか。続きは来週放送される。
今回のドラマで「人間の地金が試される」という言葉が妙に心に刺さった。教育に50年間携わってきたが、果たして自分は「人間の地金」を磨く教育をしてきたのだろうか。今の社会は「地金」を磨くことより、手っ取り早く「メッキ」で取り繕って結果を出すことが喜ばれる。そんな教育に加担してきたのではないか。忸怩たる思いで自問自答する。
基本的に人間は利己的である。利己心が経済活動の源泉であり、それが社会を発展させてきた。利己心を否定した共産主義は見事に失敗した。だから、利己心を否定するつもりは全くない。
しかし利己心を肯定することは、何をしてもいいということを意味しない。そのことはアダム=スミスも『道徳感情論』の中で「共感」という概念を用いて説明している。
今の時代に「地金」を磨く教育はいかにして可能か。薄っぺらな知識を大量注入する教育を見ていて、ふとそんなことを思う。人間は動物とは違う。人間には理性というものがある。もし理性を人間の内なる良心の声だとするならば、そうした良心の声を育てることが「地金」を磨くことなのかもしれない。