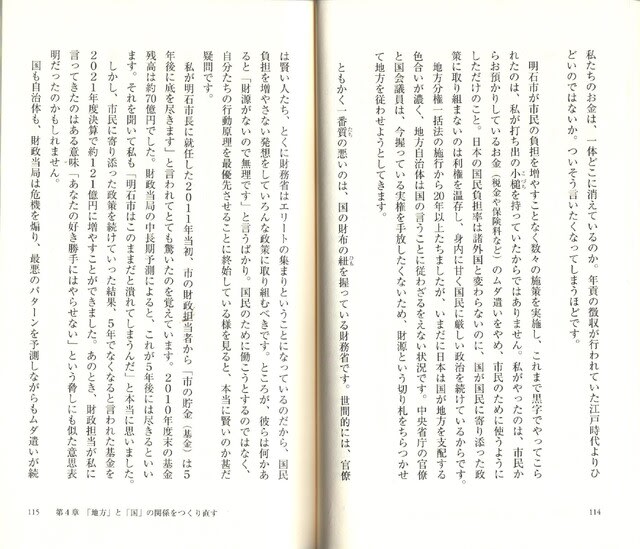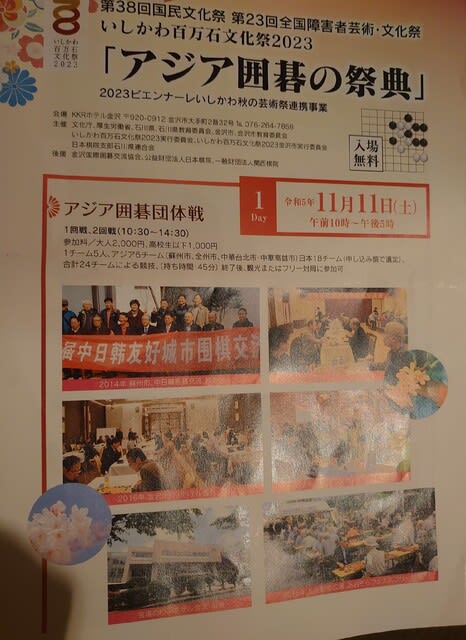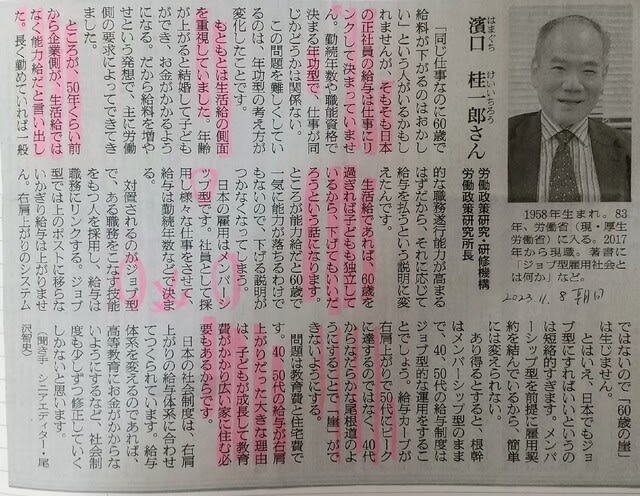立ち退きに応じない家に対して、「火つけて燃やしてこい」と職員に暴言を吐いたことで一躍有名になった泉房穂明石市長(元)。しかし、この本を読んでそれまでの政治家泉房穂に対するイメージが180度変わった。そうした過激な発言の裏にあったのは何か。
原点となったのは彼が10歳のとき障害を持つ弟が小学校に入学する際に社会の冷たさを体験したことだったという。その時、将来明石市の市長となり、冷たい社会をやさしい社会に変えたいと決心した。
NHK職員・弁護士を経て、2011年47歳で明石市市長となった。その時の対立候補は自民党、民主党が推薦し、兵庫県知事、医師会、商工会議所、労働組合などの全面支援を受けていた。しかし、それまで地元で弱者に寄り添う弁護士活動を展開していた泉は69票差で勝利を収めた。
市長に就任した泉は早速所得制限なしの5つの子育て支援策を実施した。
① 18歳までの医療費(薬代を含む)を無償化
② 第2子以降の保育料の無償化
③ おむつ定期便の実施(無償)
④ 中学校給食費の無償化
⑤ 公共施設の遊び場の無償化
これらの実施には予算が必要である。泉は公共事業などを削減し、子育て支援に予算をシフトさせた。泉によると市長の仕事は3つだけだという。
1.方針(ビジョン)を決める。
2.予算をシフトさせる。
3.人事を適正に配置する。
当然、既得権益を持つ勢力からは強く抵抗された。何度も「殺すぞ」と脅された。また、暴言市長のレッテルを張られ、泉に不利な情報がリークされた。しかし、泉はひるまなかった。
効果は5年後に現れた。明石市の人口は増加し、商店街は活気を取り戻し、建築ラッシュが起きて税収も増加した。2019年の選挙では8万票、実に70パーセントの得票率を得た。とくに子育て世代からの支持は圧倒的で、30代の得票率は90パーセントに上ったという。泉は言う。明石市でできることは全国どこの自治体ででもできる。
泉の国政批判も小気味がいい。議院内閣制の下では首相は国会議員によって選ばれるため、首相は国民をろくに見ないで与党議員の顔ばかりを見て仕事をしている。
財務省は税金を上げることしか考えていない。厚生労働省も社会保険料を引き上げることばかりを考えている。その結果、1970年に25パーセントだった国民負担率は2023年には47.5パーセントにまで上昇してしまった。彼らが本当に頭がいいなら、国民の負担を増やさないで予算をシフトできるはずだと説く。
地方分権一括法ができて国と地方は対等になった。しかし、いまだに市町村より都道府県が偉くて、都道府県より国が偉いとみんな思っている。予算が欲しければ国の言うことを聞けという政治がまかり通っている。市長も県知事も国会議員も総理大臣も同等であり、単に役割が違うだけだと泉は主張する。彼の政治姿勢に本物の政治家を見た思いがする。