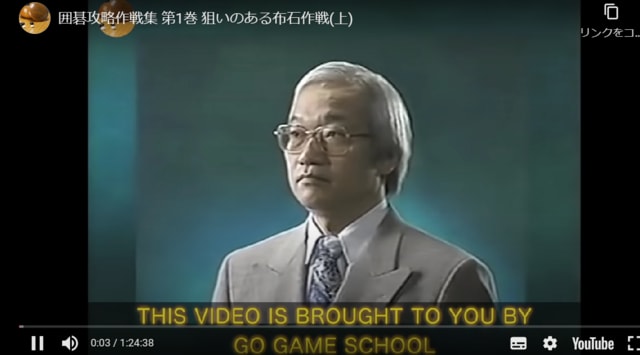500円割れを狙って2年前からずっと追いかけてきたが、とうとう買いそびれてしまった。掉尾の一振か。今日は跳ね上がっている。仕方ないね。別に損したわけでもないのに、なぜかちょっと悔しい。
700円近辺から異常に強い相場だった。誰かが買い集めているのだろうと思っていたが、理由は今日発表された内容でわかった。
(以下引用)
不動産関連のグループ会社の再編に関するお知らせ(発表日:2023年07月31日)
当社は、当社のグループ会社で不動産賃貸事業などを手掛ける三菱HCキャピタルプロパティ株式会社と三菱HCキャピタルコミュニティ株式会社において、三菱HCキャピタルプロパティを存続会社、三菱HCキャピタルコミュニティを消滅会社とする合併(以下、本合併)を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。(引用終わり)
ここから先は私の邪推でしかないが、多分どこぞから情報が洩れて誰かがひそかに買い集めていたのだろう。そう考えると合点がいく。株式市場とは玄人筋が素人からお金を巻き上げる合法的制度だという思いを新たにした。
今日の値上がりを見て飛びついた素人が今度は食い物にされるのだろう。山高ければ谷深し。クワバラクワバラ。度胸があればここでカラ売りを仕掛けてもいいのだが、残念ながら年金暮らしの身にそういうリスクをとる行為は似合わない。当分高みの見物と行くか。