
ついに1ドル130円を突破した。日米の物価動向(日本のデフレとアメリカのインフレ)を考慮すれば、理論的には円高が進行するはずである。1ドル69円が妥当な水準だという試算もある(購買力平価)
しかし、実際にはアメリカはインフレを抑えるために金利を引き上げ、日本は景気回復および国債の利子負担を軽くするために低金利を維持しており、その結果、急激な円安が進行している。いま日本経済に何が起きているのか。
ここから先は筆者の個人的な勝手読みである。


ついに1ドル130円を突破した。日米の物価動向(日本のデフレとアメリカのインフレ)を考慮すれば、理論的には円高が進行するはずである。1ドル69円が妥当な水準だという試算もある(購買力平価)
しかし、実際にはアメリカはインフレを抑えるために金利を引き上げ、日本は景気回復および国債の利子負担を軽くするために低金利を維持しており、その結果、急激な円安が進行している。いま日本経済に何が起きているのか。
ここから先は筆者の個人的な勝手読みである。

最近メルカリをよく使う。おかげで、クロネコヤマト、佐川急便、郵便局など、配達する人とすっかり顔なじみになってしまった。
今日もエレクトーンの楽譜が10冊以上届いた。これでクラシック、ポピュラー、映画音楽、歌謡曲、ジブリなど50冊以上たまった。1曲弾けるようになるのに2週間はかかるから、もう当分楽譜には困らない。ずいぶん散財した。


売る方もしっかりやっている。読んだ本はたいていすぐメルカリに出品する。4月だけで13冊売れた。最近は、日本画の岩絵具や本なども断捨離している。例えば下の放光堂の岩絵具。放光堂はかつては横山大観もひいきにした京都の老舗である。色があまりにきれいなのでもったいなくて使えなかった。しかし、このまま持っていても宝の持ち腐れなので、結局、買値より少し割り引いて4万円で売却した。新品のままだったからお買い得だったと思う。

今度は世界文学全集全70巻を売りに出そうかな。でも、今時こんなもの買う人いるかな?


500ページを超える大著(2006年)である。
もともと利己的な遺伝子という考え方はダーウィンの考え方である。「われわれは生存機械ー遺伝子というのあの利己的な分子を保存するべく盲目的にプログラムされたロボット機械なのだ」。しかし、その一方で利他的な行動をすることもある。
たとえば、働きバチがひたすら女王の子孫のために働くのはその例である。働きバチは遺伝的には雌であるにもかかわらず、自ら卵を産み育てることをせず、もっぱら妹の養育に専念する。しかも、ひとたび巣が危険にさらされると、働きバチたちは自らの命を投げ出して巣の防衛にあたる。刺すという行為で針と共に内臓がもぎ取られてしまう。こうした利他的な行動はなぜ進化しえたのか。
人間も動物であるが、人間はほかの動物と違って文化によっ利他的に行動することを学習する。最近、民族主義や愛国心に反対して、仲間意識の対象を人間の種全体に置き換えようとする傾向が出てきた。どのレベルでの利他主義が望ましいのか。家族か、国家か、人種か、それとも全生物か。
動物が子孫を残す仕掛けには「ハーレム制」「一夫一婦制」「乱婚」などいろいろある。通常一頭の雄は莫大な量の精子を簡単に作るから、雌100頭くらいのハーレムを作ることもできる。実際にゾウアザラシは、4%の雄が交尾例の88%を達成しているという。
人間は通常一夫一婦制である。しかし、男はよく浮気をし「乱婚」もどきの行為に及ぶ。これは、男は毎日莫大な数の精子を作るので、できるだけ多くの性交渉を行うことで大いに利益を上げることができるからである。一方、女は限られた数の卵子をゆっくり作り出すので、やたら性交渉を重ねても利益はない。
面白い本である。


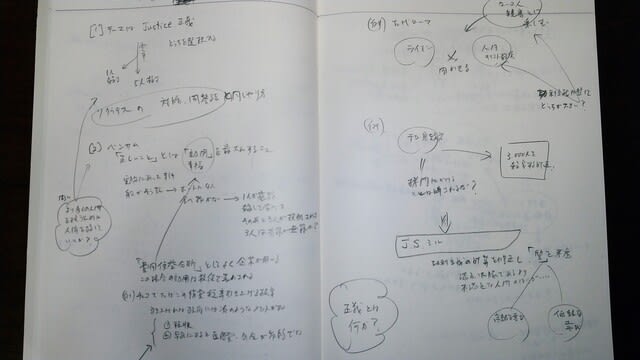

『Amazonの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した』 ジェームズ・ブラッドワース著 を読んだ。
現在、イギリスでは20人に一人が最低賃金で生活している。その実態を知るために、ジャーナリストである著者がAmazon、介護、コールセンター、ウーバーの現場に自ら飛び込む。クリックの向こう側でどんなことが行われているのか。
イギリスにあるAmazonのこの広大な倉庫には、1200人が働く。商品の受け入れ、整理、ピックアップ、発送の4つのグループに分かれて作業を分担する。アマゾンではこうした労働者も、CEOのジェフ・ベゾスもassociate(仲間、共同経営者)と呼ばれる。
有能なら正社員への道もあるとされるが、実際に正社員になれることはない。時給7ポンド。71%の人が倉庫内を1日16キロ以上歩く。あまりに過酷な現場のため次々に辞めていく。最初はイギリス人が雇われていたがみんな辞めていき、いまはルーマニア人など東欧の外国人労働者が多く働く。
ウーバーというタクシー業界は「ギグ・エコノミー」と呼ばれる。ギグ・エコノミーとは、フリーランスの単発の仕事によって成り立つ急成長の労働市場である。ケータイのアプリを利用して、いつでも好きな時に仕事ができ、支払いは出来高払い。あなた自身が社長という美辞麗句の下で彼らがどのような環境で働かされているか。
便利さと引き換えに、クリックの向こう側でどんなことが行われているかを告発した本である。



例えば「水」。
「水は何でできてるのか」、「水を冷やすとどうして氷に変わるのか」、「水を沸騰させると何で泡が出てくるのか」。ちなみに最後の問題は宮城教育大学入試問題である。
学校ではこれを「知識」として教えてきた。中学校のとき、水素の燃焼実験というのを理科の時間に習った。水素と酸素を2対1の割合で混ぜ、これに火をつけると「ボン」という大きな音がして水ができるというあれである。大きな音だけが印象に残っている。
この実験を通して、水は水素と酸素からできていることを教えられたわけだが、物質が元素の集まりによってできているという「不思議さ」に「感動」した覚えは全くない。2H2+O2→2H2O という化学式を知識として暗記しておしまいだった。よく分からなくても、これを覚えていればテストで満点が取れた。
しかし、本当に大切なことは「物質は何によってできているのか」と考える好奇心のはずである。好奇心があれば、知りたいという欲求が自然にわいてくる。木は何でできているのか。なんで燃えるのか。燃えるとなんで黒炭ができるのか。ダイヤモンドはなぜ硬いのか。ダイヤモンドも燃えるのか。
これまでの日本の教育は「知りたい」という心のエンジンに火をつけるのではなく、結論を覚えさせてテストでいい点数を取らせることを優先してきた。だからどうでもいい細かなことをいっぱい教えてきた。とくに力量のない先生ほど、細かな知識に逃げる傾向があった。
最近になってようやくこのことの反省が始まっている。ただし、「好奇心教育」をやろうと思ったら、教員のほうによほどの力量がないとできない。知識を教えるほうがはるかに楽である。また、行政のトップや校長も点数を取らせることに執着している。日本の教育はやっぱり変わらないのかもしれない。


今日も2冊読んだ。一冊は300ページ余り、もう一冊は500ページ余りの大著である。 必要な箇所はすべてノートにメモをした。
「読書の全技術」では、1日に10冊以上を読破することもあるという著者が、速読のための全技術を明かす。私の速読術と共通する部分が多かった。本はたくさん読めば読むほど知識量が蓄えられ、読むスピードが速くなる。読書を通して思考力が養われ、知識が身につく。テレビやインターネットでは、読書から得られるような体系的な知識や思考力は得られない。
「ベンチャー・キャピタリスト」にはグーグル、アップル、テスラ、モデルナなどに投資した世界の代表的なベンチャー・キャピタリスト30人(孫正義氏もその一人)が紹介されている。世の中には発明家と呼ばれる人と、それを資金的に支える資本家と呼ばれる人がいる。銀行はローリスク・ローリターンの投資先にしか貸さない。しかし、世界を大きく変える技術はハイリスク・ハイリターンである。ベンチャー・キャピタリストはこうしたハイリスク・ハイリターンに投資する。
GAFAといえども盛者必衰の世界。創業者が年を取れば成長と輝きは薄れていく。小さなヒットを量産してもたかが知れている。いかにして大ホームランの案件を見つけるか。世界を動かす最強の「キングメーカー」たちは黙して語らない。

宅配便の取扱個数が急速に増えている。2020年度の年間取扱個数は48億個に上るという。私自身も最近は宅配便のお世話になることが多い。2022年3月だけで25回(Amazon8回、メルカリ17回)利用していた。ほとんど毎日だ。Amazonでは、朝注文するとその日のうちに配達されることもある。とにかく便利である。
増加する荷物の多くは個人宅配業者と呼ばれる個人事業主によって配送されている。個人事業主は労働基準法の残業規制が適用されない。彼らは、荷物を効率的に運ぶためにAIが出したルートが表示されているスマートフォンを片手に走り回っている。ちなみに、佐川急便は2013年、採算の合わないアマゾン配送から完全撤退した。
業務委託契約には様々なタイプがあるらしい。以前聞いたところでは、1件の配達で200円だった。しかし、今はもっと値下がりしクロネコの場合1件につき160円、ポストに入る薄型のものは1件30円である。月収は30万円ほどになるという。
そのほか、日当制のところもあるようだ。1日1万5千円。ただし、月収30万円あったとしても、そのうち車の維持費などを差し引くと手取りは20万円だという。
個人事業主は建前上は契約する事業者と対等であるとされるが、実際にはいつ契約を打ち切られるかもわからない不安定な立場にある。厚労省の調べによると、全産業の年間所得489万円に対して、中小型トラックドライバーの年間所得は388万円だという。
円安に加えて原油価格の高騰と、宅配業者にはさらに厳しいコスト増が待ち受けている。

(写真は若手研究者を招いて三国丘高校で行った自主ゼミ 2002年11月30日土曜日)
高校生が自ら課題を見つけ、調べ、考え、その結果を報告する「探求学習」がようやく行われるようになってきた。これにより思考力や表現力を養うことが目的とされる。大いに結構なことである。実は同じことを私は20年以上前から提唱し、実践してきた。
高校でもゼミ教育を! - 南英世の 「くろねこ日記」 (goo.ne.jp)
今、現場の探求学習がどのような形で行われているかは知らない。しかし、問題が二つある。
一つは指導する先生がきちんとした指導をできるかという問題である。課題が細分化し、学問の最先端に近づけば近づくほど、高校教員では十分な指導が困難になってくる。その時、それをサポートする体制をどのように作るか。大学の若手研究者や院生に援助を求めるとしても、その財源まで確保する気が文部科学省にあるのか。もし予算もつけず、全部高校の先生任せだとするならば、「探求学習」は「ほったらかし学習」の遊びの時間になってしまうであろう。
二つ目は入試制度の問題である。共通テストになって「思考力」や「判断力」を問うことに重点が置かれるようになってきたといわれる。しかし、高校3年間で学習するボリュームは基本的に減ってはいない。
そうなると、従来の受験勉強に加えて、生徒が「探求学習」にどれくらいの時間をかけることができるのか。たぶん、多くの時間をかけることは難しいだろう。それでなくても、多くの進学校では文科省が定めたカリキュラム通りの授業を行わず、受験科目に特化した授業をやっている。もし、探求学習が入試に「直接」役に立たない科目だとすると、せっかく鳴り物入りで導入しても「やってるふり科目」として軽く流されてしまうであろう。
探求学習がこの先どうなるか、じっくり見物させてもらう。自らの手柄としたい役人の一過性の思い付きに終わらないことを切に願う。

1978年に芹洋子が歌ってヒットした曲です。エレクトーンで弾いてみました。御笑覧ください。
Facebook(坊がつる讃歌)
実はこの元歌となったのは、広島高等師範学校山岳部山男の歌です。
広島高師って、すごいんですね。


