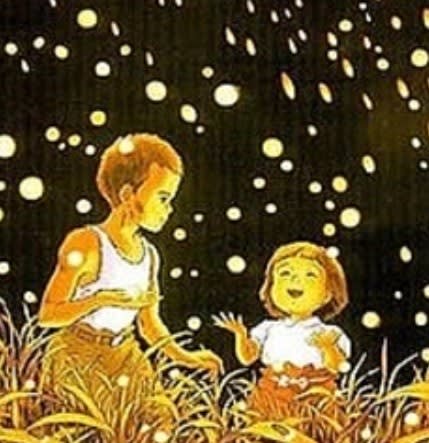ちょうど1年前、コロナの影響で世界恐慌にも匹敵する大不況が来るのではないかと予想した。しかし、不況対策として大幅な金融緩和が実施されたため、予想に反して株式市場は活況を呈している。
とくに日銀が相場を支えているのが大きい。日銀の年間の購入額は、一昨年までは6兆円だったが、2020年3月にはコロナ対策として12兆円に増額された。値下がりすると日銀が買い支えるものだから、実体経済と乖離していても資金が株式市場に流入しやすくなっている。
ただし、日銀が個別の会社の株を買うのは流石にまずいでので、たくさんの会社の株がセットになっている上場投資信託(ETF)を購入する。そのセットの中にユニクロも入っており、現在ユニクロの最大株主は日銀で、その持ち株比率は20%にも達している。このほかにも日銀が実質的な最大株主となっている企業は多い。
しかし、日銀が主導して株価を吊り上げるなどという行為は、株式市場の本来の価格形成能力をゆがめるものであり、好ましくないことは言うまでもない。日銀もこの点は自覚しており、どこかで出口(手持ち株式の売却)を作る必要がある。
そうした矢先、2021年年3月19日、日銀は買い入れ対象から日経平均連動型の上場投資信託(ETF)を外し、あわせて年6兆円としてきた購入額の目安もなくすと発表した。今、なぜこのタイミングなのかはよくわからないが、これをきっかけにユニクロをはじめ株式市場は急落しはじめた。
コロナワクチンが普及して、コロナ騒ぎが一段落すれば金融相場は終わりを迎える。今回のETF購入修正はその第一歩か?「株式投資は儲けようなどとは思わず、損をしないことを旨とすべし」。50年の投資体験から得た結論である。損をしないための絶対的方法は? 株を買わないことである(笑)。
とくに日銀が相場を支えているのが大きい。日銀の年間の購入額は、一昨年までは6兆円だったが、2020年3月にはコロナ対策として12兆円に増額された。値下がりすると日銀が買い支えるものだから、実体経済と乖離していても資金が株式市場に流入しやすくなっている。
ただし、日銀が個別の会社の株を買うのは流石にまずいでので、たくさんの会社の株がセットになっている上場投資信託(ETF)を購入する。そのセットの中にユニクロも入っており、現在ユニクロの最大株主は日銀で、その持ち株比率は20%にも達している。このほかにも日銀が実質的な最大株主となっている企業は多い。
しかし、日銀が主導して株価を吊り上げるなどという行為は、株式市場の本来の価格形成能力をゆがめるものであり、好ましくないことは言うまでもない。日銀もこの点は自覚しており、どこかで出口(手持ち株式の売却)を作る必要がある。
そうした矢先、2021年年3月19日、日銀は買い入れ対象から日経平均連動型の上場投資信託(ETF)を外し、あわせて年6兆円としてきた購入額の目安もなくすと発表した。今、なぜこのタイミングなのかはよくわからないが、これをきっかけにユニクロをはじめ株式市場は急落しはじめた。
コロナワクチンが普及して、コロナ騒ぎが一段落すれば金融相場は終わりを迎える。今回のETF購入修正はその第一歩か?「株式投資は儲けようなどとは思わず、損をしないことを旨とすべし」。50年の投資体験から得た結論である。損をしないための絶対的方法は? 株を買わないことである(笑)。