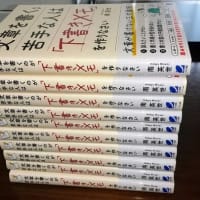「宇沢弘文傑作論文全ファイル」(418ページ)をやっと読み終えた。ものすごくスケールが大きく人間味あふれる学者だったことを改めて知る。
彼の著作の中で一番体系的でわかりやすいのは『社会的共通資本』(岩波新書)であろう。

彼はこの中で、次のようなことを述べている。豊かな経済生活を送り、幸せに暮らすには「社会的共通資本」の整備が欠かせない。社会的共通資本とは次の3つの分野のことを言う。
① 自然環境・・・大気、森林、河川、水、土壌など
② 社会的インフラストラクチャー・・・道路、交通機関、上下水道、電力、ガスなど
③ 制度資本・・・教育、医療、司法、行政、金融制度など
これらのものは純粋な私的財産と違って、たとえ私有されていても社会的な「共通財産」として適切な管理・運営がなされるべきであるとする。例えば、大気はこれまで自由財として価値がゼロであるかのように扱われてきた。それが地球温暖化を招いている。とくに教育と医療に市場原理主義を持ち込むことは間違いだ、という主張が強く印象に残った。

先日、佐々木実が書いた『宇沢弘文』(講談社現代新書)という本を読んだ。その前に読んだ『ゼロからの資本論』(斎藤幸平)と合わせて、ようやく宇沢弘文という経済学者の思想的位置を自分なりに整理できた。図解すると次のようになる。

(作成 南英世 この図の無断転載を禁じます)
小さな政府、大きな政府という政府の役割から見た概念ではなく、どこまでを私有、共有にすべきかという視点でまとめてみた。新自由主義は市場はすべてを解決するという思想の下で、市場だけを取り出して分析した。市場というものをリンゴの絵にたとえると、リンゴだけを描こうとしたのがフリードマンらの市場原理主義者である。
一方、宇沢は市場だけを分析するのではなく、市場の背後にある要素も経済学に取り込もうとした。すなわち、リンゴの絵を成り立たせるための「背景」までを分析対象としたといえる。すべての人が豊かな経済生活を送ることができるためには、社会的共通資本(Social common capital)は市場の外にあって共有されなければならない。これが宇沢経済学の肝である。
これまで経済学は近代経済学(資本主義)とマルクス経済学(社会主義)が対立する形で展開されてきた。しかし、宇沢によって経済学は新たな地平にたどり着いたと言えまいか。近い将来、宇沢弘文が再評価され、上に描いた図が教科書に掲載される日が来るような予感がする。

(上記のブログを書くための下書きノート)