
友人から勧められたこの本。読み始めたら面白くて一晩で読んじゃいました。中身は素粒子論やら周波数やらで難しいんですが、苦手な数字はざざっと斜め読み。それよりこの発想が面白い。
タンパク質は20種類のアミノ酸から合成されますが、合成時に起きる波動の振動数を平均律に置き換えることにより、音楽が作られるというもの。この音楽を聞かせることで、病気が改善したり、植物がよりたわわに実ったりと、いくつもの実験報告がされています。
この方法は物理学者のジョエル・ステルンナイメール博士が提案しています。実はこの博士、シンガーソングライターとしてエヴァリストという名前でレコードを出したら爆発的なヒット。その資金で研究を続けたと云う変わり種です。当初素粒子の質量についての研究をしていたステルンネイメールですが、ノーベル物理学賞を受賞したアンリ・ポワンカレ研究所のド・ブロイ博士の推薦を得て、アメリカ・プリンストン大学に助手のポストを約束されました。ベトナム戦争で資金不足となった当時の研究所がそのあおりをくらって、到着してみたら席がなかったということに。パリにもどり、知り合いのレコード会社から自分で作った曲を出したところベスト・セラーになり、テレビ・映画にも出演し一役スターに。その間も素粒子の質量研究をしている折、分布図が音楽の周波数に当てはまることを発見。1983年に「素粒子の音楽」という論文をまとめました。日本では大野乾(すすむ)博士がDNAの音楽を発表しており、そのほかいくつか遺伝子の音楽など、音楽に変換する試みはされています。
ステルンナイメール博士は彼らとはまた別の方法で、DNAの音楽から発展させ、タンパク質を音楽に置き換える方法を編み出します。できあがったメロディが音楽としてとてもよくできていることに博士自身がびっくりします。モーツァルトやベートヴェンのメロディと同じフレーズさえ出てきます。
毎年トマトで実験をおこなってみていますが、目覚ましい成果が上がっています。パン酵母にも試みたところ味が格段によくなったということです。1993年7月23日の朝日新聞には「うどんには四季、田園は食パンに」という記事が載っています。これもステルンナイメール博士が分析したところ、田園についてはADHの合成を活発にするメロディの一部が田園にあることがわかりました。ヴィヴァルディの四季では、味噌の酵母の出芽に関係するアクチンの音楽に似ていることがわかりました。
人間のタンパク質にも影響を与えるため、病気が改善することもいろいろとわかっています。ただし、その音楽の量など知識がないと副作用を与えることもあるということで、細かい作り方などは公開されていません。
自然を細かい部分に分解して研究をする現代科学では、そのつながりから生まれる機能などが判りにくくなっているようです。さらに総合的なアプローチとして、このような方法がさらに研究されていくとよいですね。
※タンパク質の音楽へようこそ(著者:深川洋一) http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/index.html
タンパク質は20種類のアミノ酸から合成されますが、合成時に起きる波動の振動数を平均律に置き換えることにより、音楽が作られるというもの。この音楽を聞かせることで、病気が改善したり、植物がよりたわわに実ったりと、いくつもの実験報告がされています。
この方法は物理学者のジョエル・ステルンナイメール博士が提案しています。実はこの博士、シンガーソングライターとしてエヴァリストという名前でレコードを出したら爆発的なヒット。その資金で研究を続けたと云う変わり種です。当初素粒子の質量についての研究をしていたステルンネイメールですが、ノーベル物理学賞を受賞したアンリ・ポワンカレ研究所のド・ブロイ博士の推薦を得て、アメリカ・プリンストン大学に助手のポストを約束されました。ベトナム戦争で資金不足となった当時の研究所がそのあおりをくらって、到着してみたら席がなかったということに。パリにもどり、知り合いのレコード会社から自分で作った曲を出したところベスト・セラーになり、テレビ・映画にも出演し一役スターに。その間も素粒子の質量研究をしている折、分布図が音楽の周波数に当てはまることを発見。1983年に「素粒子の音楽」という論文をまとめました。日本では大野乾(すすむ)博士がDNAの音楽を発表しており、そのほかいくつか遺伝子の音楽など、音楽に変換する試みはされています。
ステルンナイメール博士は彼らとはまた別の方法で、DNAの音楽から発展させ、タンパク質を音楽に置き換える方法を編み出します。できあがったメロディが音楽としてとてもよくできていることに博士自身がびっくりします。モーツァルトやベートヴェンのメロディと同じフレーズさえ出てきます。
毎年トマトで実験をおこなってみていますが、目覚ましい成果が上がっています。パン酵母にも試みたところ味が格段によくなったということです。1993年7月23日の朝日新聞には「うどんには四季、田園は食パンに」という記事が載っています。これもステルンナイメール博士が分析したところ、田園についてはADHの合成を活発にするメロディの一部が田園にあることがわかりました。ヴィヴァルディの四季では、味噌の酵母の出芽に関係するアクチンの音楽に似ていることがわかりました。
人間のタンパク質にも影響を与えるため、病気が改善することもいろいろとわかっています。ただし、その音楽の量など知識がないと副作用を与えることもあるということで、細かい作り方などは公開されていません。
自然を細かい部分に分解して研究をする現代科学では、そのつながりから生まれる機能などが判りにくくなっているようです。さらに総合的なアプローチとして、このような方法がさらに研究されていくとよいですね。
※タンパク質の音楽へようこそ(著者:深川洋一) http://www.bekkoame.ne.jp/~dr.fuk/index.html











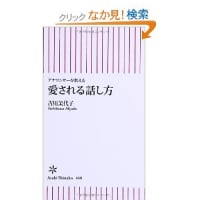
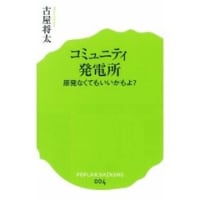




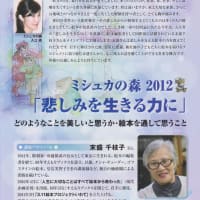
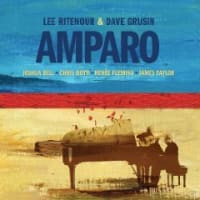

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます