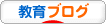次回の「場所としての学校図書館」勉強会は、神奈川県立田奈高校を訪問して、図書館とNPO法人が協働して進めておられる交流相談の取り組みについてお話をうかがいます。
田奈高校の図書館(通称「ぴっかり図書館」)では、毎週一回程度、カフェ(通称「ぴっかりカフェ」を開いて生徒たちが自由に話せる場を設け、日常会話から生徒たちの不安や悩みを聴きとって解決策につなげる活動を行っておられます。その運営にNPO法人パノラマも参加して、生活困窮など様々な困難を抱えている(あるいは、そのリスクの高い)高校生に対して企業を紹介し、職業体験やアルバイトをとおして卒業後の就労を支援する活動を展開しておられます。
勉強会では司書の松田ユリ子さんとNPO法人パノラマの石井正宏さんにそれぞれの立場からお話してただき、学校図書館と地域のNPOが協働して、このような活動を行うことの意味を考えたいと思います。
学校図書館関係者にかぎらず広く関心のある方をお誘いくだされば幸いです。
勉強会の日程は下記のとおりです。(開始時間が以前にお知らせしたのと変わっていますので、ご注意ください)
「場所としての学校図書館」勉強会(第6回)
日時:1月11日(日)13時30分~16時30分(できるだけ13時20分以後にお越しください)
場所:神奈川県立田奈高校図書館
東急田園都市線『青葉台駅』よりバスをご利用ください(「田奈高校」下車)
テーマ:田奈高図書館と「ぴっかりカフェ」
お問い合わせ及び参加を希望される方は下記のアドレスにメールをください。
holisticslinfo#gmail.com (#を@に変えて送信してください)
【参考資料】
・田奈高図書館における交流相談については、以下の文献をご覧ください。
「高校生の潜在的ニーズを顕在化させる学校図書館での交流相談‐普通科課題集中校における実践的フィールドワーク」鈴木晶子・松田ユリ子・石井正宏(東京大学大学院教育学研究科、生涯学習基盤経営研究、第38号、2013年度)
・「ぴっかりカフェ」のコンセプトを説明したサイト(動画もあります)はこちらにあります。
有給職業体験プログラム「バイターン」実施プロジェクト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆
わたしは、この「ぴっかりカフェ」の試みを、これまで何度か紹介してきたヘルシンキ大学のユリア・エンゲストローム教授の用語を借りて「ノットワーキング」と「拡張による学習」の試みととらえて、これからの学校や学校図書館のあり方を考える手がかりにしたいと考えています。
複数の活動システム(activity system)が結び目(knot)をつくって新たな活動を展開することをノットワーキング(knot-working)と呼びます。活動システム相互の関わりの中から、単独のシステムでは担いきれない新たな活動対象とツールを生みだすことによって、ノットワーキングに関わる活動システム自体が変容していくことを「拡張による学習」といいます。そのような活動は、今日の急速な社会的・文化的変化に対応できなくなっている固定的な組織や制度を変革するために有効ではないかと考えられます。
「ぴっかりカフェ」は、困難を抱えた高校生と適切な人材を求める地域の企業とをつなぐという活動のために田奈高図書館とNPO法人パノラマという二つの活動システムのノットワーキングによって生み出されたツールといえるでしょう。そこには二者だけでなく、その活動を容認あるいは支援してくれる田奈高の教師たちやカフェを利用してくれる生徒たち、さらにその生徒たちを受け入れてくれる地域の企業が参加しなければ成り立たないことを考えると、それが単に学校図書館の中だけの局所的な試みではなく、そこに参加する人々をとおして学校や社会のあり方を変えていく活動であることは明らかです。
学校図書館が、このようなノットワーキングを始動するには、まず生徒たちが置かれている文脈(背景)を視野に入れて彼らの問題を把握し、固定化された従来の図書館業務では対応しきれないことを課題として認識することが必要でしょう。その上でノットワーキングを遂行していくためには、そこに関わる当事者間の関係から生じる多様なコンテクストに対応できる「流動的な知性」(Fluid Intelligence)と状況の全体を見通す感性も求められるでしょう。次回の勉強会では、そういった点についても考えてみたいと思います。
ちなみに「活動理論」や「場所としての学校図書館」に関する私の問題意識については、下記の記事をご覧ください。
学校図書館専門職とノットワーキング:「イフォメーション・パワー」の先にみえる協同の形(2005/12/25)
間接サービスから直接サービスへ(2012/12/31)
場所と場による学校図書館づくり(2014/7/11)
居場所としての学校図書館を考える(2014/8/16)