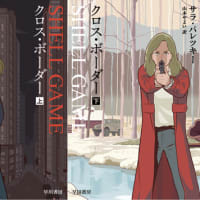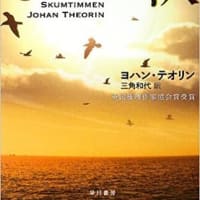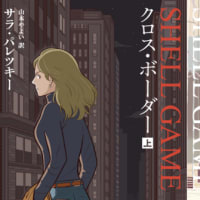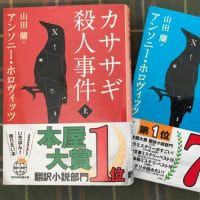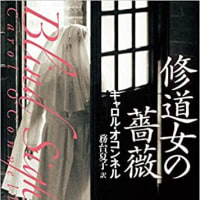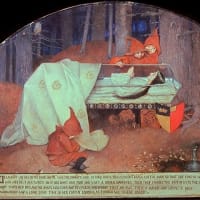前々から面白いと聞いていたので、家族も旅行に行ったのでこの隙にと読み始めた『イスタンブールの群狼』(ジェイソン・グッドウィン著・和爾桃子訳 早川書房)
前々から面白いと聞いていたので、家族も旅行に行ったのでこの隙にと読み始めた『イスタンブールの群狼』(ジェイソン・グッドウィン著・和爾桃子訳 早川書房)読み始めて気がついたのは、「トルコが舞台じゃん」ということ。
家族が旅行に行った先は、まさしくそのトルコ。
どれどれと旅程表を見れば、トプカピ宮殿、カッパドキア、世界遺産、おやおや、この本の舞台そのままじゃないか、と地理に疎いのがバレバレのおどろきよう。
シンクロなんぞと喜ぶ前に、イスタンブールと聞いてトルコと反射的に思い浮かべなかった自分の情けなさを噛みしめるべき、にゃのだ。
 去年ハヤカワ文庫から出たこの本は、19世紀のオスマントルコが舞台にゃり。
去年ハヤカワ文庫から出たこの本は、19世紀のオスマントルコが舞台にゃり。主人公はヤシムという白人の宦官。
宦官なので、男子禁制のトプカピ宮殿のハレムにも出入り自由。
オスマントルコ帝国近衛新軍の4人の士官が殺された事件と、宮廷の女奴隷が絞殺された事件の解決を申し付けられる。
国を失った、亡国のポーランド大使や思春期前に去勢された女装のコサック舞踏手。黒人の宦官。なんだか、退廃ムードただよう、エキゾチックなイスタンブール。
内容もさることながら、克明に描写されていく都市の風景が、読み手を引き込んでいきます。
 「ヤシムは服を着てスリッパをつっかけ、フックにかけてあった財布をもっておもてに出た。角をみっつ曲がってカラ・ダウト街へ。濃く甘いコーヒー二杯とパクラヴァをひとつ頼んだ。たっぷりの油で焼き、蜂蜜をかけたパイ菓子だ。」
「ヤシムは服を着てスリッパをつっかけ、フックにかけてあった財布をもっておもてに出た。角をみっつ曲がってカラ・ダウト街へ。濃く甘いコーヒー二杯とパクラヴァをひとつ頼んだ。たっぷりの油で焼き、蜂蜜をかけたパイ菓子だ。」
「ガラタ岬のふもとにたたずむ小さなレストランに早めにつくと、ヤシムはボスポラスの海を一望できる、奥まった静かな席を選んだ。ボスポラス会ってのイスタンブールだ。ヨーロッパとアジアをつなぐ交差点。黒海から地中海への出口。今も昔も世界貿易の一大集積場だ。今この席から見えるのは、ヤシムが大好きな海だ。砲金色ににぶく光る細長いおもてに、かって建った街の面影を映して。」
そんな本のなかの風景が、なかなか素敵なんです