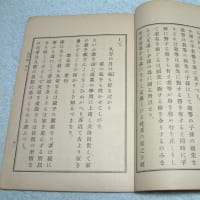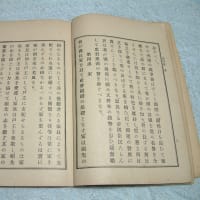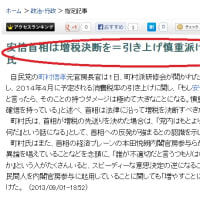http://blog.goo.ne.jp/maniac_club/e/221ee54595fe7f0429a04ad08e23e9b8
思いつきでダラダラ書いているので、本題に繋がっていかないのだが・・・(苦笑)
企業を構成する人たちのルーチンワーク化・・・ここでいうルーチンワークとは、創造的活動を行わない仕事の繰り返しと定義したいのだが(前のエントリー参照)・・・資金の円滑な流動を阻害する要因となりうる。
利益の構造はエントリーの第一回で述べたが、「利益=売上高-費用」である。会計上、売上高が一定で費用も一定であれば会計上の利益は生み出され続ける。
先般、老舗の倒産情報を見たのだが、売上高や借入金の額はさほど悪くなかった。これも先にエントリーしたのだが、”倒産”というのは売上高の低下や借入金の額にあるのではなく、”資金繰り”の悪化にその要因がある。要は”収入”のサイクルと”支出”のサイクルが合わないことに原因があるわけである。
余談ではあるが、現在のように不況下からの転換時期というのは資金繰りに窮する企業が少なくはない。売上が低迷して運転資金の大半を不況下での資金繰りに消費している状況で急激な需要の拡大(売上の上昇)で費用が膨らみ、収入のサイクルよりも前に多額の支出が発生することに起因する。
余剰資金があればよいのだが、余剰資金の不足のために起こる現象である。この回避には手形決済による費用の支払いの先送り、金融機関からの繋ぎ融資などが挙げられる。しかしながら、中小零細企業では手形や繋ぎ融資などの方法では費用の先送りは難しいケースが多い。(政府のセーフティ・ネットで売掛金を担保に資金貸付の制度もあるが・・・)
急速な景気拡大というのは、体力のない企業にとっては諸刃の剣になりかねない。特に現状のような世界経済の変化要因が複数ある場合には特に・・・
さて、本題に戻るのだが・・・。
企業全体のルーチンワーク化と資金繰り。この二つがどのように関連するのかを説明せねばならない。
これまでの説明から大体の方は”売上高”の向上が望めないと理解されるかと考える。確かに同じ取引先と同じ金額で取引していくと取引先が急速な成長を遂げない限りは自社の売上高の向上は望めない。
新しい顧客を生み出さねば売上の向上は見込めないのだろうか?
この結論を出す前に少し考えなばならないことがある。
費用の側面をおさらいしよう。会計上は費用として一括りにされるが、費用を細分化すると大きく分けて二つに分類される。
一つは売上高に左右されずに一定額発生する固定費用。そして、もう一つは売上高に比例して発生する変動費用である。
前者は事務所費用や人件費など企業自身を形成、維持するために使用される費用であり、後者は仕入や製造費など売上に伴い変動する費用である。
会計上は”電気料金”は”水道光熱費”として分類されるが、この分類に基づくと”基本料金”は固定費で”使用料金”は変動費となる。つまり、会計関連帳簿にはこの分類は明確にはなされないことになる。
一般に不況耐性のある企業は固定費が低い傾向にあると考えられる。これは売上高が低迷しても、出費が抑えられることで資金繰りへの悪影響を抑えることができるからである。
これは”損益分岐点売上高”という考えが元になっているのだが、損益分岐点とはその名の通り、費用面から見た利益と損失境目であり、”最低売上高”と表現する識者も少なくはない。
損益分岐点は下記の式にて算出される。
損益分岐点売上高=固定費/1-変動比率 ※変動比率は変動費/売上高
このシンプルな式で”凡そ”の売上高を算出することはできるが判断材料とするには心許ない部分は少なくない。
会計帳簿による場合は”結果”数値となり、あくまでも”参考数値”となる。前期における会計数値から次期の予算を産出しても現代のような急激な経済環境の変化の中では参考数値に留まざるを得なくなる。そして、最も注視せねばならないのが、”資金繰り”が示されるわけではないということである。
私のこのエントリーに興味を持たれた方の多くは、世の中にあるキャッシュ・フローに関する書籍や講演などを見聞きされていると考える。(違う側面からご興味をもたれた方も少なくはないと思いますが・・・)
ところが、多くの方が自分たちの現状と見聞きしたものとの間に”違和感”をもたれてはいないだろうか?
書籍や講演というのは、見聞きする人全体が理解できるように”一般論”を中心に展開しているので”違和感”が生じていると感じられるかもしれない。
しかし、その”違和感”が組織の中にある”問題点”から生じているものであったとしたらどうであろう?
企業内の実情と理屈が相容れない場面に遭遇し、それを理屈だからと考えてはいないだろうか?(あえて、理論を理屈とさせていただく・・・)
その”実情”こそが”問題点”である。と考えてみてはいかがだろう。見えないものが少し透けて見えるのではなかろうか?
このエントリーのタイトル「経営状態が安定してきた時こそコスト削減の努力のできる時・・・。」はコストを金額に留めることなく、企業そのものの行動の再構築によって、”生き残る企業”に変化させるタイミングであるということを示唆できればと考える次第である。