the playground of the east
北の端の花崗岩の断崖は「親知らず、子知らず」、つまり「親も構っていられないし、子も構っていられない」である。
けれでも、日本の山岳風景に一番特徴のある魅力とロマンスを与える千変万化の山の姿と輪郭を最大限に表わしているのは、北アルプスの諸峰である。
「恐らく自然美がかくも限りなく多様に山岳という形やおびただしく豊かな木々と花とで表われている国はほかのどこにもない」
奥秩父のなかで、それは金峰山だが、オパールや銅、そして日本で一番良質の水晶が発見される。
硯島からは、硯に使う一番質のいい粘土性のスレートが出る。
非常に有名な硫黄泉の1つは、愛の病のほかは、すべての軽い病気が治ると強く言われている。
しかしながら、日本人の心には、日本にある沢山の活火山の破壊的な活動への恐怖感から、山への恐怖心もしっかり根をはっている。実際、1000年以上も前にだが、南西にある九州のこうした火山の1つが恐ろしい活動を始めそうなので、驚いて「従四位」のくらいを与えたことを聞いている。
山伏は大きな法螺貝を携えて、霧の多い天候のときとか夜には、一行の人たちを離れないようにしておくのに吹いた。
弘法大使のやったほかの業績として、平仮名という日本の「草書体」の50音図の発明がある。
小島烏水
「山は真理の聖なる王座です。山は私を永遠に楽しませる沈黙の雄弁を持っています」
その記事は、ある熱心な登山家が徳本峠の北側から穂高山の花崗岩の城壁と岩塔の雄麗な光景を初めて見たときの感動を書いたものである。
「私がその雄大な眺めと対面したとき、歓喜のあまり、ほとんど気も狂わんばかりだった。私はまるで、夢を見ているように感じた。・・・その変化は、神の創造物にほかならない穂高の姿をした理想の巨人によって引き起こされると、私は心の底から感じるのである」
甲府の名物は「月の雫」という菓子だが、これは熟した黒い葡萄を砂糖の衣でくるんだもの。
その向こうには、鋸山とはうまい名を付けた、鋸歯状の尾根が聳えていた。
私はこの鳳凰山ーー不死鳥の峰ーーを1904年の夏の「新しい」遠征リストの最初に選んだ。
それは、一部分は、それに接近不可能と言い立てられたことに刺激され、他の一部分は、黒々と切り立つ尾根から屹(そばだ)っている、その鋭い岩塔の挑戦的な外容からしてである。
この山を、私は今まで何度も、近くの峰々から好奇心をかりたてられて、見つめてきたのだった。
鳳凰山の尾根で一番壮大な地点は地蔵岳だが、ここにわれわれは、大室から1時間半呑気に登って着いた。これは、幻想的な形をし、白い色から紫に変わっていく岩が、こなごなになった斜面から聳えている。
中房温泉の湯は硫黄と炭酸瓦斯を含んでいるので、飲んでも、はいっても、身体を健康にし、人の役に立つ。この温泉は行き易いし、そこまで行き着く旅が楽しい。余り人に知られていない日本のうちで、たしかに一番魅力があると言っていい場所の1つに、将来きっとなることであろう。
梓川谷の向こうに、焼岳と面と向かい、それよりも600フィートほど高い霞岳という、嶮しい大岩でできた花崗岩の巨大な塊が聳え立っている。
花崗岩の幻想的な尖塔が歩哨のように突っ立っている。
穂高岳は別名、岳川岳と言われている。
左手に見える雪襞のついた杓子岳の花崗岩のピラミッドを、何とも言えない美しいバラ色と黄金色で照らしていた。
東の方を振り返ると、戸隠の濃藍の山稜が、棉花と羊毛をまぜた灰色の海のなかに横たわる、長い鯨の背骨のように聳えていた。
太平洋の横浜から日本海岸の直江津に着いた。
記者は、花崗岩の岩面の上高い所を狭い岩棚に沿って走って行ったり、数え切れないトンネルに入ったり出たりする。
われわれは古い町の大町に着き、対山館に入ると・・・
その日、われわれの生活は本当に登り降りの多いものだった。
というのは、燕岳の鞍部から大天井岳の頂へとその北尾根を通るのに4時間かかったが、高度にほとんど変化がなかったからである。この最後の時間に、最終峰へと急な斜面を登っていった。大天井岳は、今や新しく見つけた友だちとなった。この山は、槍尾根の東に当たる分離峰だが、この山の全長に亘って槍尾根と平行しており、そうした位置から、目を見張るような展望が得られるのである。
翌朝になってみると、空は雲もなく美しく晴れ渡り、槍から穂高の岩塔まで走るあの尾根筋の大きな断崖や雪の峡谷が、西の方へに、壮麗な展望を繰り広げていた。
南東には、先の日の旧友、常念岳が聳え立っていた。その向こうには、遥か南に薄紫色の富士が姿を見せていた。
全く突然に、古い徳本小屋の低くて幅広い屋根が、樺や松のなかに茶色の姿を見せてきた。われわれは大天井岳の頂上から11時間踏破してきたのだが、愉快な鋸歯状の尾根に沿う「尾根歩き」は、幸福な成功を収めて、終わりを告げた。
今年、上高地に私たちが告げる「さようなら」は特別悲しい別れだった。
また来ますとはできない約束だった。
人影のない田代池のそばを通り過ぎた。
この鏡のような水面は、穂高の灰色の断崖と輝く雪を静かに映していた。
北の端の花崗岩の断崖は「親知らず、子知らず」、つまり「親も構っていられないし、子も構っていられない」である。
けれでも、日本の山岳風景に一番特徴のある魅力とロマンスを与える千変万化の山の姿と輪郭を最大限に表わしているのは、北アルプスの諸峰である。
「恐らく自然美がかくも限りなく多様に山岳という形やおびただしく豊かな木々と花とで表われている国はほかのどこにもない」
奥秩父のなかで、それは金峰山だが、オパールや銅、そして日本で一番良質の水晶が発見される。
硯島からは、硯に使う一番質のいい粘土性のスレートが出る。
非常に有名な硫黄泉の1つは、愛の病のほかは、すべての軽い病気が治ると強く言われている。
しかしながら、日本人の心には、日本にある沢山の活火山の破壊的な活動への恐怖感から、山への恐怖心もしっかり根をはっている。実際、1000年以上も前にだが、南西にある九州のこうした火山の1つが恐ろしい活動を始めそうなので、驚いて「従四位」のくらいを与えたことを聞いている。
山伏は大きな法螺貝を携えて、霧の多い天候のときとか夜には、一行の人たちを離れないようにしておくのに吹いた。
弘法大使のやったほかの業績として、平仮名という日本の「草書体」の50音図の発明がある。
小島烏水
「山は真理の聖なる王座です。山は私を永遠に楽しませる沈黙の雄弁を持っています」
その記事は、ある熱心な登山家が徳本峠の北側から穂高山の花崗岩の城壁と岩塔の雄麗な光景を初めて見たときの感動を書いたものである。
「私がその雄大な眺めと対面したとき、歓喜のあまり、ほとんど気も狂わんばかりだった。私はまるで、夢を見ているように感じた。・・・その変化は、神の創造物にほかならない穂高の姿をした理想の巨人によって引き起こされると、私は心の底から感じるのである」
甲府の名物は「月の雫」という菓子だが、これは熟した黒い葡萄を砂糖の衣でくるんだもの。
その向こうには、鋸山とはうまい名を付けた、鋸歯状の尾根が聳えていた。
私はこの鳳凰山ーー不死鳥の峰ーーを1904年の夏の「新しい」遠征リストの最初に選んだ。
それは、一部分は、それに接近不可能と言い立てられたことに刺激され、他の一部分は、黒々と切り立つ尾根から屹(そばだ)っている、その鋭い岩塔の挑戦的な外容からしてである。
この山を、私は今まで何度も、近くの峰々から好奇心をかりたてられて、見つめてきたのだった。
鳳凰山の尾根で一番壮大な地点は地蔵岳だが、ここにわれわれは、大室から1時間半呑気に登って着いた。これは、幻想的な形をし、白い色から紫に変わっていく岩が、こなごなになった斜面から聳えている。
中房温泉の湯は硫黄と炭酸瓦斯を含んでいるので、飲んでも、はいっても、身体を健康にし、人の役に立つ。この温泉は行き易いし、そこまで行き着く旅が楽しい。余り人に知られていない日本のうちで、たしかに一番魅力があると言っていい場所の1つに、将来きっとなることであろう。
梓川谷の向こうに、焼岳と面と向かい、それよりも600フィートほど高い霞岳という、嶮しい大岩でできた花崗岩の巨大な塊が聳え立っている。
花崗岩の幻想的な尖塔が歩哨のように突っ立っている。
穂高岳は別名、岳川岳と言われている。
左手に見える雪襞のついた杓子岳の花崗岩のピラミッドを、何とも言えない美しいバラ色と黄金色で照らしていた。
東の方を振り返ると、戸隠の濃藍の山稜が、棉花と羊毛をまぜた灰色の海のなかに横たわる、長い鯨の背骨のように聳えていた。
太平洋の横浜から日本海岸の直江津に着いた。
記者は、花崗岩の岩面の上高い所を狭い岩棚に沿って走って行ったり、数え切れないトンネルに入ったり出たりする。
われわれは古い町の大町に着き、対山館に入ると・・・
その日、われわれの生活は本当に登り降りの多いものだった。
というのは、燕岳の鞍部から大天井岳の頂へとその北尾根を通るのに4時間かかったが、高度にほとんど変化がなかったからである。この最後の時間に、最終峰へと急な斜面を登っていった。大天井岳は、今や新しく見つけた友だちとなった。この山は、槍尾根の東に当たる分離峰だが、この山の全長に亘って槍尾根と平行しており、そうした位置から、目を見張るような展望が得られるのである。
翌朝になってみると、空は雲もなく美しく晴れ渡り、槍から穂高の岩塔まで走るあの尾根筋の大きな断崖や雪の峡谷が、西の方へに、壮麗な展望を繰り広げていた。
南東には、先の日の旧友、常念岳が聳え立っていた。その向こうには、遥か南に薄紫色の富士が姿を見せていた。
全く突然に、古い徳本小屋の低くて幅広い屋根が、樺や松のなかに茶色の姿を見せてきた。われわれは大天井岳の頂上から11時間踏破してきたのだが、愉快な鋸歯状の尾根に沿う「尾根歩き」は、幸福な成功を収めて、終わりを告げた。
今年、上高地に私たちが告げる「さようなら」は特別悲しい別れだった。
また来ますとはできない約束だった。
人影のない田代池のそばを通り過ぎた。
この鏡のような水面は、穂高の灰色の断崖と輝く雪を静かに映していた。










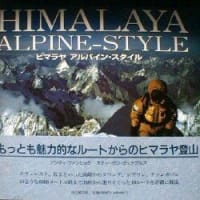
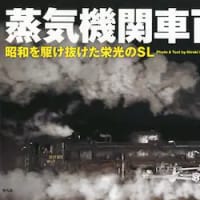
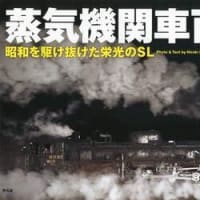
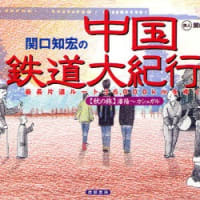
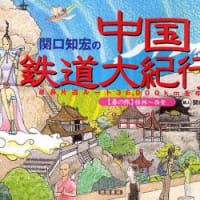
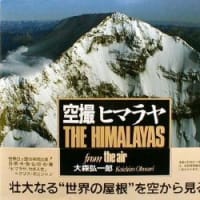

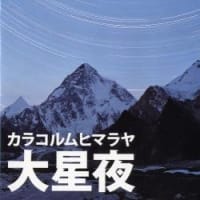
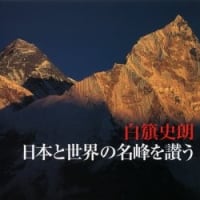
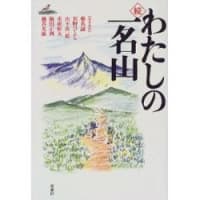
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます