
すべての護衛艦に乗りこんでいるものはそうだったが、油槽船に乗っている人たちを皆心から尊敬していた。彼らは3週間も4週間もかかる航海の間じゅう、火薬の樽の上に立っているのと同様の生活をしていた。彼らの船で運んでゆく油は、戦争を継続するのに一日も欠かすことのできないもので、そしてこれほど危険な積荷はなかった。・・・あるいは機関銃の弾が一発当たってさえも、船全体が火の塊りに変じるのだった。
彼らは皆その油槽船が好きになっていた。
というのは、この船は明らかに潜水艦にとって逃がすことができない獲物だった。それで航海の終わりが近づくにつれて、誰もがこの船だけはどうしても守らなければならないという気持ちになった。
どんなに速く泳げるものも油が広がっていく速力にはかなわず、そのうちに油に追いつかれて、炎が彼等の身体をなめ、やがて全身が炎に包まれた。
見張りの一人はまだ17歳ぐらいの若い水兵で、燃えている船の方を見ながら涙を流していた。そのような無残な死に方をしている人たちのために、何一つできずにいることに対する怒りでもあり、悲しみでもあり、そしてまた、絶望でもあるかもしれなかった。
電撃機は発見するのが一番難しくて、水の上を低く飛んでくるのが、灰色の光線のなかではなかなか見つけることができず、それからジグザグをはじめてこっちの照準を狂わせ、船とすれすれのところまできて魚雷を投下するので、かわす暇などはなくて船にあたるのをただ待っている間に、向こうはもうどこかへいってしまっているのだった・・・
それまで6時間続けて同じ単調な音を発していた水中聴音機が、そのときになって今までとは違った鉄製の物体との接触でなければ聞けない音を打ちだしはじめた。
油が浮いているだけではまだ潜水艦を沈めたことにまだ足りなかった。
彼は水中に爆発が起こって、木片や、人間の肢体の一部が海面に上がってくるのでなければ気がすまなかった。油はたいしたことではない故障の結果かもしれないし、それは敵の策略でさえもあり得た。















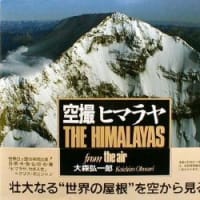




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます