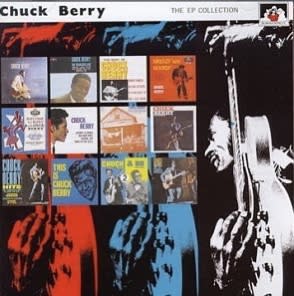2022年12月16日(金)

#397 VAN HALEN「炎の導火線」(ワーナーミュージックジャパン 20P2-2617)
米国のロック・バンド、ヴァン・ヘイレンのデビュー・アルバム。78年リリース。テッド・テンプルマンによるプロデュース。
エドワード(G)とアレックス(Ds)のヴァン・ヘイレン兄弟、マイケル・アンソニー(B)、そしてデイヴィッド(デイヴ)・リー・ロス(Vo)の4人編成のヴァン・ヘイレンは、元々はカレッジ内で作られたバンド。
当初は有名ハード・ロック・バンドのカバーとオリジナルを取りまぜてやっていた。まぁ、よくあるアマチュア・バンドのひとつに過ぎなかったわけだ。
しかし、エディことエドワードのギター・プレイは、他のバンドのそれを大きく凌駕する、テクニックとアイデアに満ち溢れていた。
カリフォルニアのクラブで演奏しているうちに、その評判が各所に伝わったのかチャンスをつかみ、大手のワーナーブラザーズと契約、このアルバムのリリースにこぎつけた。
セールスは好調、瞬く間に150万枚を売上げ(全米19位)、まったくの新人バンドとしては、破格のスタートとなった。
ファンの間ではやはり、エディの超絶技巧ギターが、話題の中心であった。「あの音はいったいどうやって弾いているんだ?」と、全米のギター・キッズどもを騒がせたのである。
エディのタッピング奏法(日本のギター雑誌ではライトハンド奏法とも言われたりした)は、それまでの速弾き奏法とは一線を画した、新鮮なものだった。
70年代は数々の新しいロックギター・ヒーロー、たとえばリッチー・ブラックモア、アルビン・リー、スティーブ・ハウ、ブライアン・メイ、ロリー・ギャラガー、スティーブ・ルカサーといったテクニシャンたちにスポットが当たってきたが、エディはその最後の最後に登場した、最強ヒーローだった。
その音は、ワンアンドオンリーの独創品であり、後続のハード・ロック系ギタリストたちはこぞって彼のテクニックを模倣するようになる。
ジミ・ヘンドリクス以来の逸材、ギターの革命児、そんな評価をデビュー以来ずっと受け続けてきたエディだったが、2020年10月、がんのため65歳の若さで亡くなった。
まだまだ現役ロッカーとして活躍出来たであろうに、残念でならない。
そんな彼を偲んで、「このエディがスゴい!ベストフォー」を組んでみたい。
第4位「ユー・リアリー・ガット・ミー」
デビュー・シングルでもあり、全米36位のクリーン・ヒットとなった。英国のバンド、キンクス64年のヒット・シングルのカバー。
3分足らずの短尺に、彼らのセールス・ポイントを全て凝縮した一曲。すなわち、エディのフィンガー・ハーモニクス、タッピング、アーミングを駆使したプレイ、デイヴの野獣じみたシャウト、リズム隊のダイナミックなビート。
あのキンクスがゴリゴリのハード・ロックへと変身を遂げるとは。当時、ラジオで聴いてビックリしたものだ(種明かしをすると、リック・デリンジャーが彼のバンド「デリンジャー」のライブで前年にやったバージョンが、どうやらネタ元みたいなんだけどね)。
この曲こそヴァン・ヘイレンのAであり、Zである。
第3位「アイス・クリーム・マン」
アコースティック・ブルースのスタイルで始まり、いきなりハード・ロックにお色直し、というユニークな構成。
間奏のギター・ソロは、エグいまでにエディ節全開である。笑ってしまうほど。
オリジナルは黒人ブルースマン、ジョン・ブリムの作品。いなたく、ほのぼのとしたあのブルースが、ここまで変わるとは。まさにアレンジの妙である。
第2位「アイム・ザ・ワン」
ヴァン・ヘイレンを語る上で忘れてならないのは、そのボーカリストの確かな実力だろう。オリジナルのデイヴ然り、後任のサミー・ヘイガー然り。
どれだけエディがスゴいギタリストであろうと、ボーカルがそれに太刀打ちするだけのものを持っていないと、バンドとして成立しない。バランスが取れない。
その意味で、陰の功労者としてのボーカリストのスゴさにも触れておかないと、ね。
普通、ボーカリストがバンドの立役者なんだけど、ヴァン・ヘイレンだけはギタリストが立役者というのが、なんともおかしい。
この曲でも、デイヴのスピーディ極まりない歌が、バックの超高速ビートに完全に拮抗していて、息も詰まるような展開だ。
エディも負けじとフル・スピードで弾きまくり。お腹いっぱいになる。
終盤、憂歌団の「おそうじオバチャン」みたいなおチャラケもあって、思わずニッコリ。
スピード感に溢れた、アルバム随一のパワー・チューンであります。
第1位「暗闇の爆撃(Eruption)」
短いインストゥルメンタルなれど、この曲ほどリスナーにショックを与えたナンバーはあるまい。
パガニーニの超絶技巧ヴァイオリン・ソロにも匹敵する破壊力を持つ、エディのタッピングをとくと味わってくれ。トリルのスゴさに、悶絶しそうである。
エディの死により、ヴァン・ヘイレンの42年にわたる歴史は唐突に終わりを告げてしまった。
だが、その輝けるサウンドは12枚のオリジナル・アルバムやライブ・アルバム等で、いつまでも聴くことが出来る。
偉大なる爆撃機、ヴァン・ヘイレンよ永遠に。
<独断評価>★★★★☆
米国のロック・バンド、ヴァン・ヘイレンのデビュー・アルバム。78年リリース。テッド・テンプルマンによるプロデュース。
エドワード(G)とアレックス(Ds)のヴァン・ヘイレン兄弟、マイケル・アンソニー(B)、そしてデイヴィッド(デイヴ)・リー・ロス(Vo)の4人編成のヴァン・ヘイレンは、元々はカレッジ内で作られたバンド。
当初は有名ハード・ロック・バンドのカバーとオリジナルを取りまぜてやっていた。まぁ、よくあるアマチュア・バンドのひとつに過ぎなかったわけだ。
しかし、エディことエドワードのギター・プレイは、他のバンドのそれを大きく凌駕する、テクニックとアイデアに満ち溢れていた。
カリフォルニアのクラブで演奏しているうちに、その評判が各所に伝わったのかチャンスをつかみ、大手のワーナーブラザーズと契約、このアルバムのリリースにこぎつけた。
セールスは好調、瞬く間に150万枚を売上げ(全米19位)、まったくの新人バンドとしては、破格のスタートとなった。
ファンの間ではやはり、エディの超絶技巧ギターが、話題の中心であった。「あの音はいったいどうやって弾いているんだ?」と、全米のギター・キッズどもを騒がせたのである。
エディのタッピング奏法(日本のギター雑誌ではライトハンド奏法とも言われたりした)は、それまでの速弾き奏法とは一線を画した、新鮮なものだった。
70年代は数々の新しいロックギター・ヒーロー、たとえばリッチー・ブラックモア、アルビン・リー、スティーブ・ハウ、ブライアン・メイ、ロリー・ギャラガー、スティーブ・ルカサーといったテクニシャンたちにスポットが当たってきたが、エディはその最後の最後に登場した、最強ヒーローだった。
その音は、ワンアンドオンリーの独創品であり、後続のハード・ロック系ギタリストたちはこぞって彼のテクニックを模倣するようになる。
ジミ・ヘンドリクス以来の逸材、ギターの革命児、そんな評価をデビュー以来ずっと受け続けてきたエディだったが、2020年10月、がんのため65歳の若さで亡くなった。
まだまだ現役ロッカーとして活躍出来たであろうに、残念でならない。
そんな彼を偲んで、「このエディがスゴい!ベストフォー」を組んでみたい。
第4位「ユー・リアリー・ガット・ミー」
デビュー・シングルでもあり、全米36位のクリーン・ヒットとなった。英国のバンド、キンクス64年のヒット・シングルのカバー。
3分足らずの短尺に、彼らのセールス・ポイントを全て凝縮した一曲。すなわち、エディのフィンガー・ハーモニクス、タッピング、アーミングを駆使したプレイ、デイヴの野獣じみたシャウト、リズム隊のダイナミックなビート。
あのキンクスがゴリゴリのハード・ロックへと変身を遂げるとは。当時、ラジオで聴いてビックリしたものだ(種明かしをすると、リック・デリンジャーが彼のバンド「デリンジャー」のライブで前年にやったバージョンが、どうやらネタ元みたいなんだけどね)。
この曲こそヴァン・ヘイレンのAであり、Zである。
第3位「アイス・クリーム・マン」
アコースティック・ブルースのスタイルで始まり、いきなりハード・ロックにお色直し、というユニークな構成。
間奏のギター・ソロは、エグいまでにエディ節全開である。笑ってしまうほど。
オリジナルは黒人ブルースマン、ジョン・ブリムの作品。いなたく、ほのぼのとしたあのブルースが、ここまで変わるとは。まさにアレンジの妙である。
第2位「アイム・ザ・ワン」
ヴァン・ヘイレンを語る上で忘れてならないのは、そのボーカリストの確かな実力だろう。オリジナルのデイヴ然り、後任のサミー・ヘイガー然り。
どれだけエディがスゴいギタリストであろうと、ボーカルがそれに太刀打ちするだけのものを持っていないと、バンドとして成立しない。バランスが取れない。
その意味で、陰の功労者としてのボーカリストのスゴさにも触れておかないと、ね。
普通、ボーカリストがバンドの立役者なんだけど、ヴァン・ヘイレンだけはギタリストが立役者というのが、なんともおかしい。
この曲でも、デイヴのスピーディ極まりない歌が、バックの超高速ビートに完全に拮抗していて、息も詰まるような展開だ。
エディも負けじとフル・スピードで弾きまくり。お腹いっぱいになる。
終盤、憂歌団の「おそうじオバチャン」みたいなおチャラケもあって、思わずニッコリ。
スピード感に溢れた、アルバム随一のパワー・チューンであります。
第1位「暗闇の爆撃(Eruption)」
短いインストゥルメンタルなれど、この曲ほどリスナーにショックを与えたナンバーはあるまい。
パガニーニの超絶技巧ヴァイオリン・ソロにも匹敵する破壊力を持つ、エディのタッピングをとくと味わってくれ。トリルのスゴさに、悶絶しそうである。
エディの死により、ヴァン・ヘイレンの42年にわたる歴史は唐突に終わりを告げてしまった。
だが、その輝けるサウンドは12枚のオリジナル・アルバムやライブ・アルバム等で、いつまでも聴くことが出来る。
偉大なる爆撃機、ヴァン・ヘイレンよ永遠に。
<独断評価>★★★★☆