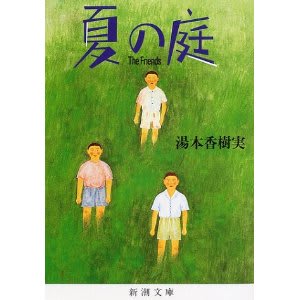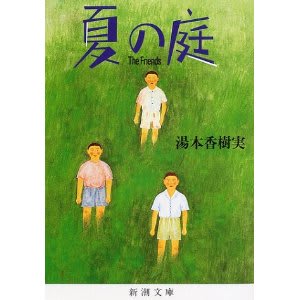
「夏の庭 The Friends」
湯本 香樹実 著 新潮文庫
いろいろ受賞していて、映画にもなりました。
平成4年に福武書店刊行、新潮文庫になったのは平成6年。
ちょうど子育て真っ最中で当時は絵本ばかりに目が行っていましたっけ。
今めぐり合えてよかった!
もうご存知かとも思ったのですが、
面白かったのでご紹介します。
小学校6年生の木山、山下、河辺の3人は
塾もサッカークラブもいっしょの3人組。
山下が疎遠だったいなかのおばあさんのお葬式に行ったことから
人の死について興味を抱いた3人は
もうすぐ死にそうなおじいさんの情報を得る。
死んだらどうなるんだろう?
それでおしまいなのかな、それとも…
第一発見者になって、死んだ人ってどんなふうだか見よう…
本人には絶対迷惑をかけないってことで…
ばれないようにと心がけてはいるものの
3人の見張りはすぐにおじいさんに感付かれ
短気な河辺がついに叫んでしまいます。
「ちっくしょう! じじい、よく聞け! オレたちはおまえを見張ってたんだよ!
おまえが死にそうだっていうから、見張ってたんだ!
おまえがどんな死に方をするか、オレは絶対見てやるからな!」(本文のまま)
こそこそ隠れることがなくなって
おじいさんと3人組の距離はぐっと縮まり
洗濯、草取り、スイカ、家の修理、庭の種まきなど
おじいさんを見張っているのだか、おじいさんにこき使われているのだか!
それまでなんにもしないで
ただ少しの食品の買出しと、テレビを見ていただけのおじいさんは
みごとに「復活」した…みたいです。
花火師だったおじいさん
南方の戦地で戦ってきたおじいさん
おじいさんはもう「今にも死にそうな知らない人」ではなくて
サッカーの合宿であったいろんなことを聞いてもらいたい人になっていました。
そして、3人が合宿から帰ってくると…
警察やお葬式や、いろいろなシーンで、
親戚付き合いも全然していなかったおじいさんの死を
心底悲しんでいるのは3人組です。
自分の遺言を3人組に託したおじいさん…
おじいさんにとっても
このひと夏の子供たちとの「友情」は
忘れがたいものとなったにちがいありません。
語り手の「木山」の心の描写が、ていねいで、的確で
気持ちがいいです。
3人それぞれがよく書き分けられています。
笑い所も多く、テンポもよくて一気に読めます。
夕立、スイカ、花火、合宿
夏が溢れていて、面白いですよ。