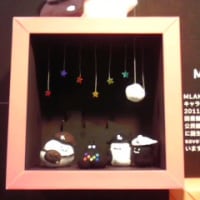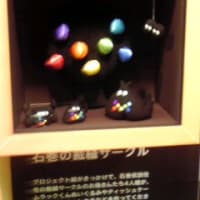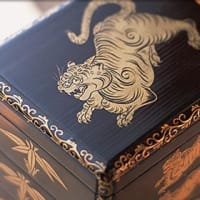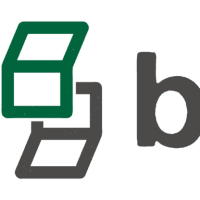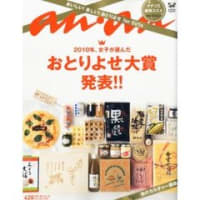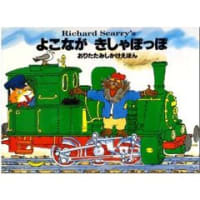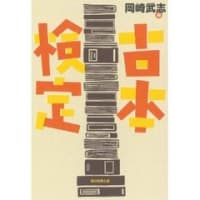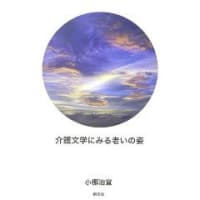第3回の課題:3つ
1.事例紹介(1)(2)(3)から最低限1つを利用し、その使用感をまとめる。
2.新しいOPACの模索に関する文献リストをまとめる。
3.その上で、理想のOPACについて自分の考えをまとめる。
【3.理想のOPACについて自分の考えをまとめる】
●勤務館が公共図書館ですので、「街の公共図書館で求められるサービス」を視点に入れて考えました。
*「街の公共図書館」は大学・専門図書館と違い、
『利用者により「IT・PCへのスタンス/スキル」が大きく異なる』という特徴があります。
~ご年配の方には、「PC・OPACは使えない」・「(これからも)使いたくない」という方がいらっしゃしますが、これは現在のOPACが「楽しくなさそう」・「わざわざ憶えても、それほど便利ではないのでは?」という印象を与えてしまっているためではないかと思います。その解決の為にも、
→「パッと見てわかりやすい」・「簡単・使いやすい」→「とりあえず使ってみようか」と思って頂けるためには?を考えました。
(現場レベルの視点も取り上げた為、「次世代サービス」導入に躊躇している様に見える記述もありますが、「導入のためには、一つ一つ何をして行ったら
良いか?」を具体的に整理するための物です)
●1.「分かりやすい画面」
・「ビジュアル(デザイン)」的に把握しやすい
~色分け・アイコンの工夫など
・「初めてアクセスする方にも使いやすい」構成を
~講義でも「利用者教育をしなければ使えないならば『親切なOPAC』
とは言えない」と言われましたが、システムを作る側の方
(PC・Webに慣れている方)の
「これくらいは常識」という感覚は、公共図書館の利用者の感覚とは
だいぶ異なっている様に感じられます。
*「まずログインするのが常識」として作られているのですが、
館内・館外OPACとも、「最初にログインして下さい」という分かりやすい
表示があれば、検索結果に予約をしようとする段階で、
「あれ?出来ない・そもそもログインって何?」と
戸惑う事も少なくなるのではと思います。
(口頭や冊子でも『使い方』ご案内はしていますが、実際に画面を見て
初めて、「わからない事がある」のに「気づかれる」状態です)
*また、上記で「あれ?」と思われる方にはキーボード入力自体が
スムーズでない方も多く、「入力し直し」だけでストレスとなり、
そのまま「クレーム」になる事もあります。
*「操作性」の向上の必要性
~一例として、「前の画面に戻る」操作の場合、
1.「OPAC画面の「戻る」ボタン」では前の画面(検索結果一覧)に
戻れるのに、
2.「ブラウザの「戻る」ボタンでは「検索入力」の初期画面に
戻ってしまい、検索作業が1からやり直しになってしまう
OPACもあります。
プログラムのミスなのか、ソフトの「ローカル・ルール」の
問題かは不明ですが、
この様な「小さな事」を一つ一つ解消していく事が
「使いやすいOPAC」実現に必要だと思います。
(「次世代OPAC」とは次元が異なる問題ですが…)
*「図書館用語」でなく、分かりやすい言葉での表記を。
・「書架」でなく「本棚」など、「普通に使う言葉」で。
●2.「表記のゆれ・あいまい検索」への対応
・「1文字でも違えば検索がヒットしない」(かな・漢字表記まで合致して
いなくてないけない)が現状ですが、
検索エンジンの様に「~ではありませんか?」と候補を出してくれれば、
と思います。
カウンターへの質問でも正確に書名や著者を憶えていないケースが
殆んどです。
●3.「検索結果」にランキング表示を取り入れる
*検索エンジンのように、ランキング表示を取り入れる。
現在の「五十音順」・「出版年順」ソートに、
「ランキング表示」を付け加えることにより、
・「このジャンルで人気のある本」(≒内容が信用出来る本)
・「最近話題になっている本は?」
という要求に対応出来ます。
(現在は「タイトル五十音順」がデフォルトの物が多いでしょうか。)
●4.「入力が「単語」にも「文章」にも対応
・「Webcat Plus」・「想IMAGINE」
●5.「連想検索」
・関連資料や関連語でイメージが広がり、資料収集の手助けとなる事。
●6.「横断検索」
・「自館完結」でなく、選択すれば他情報機関・検索エンジン・Amazon等も
含めて資料への最終アプローチ方法」の提示が可能なシステム。
(ILLの物流増加・処理能力向上の必要があり)
●7.「外部へのリンク」(「横断検索」にプラスして)
・横断検索で外部機関に所蔵がある事が判っても、現状では
改めて外部機関のOPACにアクセスし直さなくては、該当資料が
利用可能か判らない。
●8.「図書館貸出記録の活用 」
・「以前借りた本をまた読みたい」という希望への対応。
「個人情報」・「図書館の自由」の問題はありますが、
記録を残したい資料かを選択できる様にした上でならば。
●9.「RSS・メール機能の活用」
・実現されている所も既に有りますが、
*「興味のあるジャンル」を登録し、新着本を通知
*「貸出・予約記録」から「関連本」を解析し、提示
*「督促」通知~電話通知より効率化を
●10.「利用者参加型OPAC」(SOPAC)
・「フォークソノミー」の活用。
*「ユーザーレビュー」~「公開」か「非公開」か選択制に
*「ユーザによるタグ付与」~Ann Arbor District Library→利用者による「タグ付け」、「公開のコメント」、「『Googleで中身を見る」へのリンク」が行われています。
●11.「地域資料」~10.の「利用者(住民)参加」を含めて
・「地域資料収集」は地域発展のための公共図書館の大切な仕事です。
*「小平市立図書館」
の様に、図書館側が地域・行政資料を収集するほか、
*「urumaxの しまPasha CLUB」(特派員が携帯カメラで撮影した画像を携帯メールで送るとサイトにアップされる→「○年○月○日の街の姿」の画像が蓄積出来る)の様に、住民参加による地域情報の形成・活用→「Web2.0の双方向性」を活かした有効なサービスに繋げていく事が出来るのでは。(「街の地理や歴史」に興味のある方は多いので、上記の様な「仕組み」を作れば、情報は集まって来ると思います。活用方法は課題)
●12.「書誌情報の様々な形式での「出力」と「積極的な公開」」
*「出力」~「検索結果のメール送信、CSV出力、印刷」
~レポート作成などの利用に。
*「書誌情報の積極的な公開」~8.で述べた通り、「地域資料収集と書誌作成・管理によるデータベース化」(自治体議会議事録・計画書など)は 「その地域の図書館」でしか出来ない事です。(業務自体は他でも行えますが、「コスト」(直接利益に繋がる仕事とは考えにくいので(いつかは「Google」等が実現するかも知れませんが…))・「灰色文献の継続入手」面の問題から)
他自治体・機関・企業でも、「地域資料データ」は「類似事例」として活用出来るケースがあります。
●13.「わかりやすい画面・操作」(1.と重複する部分あり)
*「簡易検索」(入力ボックス1つ)~「詳細検索」と使い分け。
~検索に慣れない方・「タイトル、著者、出版「者」」などの、
「面倒な入力は好みでない方」に。
(「面倒」を除いていくのが「仕事」。「慣れて下さい」という姿勢を
考え直す)
*「ソフトウェアキーボード」
~「キーボード操作がスムーズでない方」に。(年配の方が主)
(参考:「学校法人 尚絅学園 ソフトウェアキーボード」)
*「子ども用OPAC」
~字が読めれば、子どもはキーボード入力をすぐ憶えてしまう事が多く、
「タッチパネル」≒「ソフトウェアキーボード」を
それほど必要としないのでは、と思います。
→・「検索ボックスが一つ」の簡易検索のスタイルで、
・表示を「大人用をそのまま平がなにした物」だけでなく、
「子どもの語彙で言い換える」、「絵入り」、
『本の海 大冒険』
の様に、ゲーム性を取り入れる工夫をする(「さがす」の他に「あそぶ」
でゲーム機能あり)など、「楽しさ」を重視した構成を考えては、と思います。
■課題1~3を通して「理想のOPAC」について考えまてみましたが、
①「入り口は広く(誰にでも使いやすい)」
②「奥行きは深く(最終的にリンク等で目的の資料に到達出来る)」
の「両方を兼ね備えた物」ではないでしょうか?
(現実的にはコストや運営面からその中間の何処かに落ち着く筈ですが)
*実現への課題は多いですが、
・利用者に「図書館のステークホルダーになりたい」
(千代田区立図書館の「サポーターズクラブ」等)
と思って頂けるために、また
・「コストに見合ったサービス」実現への工夫
(外部サービスで利用可能なものはそちらにリンク)を通して、
各館の事情に合わせたカスタマイズを模索して行こうと思います。
~これで提出にしようと思いますが、次回の講義までに思いついた事が
ありましたら、また追記致します。
1.事例紹介(1)(2)(3)から最低限1つを利用し、その使用感をまとめる。
2.新しいOPACの模索に関する文献リストをまとめる。
3.その上で、理想のOPACについて自分の考えをまとめる。
【3.理想のOPACについて自分の考えをまとめる】
●勤務館が公共図書館ですので、「街の公共図書館で求められるサービス」を視点に入れて考えました。
*「街の公共図書館」は大学・専門図書館と違い、
『利用者により「IT・PCへのスタンス/スキル」が大きく異なる』という特徴があります。
~ご年配の方には、「PC・OPACは使えない」・「(これからも)使いたくない」という方がいらっしゃしますが、これは現在のOPACが「楽しくなさそう」・「わざわざ憶えても、それほど便利ではないのでは?」という印象を与えてしまっているためではないかと思います。その解決の為にも、
→「パッと見てわかりやすい」・「簡単・使いやすい」→「とりあえず使ってみようか」と思って頂けるためには?を考えました。
(現場レベルの視点も取り上げた為、「次世代サービス」導入に躊躇している様に見える記述もありますが、「導入のためには、一つ一つ何をして行ったら
良いか?」を具体的に整理するための物です)
●1.「分かりやすい画面」
・「ビジュアル(デザイン)」的に把握しやすい
~色分け・アイコンの工夫など
・「初めてアクセスする方にも使いやすい」構成を
~講義でも「利用者教育をしなければ使えないならば『親切なOPAC』
とは言えない」と言われましたが、システムを作る側の方
(PC・Webに慣れている方)の
「これくらいは常識」という感覚は、公共図書館の利用者の感覚とは
だいぶ異なっている様に感じられます。
*「まずログインするのが常識」として作られているのですが、
館内・館外OPACとも、「最初にログインして下さい」という分かりやすい
表示があれば、検索結果に予約をしようとする段階で、
「あれ?出来ない・そもそもログインって何?」と
戸惑う事も少なくなるのではと思います。
(口頭や冊子でも『使い方』ご案内はしていますが、実際に画面を見て
初めて、「わからない事がある」のに「気づかれる」状態です)
*また、上記で「あれ?」と思われる方にはキーボード入力自体が
スムーズでない方も多く、「入力し直し」だけでストレスとなり、
そのまま「クレーム」になる事もあります。
*「操作性」の向上の必要性
~一例として、「前の画面に戻る」操作の場合、
1.「OPAC画面の「戻る」ボタン」では前の画面(検索結果一覧)に
戻れるのに、
2.「ブラウザの「戻る」ボタンでは「検索入力」の初期画面に
戻ってしまい、検索作業が1からやり直しになってしまう
OPACもあります。
プログラムのミスなのか、ソフトの「ローカル・ルール」の
問題かは不明ですが、
この様な「小さな事」を一つ一つ解消していく事が
「使いやすいOPAC」実現に必要だと思います。
(「次世代OPAC」とは次元が異なる問題ですが…)
*「図書館用語」でなく、分かりやすい言葉での表記を。
・「書架」でなく「本棚」など、「普通に使う言葉」で。
●2.「表記のゆれ・あいまい検索」への対応
・「1文字でも違えば検索がヒットしない」(かな・漢字表記まで合致して
いなくてないけない)が現状ですが、
検索エンジンの様に「~ではありませんか?」と候補を出してくれれば、
と思います。
カウンターへの質問でも正確に書名や著者を憶えていないケースが
殆んどです。
●3.「検索結果」にランキング表示を取り入れる
*検索エンジンのように、ランキング表示を取り入れる。
現在の「五十音順」・「出版年順」ソートに、
「ランキング表示」を付け加えることにより、
・「このジャンルで人気のある本」(≒内容が信用出来る本)
・「最近話題になっている本は?」
という要求に対応出来ます。
(現在は「タイトル五十音順」がデフォルトの物が多いでしょうか。)
●4.「入力が「単語」にも「文章」にも対応
・「Webcat Plus」・「想IMAGINE」
●5.「連想検索」
・関連資料や関連語でイメージが広がり、資料収集の手助けとなる事。
●6.「横断検索」
・「自館完結」でなく、選択すれば他情報機関・検索エンジン・Amazon等も
含めて資料への最終アプローチ方法」の提示が可能なシステム。
(ILLの物流増加・処理能力向上の必要があり)
●7.「外部へのリンク」(「横断検索」にプラスして)
・横断検索で外部機関に所蔵がある事が判っても、現状では
改めて外部機関のOPACにアクセスし直さなくては、該当資料が
利用可能か判らない。
●8.「図書館貸出記録の活用 」
・「以前借りた本をまた読みたい」という希望への対応。
「個人情報」・「図書館の自由」の問題はありますが、
記録を残したい資料かを選択できる様にした上でならば。
●9.「RSS・メール機能の活用」
・実現されている所も既に有りますが、
*「興味のあるジャンル」を登録し、新着本を通知
*「貸出・予約記録」から「関連本」を解析し、提示
*「督促」通知~電話通知より効率化を
●10.「利用者参加型OPAC」(SOPAC)
・「フォークソノミー」の活用。
*「ユーザーレビュー」~「公開」か「非公開」か選択制に
*「ユーザによるタグ付与」~Ann Arbor District Library→利用者による「タグ付け」、「公開のコメント」、「『Googleで中身を見る」へのリンク」が行われています。
●11.「地域資料」~10.の「利用者(住民)参加」を含めて
・「地域資料収集」は地域発展のための公共図書館の大切な仕事です。
*「小平市立図書館」
の様に、図書館側が地域・行政資料を収集するほか、
*「urumaxの しまPasha CLUB」(特派員が携帯カメラで撮影した画像を携帯メールで送るとサイトにアップされる→「○年○月○日の街の姿」の画像が蓄積出来る)の様に、住民参加による地域情報の形成・活用→「Web2.0の双方向性」を活かした有効なサービスに繋げていく事が出来るのでは。(「街の地理や歴史」に興味のある方は多いので、上記の様な「仕組み」を作れば、情報は集まって来ると思います。活用方法は課題)
●12.「書誌情報の様々な形式での「出力」と「積極的な公開」」
*「出力」~「検索結果のメール送信、CSV出力、印刷」
~レポート作成などの利用に。
*「書誌情報の積極的な公開」~8.で述べた通り、「地域資料収集と書誌作成・管理によるデータベース化」(自治体議会議事録・計画書など)は 「その地域の図書館」でしか出来ない事です。(業務自体は他でも行えますが、「コスト」(直接利益に繋がる仕事とは考えにくいので(いつかは「Google」等が実現するかも知れませんが…))・「灰色文献の継続入手」面の問題から)
他自治体・機関・企業でも、「地域資料データ」は「類似事例」として活用出来るケースがあります。
●13.「わかりやすい画面・操作」(1.と重複する部分あり)
*「簡易検索」(入力ボックス1つ)~「詳細検索」と使い分け。
~検索に慣れない方・「タイトル、著者、出版「者」」などの、
「面倒な入力は好みでない方」に。
(「面倒」を除いていくのが「仕事」。「慣れて下さい」という姿勢を
考え直す)
*「ソフトウェアキーボード」
~「キーボード操作がスムーズでない方」に。(年配の方が主)
(参考:「学校法人 尚絅学園 ソフトウェアキーボード」)
*「子ども用OPAC」
~字が読めれば、子どもはキーボード入力をすぐ憶えてしまう事が多く、
「タッチパネル」≒「ソフトウェアキーボード」を
それほど必要としないのでは、と思います。
→・「検索ボックスが一つ」の簡易検索のスタイルで、
・表示を「大人用をそのまま平がなにした物」だけでなく、
「子どもの語彙で言い換える」、「絵入り」、
『本の海 大冒険』
の様に、ゲーム性を取り入れる工夫をする(「さがす」の他に「あそぶ」
でゲーム機能あり)など、「楽しさ」を重視した構成を考えては、と思います。
■課題1~3を通して「理想のOPAC」について考えまてみましたが、
①「入り口は広く(誰にでも使いやすい)」
②「奥行きは深く(最終的にリンク等で目的の資料に到達出来る)」
の「両方を兼ね備えた物」ではないでしょうか?
(現実的にはコストや運営面からその中間の何処かに落ち着く筈ですが)
*実現への課題は多いですが、
・利用者に「図書館のステークホルダーになりたい」
(千代田区立図書館の「サポーターズクラブ」等)
と思って頂けるために、また
・「コストに見合ったサービス」実現への工夫
(外部サービスで利用可能なものはそちらにリンク)を通して、
各館の事情に合わせたカスタマイズを模索して行こうと思います。
~これで提出にしようと思いますが、次回の講義までに思いついた事が
ありましたら、また追記致します。