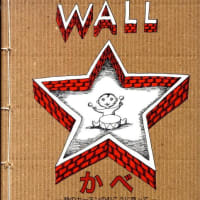大阪城公園駅
おごそかなことに、地もまたうごく。
私どもは、思うことができる。この駅に立てば、台地のかなたに渚 [なぎさ]があったことを。遠い光のなかで波がうちよせ、漁人 [いさりびと]が網を打ち、浜の女 [め]らが藻塩 [もしお]を焼いていたことども。秋の夜、森の上の星だけが、遙かな光年のなかで思い出している。
夏、駅舎の前の森の露草の花の青さにおどろくとき、またたきの間 [ま]でも茅渟 [ちぬ]の海を思いかさねてもらえまいか。ひたにこのあたりまで満ちていたことを。
目の前の台地は島根のごとくせりあがり、まわりを淡水 [まみず]が音をたてて流れ、大和や近江の玉砂を運び、やがては海を浅め、水が葦 [あし]を飼い、葦が土砂を溜めつつ、やがては洲 [しま]になりはててゆく姿は、たれの目にもうかべることができる。
八十 [やそ]の洲 [しま]
それがいまの大阪の市街であることを。冬の日、この駅から職場へいそぐ赤いポシェットの乙女らの心にふとかすめるに違いない。創世の若さ、なんと年老いざる土 [くに]であることか。
私どもは、津の国にいる。
津、水門 [みなと]、湊、港。私どもは、古き津の風防ぎする台上にいる。
台地は海鼠形 [なまこがた]をなし、方正にも北から南によこたわり、南端の岩盤に四天王寺が建った日のことを、炎 [ほのお]だつ陽炎のなかで思っている。輪奐 [りんかん]が海に輝いたとき、遠 [とお]つ國々の舶 [ふね]が帆をななめにして松屋町筋の白沙に近づき、この駅舎のあたりの入江のいずれかへ石の碇 [いかり]を沈め、内典 [ないてん]・外典 [げてん]の書籍を積みおろしたにちがいない。思想の書、詩の書、工芸の書。…もし若者が、駅舎のベンチの何番目かに腰をおろし、ひざに書物を置いて空を見あげたとき、櫂 [かい]で描 [えが]いたような飛行機雲があらわれるとすれば、その舶が曳きつづけてきた航跡であるとおもっていいのではないか。
海鼠形の台地の北の端は、いま私どもが眺めている。ここに西方 [さいほう]浄土にあこがれた不思議の経典を誦 [ず]する堂宇ができたとき、地は生玉荘 [いくたまのしょう]とよばれ、坂があった。おさかとよばれた。堂宇の地は礫 [こいし]多く、石山とよばれていたが、ここに町屋 [まちや]がならんだとき、この台上にはじめてささやかな賑わいができた。
楼上から西をのぞみ、陽傾き、帰帆相次ぐころ、波のかなたの一の谷の崖に沈んでゆく陽日の華やぎは、ひと堂宇が去り、城ができたとき、日本の歴史は変った。
威と美を多層であらわした世界最大の木造構造物は、大航海時代の申し子というべく、その威容を海から見られるべく意識した。事実、この海域に入った南蛮船は、極東のはてに世界意識をもった文明があることを象徴として知った。
城の台上から西へ降りた低地はすでに八十洲 [やそしま]ではなくなり、網模様のように堀川がうがたれ、大小の商家がひしめき、日本國のあらゆる商品がいったんそこに運ばれ、市 [いち]が立ち、値がさだまり、やがて諸国に散じた。
この前例のない仕組みそのものが天下統一の独創から出ており、にぎわいは空前のものとなった。
台上の城には、あざやかな意志があった。台下の商権と表裏をなしつつそれを保護し、さらには海外を意識し、やがて思想なき過剰な自信が自己肥大をまねき、精神の重心が舞いあがるとともに暴発し、他國に災をあたえ、みずからも同じ火のなかでほろんだ。人の世にあることのかがやきと、世に在りつづけることの難 [かた]さをこれほど詩的に象徴した建造物が他にあるだろうか。
つぎの政権は、篤農家のように油断なく、諸事控えめで、無理をつつしみ、この地の商権もまた前時代と同様、手あつく保護した。信じられるだろうか、二百七十年ものあいだ、この一都市が六十余州の津々浦々に商品と文化をくばりつづけたことを。
さらには、評価の街でもあった。物の見方、物の質、物の値段……多様な具象物 [ぐしょうぶつ]が数字とし抽象化されてゆくとき、ひとびとの心に非條理の情念が消え、人文科学としか言いようのない思想が萌芽した。さらには自然科学もこの地で芽生える一方、人の世のわりなきこと、恋のつらさ、人の情の頼もしさ、はかなさが、ことばの芸術をうみ、歌舞音曲を育て、ひとびとの心を満たした。
右の二世紀半、ひとびとは巨大なシャボン玉のなかにいた。
あるいは六十余州だけがべつの内圧のなかにいた。
数隻の蒸気船の到来によって破れ、ただの地球の気圧と均等 [ひとしなみ]になったとき、暴風がおこった。
この城は、ふたたび情勢の中心となり、政府軍が篭り、淀川十三里のかなたの京の新勢力と対峙 [たいじ]した。ついには、やぶれた。二度目の落城であり、二度ともやぶれることによって歴史が旋回した。この神秘さを感ずるとき、城はただの構造物から人格になっていると感じてもよいのではないか。
その地に居ることは、その運命とかかわる。この城が六十余州の中央に在ることで、好まざる運命をも背負わされた。薩南の暴発にそなえるために、城のまわりに火砲の鋳造所が置かれた。
やがて、首都を頭脳とする日本國が、十九世紀の欧州の膨張主義を妄想しはじめるとともに、この場所の設備も拡大され、やがて共同妄想が業火とともに燃えおちた日、城のまわりの鉄という鉄が熔け、人という人が鬼籍に入った。城は三度目の業火を見た。
悲しみは、この街に似合わない。
ただ、思うべきである。とくに春、この駅に立ち、風に乗る万緑の芽の香に包まれるとき、ひそかに、石垣をとりまく樹々の発しつづける多重な信号を感應すべきであろう。その感應があるかぎり、この駅に立つひとびとはすでに祝われてある。日日のいのち満ち、誤りあることが、決してない。
司馬遼太郎