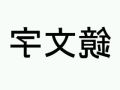下巻は第一次世界大戦以降から第二次世界大戦終戦、朝鮮戦争までをカバーしている。 . . . 本文を読む
学校を卒業してから人生で学ぶことはたくさんあると思う。
もし自分が学校の先生だったら道徳の時間にこういうことを中学生や高校生に伝えたい、考えてもらいたいと思い、先日行きつけのお店で(酔った勢いで)持論を展開してしまった。
僕は中学生、高校生のころに、このようなテーマで議論できる授業があったらよかったのにと思うのだ。
1)人から持ちかけられる話に「うまい話」はほとんどない。
「うまい話」 . . . 本文を読む
光が真っ直ぐに進むことや反射や屈折をしたときの光の経路は「フェルマーの原理(最小時間の原理)」で説明される。つまり鏡に反射する光線の入射角と反射角が等しくなるのは所要時間を最小にする、つまり最短経路を光が進むからだということになるわけだ。
小中学校ではこのように「入射角と反射角は等しい。」ことだけを教わり、高校や大学では「それは所要時間を最小にするためだ。」と教わるのだったと思う。
けれども . . . 本文を読む
そもそもどうして入射角と反射角は等しいのだろうか?
ファインマン物理学の第2巻の冒頭。光学の理論にはいるところでふと考えてしまった。高校物理どころか小学校の理科でも教わる「常識」であるはずなのに、自分はその理由を答えられないことに気がついたのだ。このままでは気になって眠れない。深夜にもかかわらずこのような記事を書いているのはそんなわけである。
光線の場合には入射角と反射角が等しいことは感覚的 . . . 本文を読む
掲載画像:複素平面(ガウス平面)に描かれたマンデルブロート集合の図形
「複素世界は実世界とつながっている」という記事で中学、高校で習う数学公式の多くが複素数の世界でも成り立っているのが不思議だと説明した。そして「それを成り立たせる「理由」がどこかにあるはずだ。」とまで書いたのだが、今日の記事ではその理由を示そう。
それは「実数で成り立つ演算規則は複素数でもそのまま成り立つから。」という一言に尽 . . . 本文を読む
掲載画像:複素平面(ガウス平面)に描かれたマンデルブロート集合の図形
今月号の「ニュートン」で虚数についての特集記事が掲載されていることを紹介したので、この記事では虚数や複素数の世界が実世界とつながっていることについて書こうと思う。それはもちろん複素数を図示するための「複素平面(ガウス平面)」が実数の数直線を含んでいるからということではない。
この記事に掲載している数学の公式は中学と高校で学習 . . . 本文を読む
私たちの住む世界が3次元空間だという話で、よく持ち出されるのが1次元や2次元の世界の話がある。1次元世界は直線や曲線など「線」の世界で2次元世界は平面や曲面の「面」の世界。そこに生物がいるとすれば、お互いはそれぞれ「点」や「線分」とでしか相手を見ることができない、というような話は聞いたことがあるだろう。
でもよく考えて見れば相手を見るためには「光」が必要で、「光」は「電磁波」の一種だ。電磁波は掲 . . . 本文を読む
光や音がその光源や音源から離れるにつれて弱まっていくことは経験によってもよく知られたことだ。その弱まり方は掲載画像のように距離の2乗に反比例している。つまり距離が2倍になれば強さは4分の1に、距離が3倍になれば強さは9分の1になる。
光や音のエネルギーが空間のあらゆる方向に放射されるから、中心からの距離rを半径とする球面を考えれば、球面の面積はrの2乗に比例するからだ。球面全体は中心から放射され . . . 本文を読む
一昨日の記事「どうして鏡は左右を逆に映すのに上下はそのままなの?」の答をみなさんは見つけることができただろうか?
以下がその答だ。
大事なことは「実は鏡は左右を逆に映していない。」という点だ。そして「上下も逆に映していない。」のだ。鏡がしていることは「鏡を正面から見たときに手前と奥を逆転させている。」だけなのだ。この絵を見ればよくわかるだろう。
鏡は左右も上下もそのまま映し、手前と奥が . . . 本文を読む
「どうして鏡は左右を逆に映すのに上下はそのままなの?」
このことをわかりやすく説明できる人はかなり少ないようだ。鏡は上下左右対称にできているのに左右だけ逆転させてしまうのは不思議な気がしませんか?
中学のとき線対称や面対称、点対称を習ったとき先生に質問したことがあるが、納得のいく説明はもらえなかった。
「人間の目が左右についているから。」と答える人がいるが、これは明らかに間違いだ。片目で見て . . . 本文を読む
昨日の「4次元生物に目はいくつ必要か?」という記事の次は「耳の個数」の話。
耳の場合は目のときにくらべてはるかに簡単だ。けれども考えていくうちに意外な事実に気がついたので、記事にせずにはいられなかった。
人間は左右に耳があるおかげで音楽をステレオで楽しむことができる。救急車のサイレンの音も、両耳があるおかげでどちらの方向から近づいてきているのかもわかるのだ。音の空間を立体的に聞いているからで、 . . . 本文を読む