 私は昆虫の生活史を記載する際、その種が独居性か集合性か必ず言及するべきだと九重昆虫記に何度も書きました。独居性の種に属する幼虫は同種の他の幼虫と必ず一定の距離をおいて暮らしています。つまりもともと同種の幼虫ですから、同種の他者を常に意識し、距離を保たねばならない明確な理由があるのです。私もその理由をすべて挙げることはできませんが、一つ例を挙げればヤママユガなど大型の蛾の幼虫はなるべく同種の他個体と距離をおきます。なぜなら大型で目立つから誰かが見つかると、天敵は執拗にその周りを探すでしょう。また一般に何かに擬態している幼虫も同種の他個体と距離をおきます(九重昆虫記第6巻シャクガ科の各章参照)。擬態するものは天敵から隠れず、姿を人前にさらしても平然としていますが、万一運悪く天敵に襲われた場合、すぐそばに同じ虫がいれば当然その虫にも危険が及びます。
私は昆虫の生活史を記載する際、その種が独居性か集合性か必ず言及するべきだと九重昆虫記に何度も書きました。独居性の種に属する幼虫は同種の他の幼虫と必ず一定の距離をおいて暮らしています。つまりもともと同種の幼虫ですから、同種の他者を常に意識し、距離を保たねばならない明確な理由があるのです。私もその理由をすべて挙げることはできませんが、一つ例を挙げればヤママユガなど大型の蛾の幼虫はなるべく同種の他個体と距離をおきます。なぜなら大型で目立つから誰かが見つかると、天敵は執拗にその周りを探すでしょう。また一般に何かに擬態している幼虫も同種の他個体と距離をおきます(九重昆虫記第6巻シャクガ科の各章参照)。擬態するものは天敵から隠れず、姿を人前にさらしても平然としていますが、万一運悪く天敵に襲われた場合、すぐそばに同じ虫がいれば当然その虫にも危険が及びます。反対に集合性の種は同種の個体が集まって社会を作っています。このシリーズでは集合性の例をまず挙げます。最初の写真はキバラヘリカメムシの集団です。本種は秋から晩秋にかけて九重自然史研究所の庭のニシキギ(ニシキギ科)の葉上で集団をつくります。この虫はその時期に熟すニシキギの実を吸いに来ます。葉は無数にあるので1個体が1枚ずつ占拠しても余るはずなのに、必ず数頭から10頭ほどの群れを作ります。写真をよく見ると、齢の違う個体が混じっています。成虫も混じっていますがこれは親ではなく、新たに羽化した新成虫です。この成虫は間もなく越冬態勢に入り、来春になってから交尾し産卵します。多分、夏に新世代が羽化し、それが秋の幼虫の親になるのだろうと思いますが、私は秋になるまで本種の成虫も幼虫も見たことがありません。
ニシキギの葉上の幼虫は終齢から3齢の幼虫が混じっているので、この集団は血縁集団ではなく、この木に産卵した複数の雌に由来する集団です。私は日向ぼっこ集団と呼んでいますが、幼虫は黄色の警告色を持っており、集団を作れば目立ちます。九重自然史研究所の庭には多くの鳥が来ますが、悪臭を放つこの集団を捕食するものはいません。










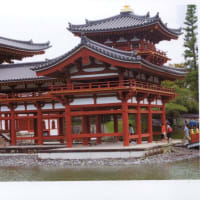
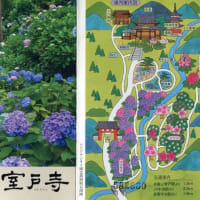








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます