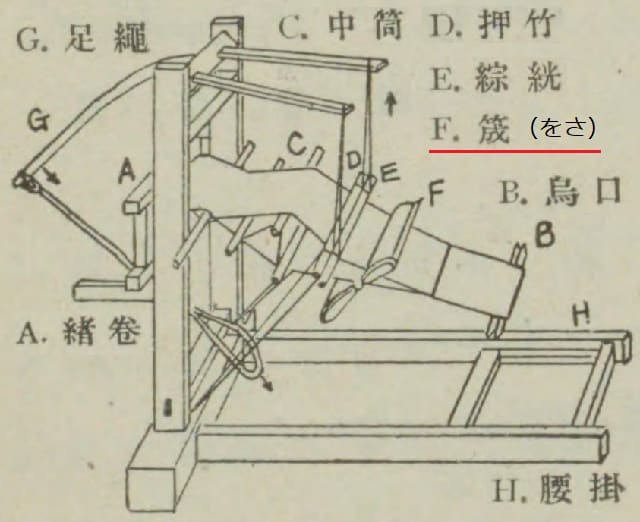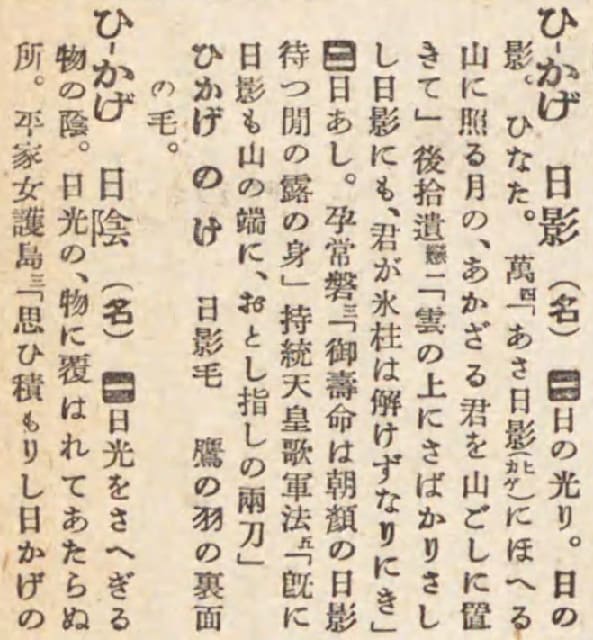『ついに現われた幻の奉納文 伊勢神宮の古代文字』(丹代貞太郎・小島末喜:著、小島末喜:1977年刊)という本の内容をご紹介しています。
今回は中臣連鎌子の3枚の奉納文です。
【中臣連鎌子の奉納文】
・1枚目
|
番号
|
読み
|
解釈
|
古代文字の種類
|
|---|---|---|---|
|
2
|
あめのみはしらのかみ | 天御柱神 | 阿比留文字 |
| なかおみむらしかまこ | 中臣連鎌子 | 阿比留文字 |
・2枚目
|
番号
|
読み
|
解釈
|
古代文字の種類
|
|---|---|---|---|
|
3
|
くにのみはしらのかみ | 国御柱神 | 阿比留文字 |
| なかおみむらしかまこ | 中臣連鎌子 | 阿比留文字 |
・3枚目
|
番号
|
読み
|
解釈
|
古代文字の種類
|
|---|---|---|---|
|
4
|
あめのこやねのみこと | 天児屋根命 | 阿比留文字 |
| なかおみむらしかまこ | 中臣連鎌子 | 阿比留文字 |
1枚目の「あめのみはしらのかみ」、および2枚目の「くにのみはしらのかみ」は、『日本古語大辞典』によると、官幣大社龍田神社の祭神で、欽明天皇の夢枕に立って自ら天乃御柱乃命、国乃御柱乃命と名乗ったとされ、比古神、比売神とも記されているそうなので夫婦の神様のようです。
3枚目の「あめのこやねのみこと」は、古事記によると、天孫降臨の際に邇邇芸命(ににぎのみこと)の従者として天降った神で、「中臣連等之祖」と明記されています。
各奉納文の2行目は奉納者の署名で、「なかおみむらしかまこ」に相当する人物は、前回、物部大連尾輿とともに仏教の受け入れに反対したとご紹介した中臣連鎌子と考えられます。
なお、この本には、龍田神社の創建は崇神天皇時代とされていると書かれていますが、これは誤りで、延喜式の龍田風神祭祝詞に書かれた天皇の名前は、
「志貴島爾大八島國知志皇御孫命」
(しきしまに おほやしまくに しろしめす すめみまのみこと)
と明記されていて、崇神天皇の宮は磯城(しき)の瑞籬宮(みづがきのみや)、欽明天皇の宮は磯城嶋(しきしま)の金刺宮(かなさしのみや)ですから、龍田神社は欽明天皇の時代に創建されたと考えられるのです。
また、「なかおみむらしかまこ」を藤原鎌足に比定していますが、日本紀では、鎌足は最初「中臣鎌子連」と表記され、その後「中臣鎌足連」となり、最後は「藤原内大臣」と表記されているので、「中臣連鎌子」とは別人だと判断できます。
しかも、藤原鎌足は7世紀の人物であり、これでは、彼がこの奉納文を古代文字で書いた理由が不明になってしまいます。
前回ご紹介したように、欽明天皇の時代に仏教が公式に伝わり、中臣連鎌子は物部大連尾輿とともに仏教の受け入れに反対したわけですから、彼がこの時代に新たに出現した神様に対してどういう態度をとったか考えれば、すべてがつながってくるでしょう。
つまり、中臣連鎌子は、欽明天皇の夢枕に立った神様をおそれ敬い、自身の祖神とともにその名前を古代文字で書いて神宮に奉納することで、日本の神々に対する信仰心を表明したのではないかと思われるのです。
最後に、中臣は「なかおみ」と読むことと、やはり氏名に「の」を挿入することはなかったということがこの奉納文から分かりますから、中臣連鎌子は「なかおみむらじかまこ」と読むのが正しいということになります。
これらの奉納文は、6世紀の人名の読み方を明らかにし、かつ、延喜式の龍田風神祭祝詞の正当性を証明していると考えられますから、前回同様、非常に歴史的価値の高いものであると判断できるのです。