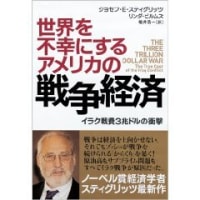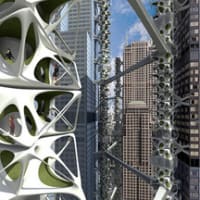本のリンクはこちら
黒猫 by エドガー・アラン・ポー 中編
前編はこちら
このできごと、災害と虐待とに因果律をみるほど僕は心が弱くはない。ただ僕は一連の事実を詳しく述べているだけであって、すこし欠けることも嫌なのだ。火事の次の日、僕は廃墟を見に行った。壁は一箇所をのぞいてくずれおちていた。一箇所とはそれほど厚くない一区画の壁で、家のまんなかほど、ちょうど僕が寝ていたベッドの頭のあたりの場所だった。ここの漆喰だけが、大部分、火に耐えていたが、それは最近塗り替えたからだろうと思っていた。その壁のまわりには黒山の人だかりができており、多くの人が壁の一部分を詳細かつ熱心に注意をはらって、調べているようだった。「おかしいな」「奇妙だな」といったような言葉が、僕の興味をそそり、近づくと、まるで白い壁の表面にレリーフを彫ったかのように、大きな猫のすがたがみてとれた。その痕跡は、まったくもって正確としかいいようのないものだった。猫の首には紐がかかっていた。
最初は幻影にしか見えなかったが、まさしくそのもの以外に見えようがなく、僕の惑う気持ちと恐怖は最高潮に達した。でも、とうとうよく考えて思い当たった。思い出すと、僕は猫を家のすぐそばの庭につるした。火事の知らせで、すぐに庭は多くの人でいっぱいになり、そのうちの誰かが木から猫を切り離して、開いてる窓から僕の寝室にほうりこんだにちがいない。きっと、僕を起こすためにやったんだろう。そのとき他の壁が崩れて、僕の残虐行為の犠牲者の猫は塗りたての漆喰におしつけられ、漆喰の石灰と炎と死体からのアンモニアで、僕がみたような像ができあがったのだと。
いま述べた驚くべき事実で、理性はすぐに納得させられたが、良心はそういうわけにはいかず、僕の心に強い印象を与えた。何ヶ月も僕は、猫の幻想から逃れられなかった。そうしているあいだ、僕の心には後悔といえるようないえないような、相半ばした気持ちがもどってきた。猫を失ったことを悔やむようにさえなり、僕がよく足を運んでいた恥ずべき場所で、同じ種類の同じような見かけの猫が、僕の心を満たしてくれないかと捜し求めるようにさえなった。
ある晩、僕は悪名だかい場所に座って、なかばぼーっとしていたら、急になにか黒いものに注意をひかれた。それはその場所にほとんど唯一あるものといってもいい、ジンかラムの大だるの一つの上に横たわっていた。しばらくのあいだ、じっと大だるの上を見つめていたが、どうしてもっと早くこれに気づかなかったのか驚くばかりだった。
僕は近寄って、手でさわってみた。黒い猫で、とても大きく、プルートと同じくらいはあった。一箇所を除いては、プルートにそっくりだった。プルートには体のどこにも白い毛は少しもなかったが、この猫はほとんど胸全体といっていいほどが、ぼんやりとした白い斑点でおおわれていた。僕が触ると、すぐに気づいて、のどを大きな声でゴロゴロとならし、僕の手に毛をこすりつけ、僕がふれたのを喜んでいるようだった。これこそ僕がまさにさがしていたものだった。すぐに店主に買い取りたいと申し入れたが、そんな猫のことは知らないし、見たこともないので、買い取らなくてもいいと答えるばかりだった。
僕は猫をなでていたが、家に帰ろうとすると、猫も一緒に帰りたそうな風をみせた。僕もそうすることを許し、帰り道でときどき立ち止まっては、頭をなでてやった。家に帰るとすぐに居つき、僕の妻もその猫がすぐさますっかりお気に入りになった。
僕はといえば、すぐにその猫に対する嫌悪の念がむくむくとわいてきた。これは僕が思っていたこととは、まったく逆の結果だった。また、なぜ、どうしてそうなのか分からなかったが、猫が僕のことを明らかにとても好きだということも僕をむかむかさせ、悩ませた。だんだん、このむかむかや悩みが、強い憎しみへと変わっていき、僕は猫を避けるようになった。ただはっきりとした恥ずかしいという気持ちと前の残虐な行為の記憶が、猫を虐待することを妨げていた。僕は数週間は猫をたたいたり、いじめたりはしなかった。でもだんだん、まさしくだんだんとだが、僕は言葉にはし難い憎しみの気持ちをいだいて猫をみるようになり、まるでペストがやってきたかというようにその憎むべき姿から、さっと身をかわすようになった。
まちがいなく、その猫への憎しみをましたのは、つれて帰った日の朝、プルートとおなじように片目がないことをみつけてからだった。でもこうしたことは妻にとってはその猫をかわいがる理由にしかならなかった。妻は、前にも言ったとおり、僕の前の特質であった、もっとも素直で純粋な喜びの源であったあの暖かい感情を存分に持ち合わせていたからだ。
ただ僕がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫は僕のことが好きになるみたいだった。みんなには分かってもらえないほど、僕の後をずっとつけまわし、僕が座っていると椅子の下にやってきて、ひざに飛び乗り、あの恐るべき愛撫を僕にするのだった。僕がたちあがって歩き出すと、足のあいだにからみつき、僕を転ばせんばかりで、あるいはその長く鋭いつめを僕の着ているものにたてて、僕の胸のところまで上ってこようとさえした。そんなときはいっそのこと殴り殺してしまいたくなったが、そうできなかったのは前のことを覚えていたからでもあるが、本当のところは言わせてもらえば、この猫が怖かったのだ。
この恐怖は正確に言えば、肉体的な恐怖ではない。ただ、僕にはなんと言っていいのかわからない。犯罪者としての監房にいても、口にだすのは非常に恥ずかしいことだが、この猫が僕にいだかせる恐怖と戦慄は、僕がもっている単なるひとつの妄想にすぎないものでますます高まっていった。妻はよく僕に一度ならず言ったものだが、前にふれた猫の白い部分の模様は、僕が殺した猫とこの猫の唯一の目に見えるちがいだった。読者の方もこのしるしが、大きいけれど、もともとはっきりしない形だったことを覚えておられるだろう。でもゆっくりと、ほとんど気づかないくらいゆっくり、僕の理性は長い間たんなる気の迷いだとしりぞけようとしていたが、それは、とうとうはっきりとした輪郭をとるようになった。僕がゾッとして名前を言えないようなあるものの形を。結局このしるしのために、僕はこの猫を嫌い、恐れ、いっそのこと消してしまいたいと思ったものだ。いまや、おぞましい、不気味なものの形をとるようになった。それこそは絞首台で、恐怖と犯罪、苦悩と死の、陰鬱で悲惨な原動力だった。
そうして僕は、人間が味わう悲惨さのなかで、もっとも悲惨なものを味わった。仲間は見下し殺してやったその畜生が、僕にしたことは、神をかたちどったこの人間の僕にしたことは、まったく耐え難いことだった。あぁ、昼夜をとわず、安息はなかった。この猫が、僕をかたときも一人にしておかないのだ。夜に僕が一時間ごとに言いようがないほど恐ろしい夢から目をさますと、僕の顔のところには温かい息をふきかける、ずっしり重いものがいて、それは夢の悪魔が実在のかたちをとったようで、僕にはふりはらうこともできず、永遠に僕の心に課せられた重荷のようだった。
こうした拷問にさらされていたせいで、僕の中にあったよい心のかすかな名残も消えさった。悪意こそが、それももっとも深く邪悪な悪意が、僕の唯一の友となった。ふつうのときから全てのものや人を憎むようになり、とつぜん、それもしばしば、抑えきれない憤怒の情にかられて、自分がまったく分からなくなり、そして文句をいわない僕の妻が、かわいそうに、いつもその被害をうけ耐えていた。
ある日、僕と妻はいっしょに家の用事を片付けに、貧乏ゆえに住まうことになった古い家の地下室にいった。猫は階段を降りるときも僕についてまわり、もうすこしで僕は階段から転げ落ちるところだった。そこで、怒りにわれを忘れてしまった。斧をふりあげると、今まで躊躇していた子供っぽい恐怖心も怒りゆえにすっかりわすれ、猫にむかってふりおろした。もちろん僕の思い通りになれば、即死だっただろう。でも妻が僕の手をつかんで邪魔をした。邪魔で、怒りは悪魔以上のものとなり、妻の手をふりはらうと、その頭めがけて斧を一刀両断うちおろした。妻はその場所に、うめき声ひとつあげずに倒れ、亡くなった。
(つづく) 後編はこちら
黒猫 by エドガー・アラン・ポー 中編
前編はこちら
このできごと、災害と虐待とに因果律をみるほど僕は心が弱くはない。ただ僕は一連の事実を詳しく述べているだけであって、すこし欠けることも嫌なのだ。火事の次の日、僕は廃墟を見に行った。壁は一箇所をのぞいてくずれおちていた。一箇所とはそれほど厚くない一区画の壁で、家のまんなかほど、ちょうど僕が寝ていたベッドの頭のあたりの場所だった。ここの漆喰だけが、大部分、火に耐えていたが、それは最近塗り替えたからだろうと思っていた。その壁のまわりには黒山の人だかりができており、多くの人が壁の一部分を詳細かつ熱心に注意をはらって、調べているようだった。「おかしいな」「奇妙だな」といったような言葉が、僕の興味をそそり、近づくと、まるで白い壁の表面にレリーフを彫ったかのように、大きな猫のすがたがみてとれた。その痕跡は、まったくもって正確としかいいようのないものだった。猫の首には紐がかかっていた。
最初は幻影にしか見えなかったが、まさしくそのもの以外に見えようがなく、僕の惑う気持ちと恐怖は最高潮に達した。でも、とうとうよく考えて思い当たった。思い出すと、僕は猫を家のすぐそばの庭につるした。火事の知らせで、すぐに庭は多くの人でいっぱいになり、そのうちの誰かが木から猫を切り離して、開いてる窓から僕の寝室にほうりこんだにちがいない。きっと、僕を起こすためにやったんだろう。そのとき他の壁が崩れて、僕の残虐行為の犠牲者の猫は塗りたての漆喰におしつけられ、漆喰の石灰と炎と死体からのアンモニアで、僕がみたような像ができあがったのだと。
いま述べた驚くべき事実で、理性はすぐに納得させられたが、良心はそういうわけにはいかず、僕の心に強い印象を与えた。何ヶ月も僕は、猫の幻想から逃れられなかった。そうしているあいだ、僕の心には後悔といえるようないえないような、相半ばした気持ちがもどってきた。猫を失ったことを悔やむようにさえなり、僕がよく足を運んでいた恥ずべき場所で、同じ種類の同じような見かけの猫が、僕の心を満たしてくれないかと捜し求めるようにさえなった。
ある晩、僕は悪名だかい場所に座って、なかばぼーっとしていたら、急になにか黒いものに注意をひかれた。それはその場所にほとんど唯一あるものといってもいい、ジンかラムの大だるの一つの上に横たわっていた。しばらくのあいだ、じっと大だるの上を見つめていたが、どうしてもっと早くこれに気づかなかったのか驚くばかりだった。
僕は近寄って、手でさわってみた。黒い猫で、とても大きく、プルートと同じくらいはあった。一箇所を除いては、プルートにそっくりだった。プルートには体のどこにも白い毛は少しもなかったが、この猫はほとんど胸全体といっていいほどが、ぼんやりとした白い斑点でおおわれていた。僕が触ると、すぐに気づいて、のどを大きな声でゴロゴロとならし、僕の手に毛をこすりつけ、僕がふれたのを喜んでいるようだった。これこそ僕がまさにさがしていたものだった。すぐに店主に買い取りたいと申し入れたが、そんな猫のことは知らないし、見たこともないので、買い取らなくてもいいと答えるばかりだった。
僕は猫をなでていたが、家に帰ろうとすると、猫も一緒に帰りたそうな風をみせた。僕もそうすることを許し、帰り道でときどき立ち止まっては、頭をなでてやった。家に帰るとすぐに居つき、僕の妻もその猫がすぐさますっかりお気に入りになった。
僕はといえば、すぐにその猫に対する嫌悪の念がむくむくとわいてきた。これは僕が思っていたこととは、まったく逆の結果だった。また、なぜ、どうしてそうなのか分からなかったが、猫が僕のことを明らかにとても好きだということも僕をむかむかさせ、悩ませた。だんだん、このむかむかや悩みが、強い憎しみへと変わっていき、僕は猫を避けるようになった。ただはっきりとした恥ずかしいという気持ちと前の残虐な行為の記憶が、猫を虐待することを妨げていた。僕は数週間は猫をたたいたり、いじめたりはしなかった。でもだんだん、まさしくだんだんとだが、僕は言葉にはし難い憎しみの気持ちをいだいて猫をみるようになり、まるでペストがやってきたかというようにその憎むべき姿から、さっと身をかわすようになった。
まちがいなく、その猫への憎しみをましたのは、つれて帰った日の朝、プルートとおなじように片目がないことをみつけてからだった。でもこうしたことは妻にとってはその猫をかわいがる理由にしかならなかった。妻は、前にも言ったとおり、僕の前の特質であった、もっとも素直で純粋な喜びの源であったあの暖かい感情を存分に持ち合わせていたからだ。
ただ僕がこの猫を嫌えば嫌うほど、猫は僕のことが好きになるみたいだった。みんなには分かってもらえないほど、僕の後をずっとつけまわし、僕が座っていると椅子の下にやってきて、ひざに飛び乗り、あの恐るべき愛撫を僕にするのだった。僕がたちあがって歩き出すと、足のあいだにからみつき、僕を転ばせんばかりで、あるいはその長く鋭いつめを僕の着ているものにたてて、僕の胸のところまで上ってこようとさえした。そんなときはいっそのこと殴り殺してしまいたくなったが、そうできなかったのは前のことを覚えていたからでもあるが、本当のところは言わせてもらえば、この猫が怖かったのだ。
この恐怖は正確に言えば、肉体的な恐怖ではない。ただ、僕にはなんと言っていいのかわからない。犯罪者としての監房にいても、口にだすのは非常に恥ずかしいことだが、この猫が僕にいだかせる恐怖と戦慄は、僕がもっている単なるひとつの妄想にすぎないものでますます高まっていった。妻はよく僕に一度ならず言ったものだが、前にふれた猫の白い部分の模様は、僕が殺した猫とこの猫の唯一の目に見えるちがいだった。読者の方もこのしるしが、大きいけれど、もともとはっきりしない形だったことを覚えておられるだろう。でもゆっくりと、ほとんど気づかないくらいゆっくり、僕の理性は長い間たんなる気の迷いだとしりぞけようとしていたが、それは、とうとうはっきりとした輪郭をとるようになった。僕がゾッとして名前を言えないようなあるものの形を。結局このしるしのために、僕はこの猫を嫌い、恐れ、いっそのこと消してしまいたいと思ったものだ。いまや、おぞましい、不気味なものの形をとるようになった。それこそは絞首台で、恐怖と犯罪、苦悩と死の、陰鬱で悲惨な原動力だった。
そうして僕は、人間が味わう悲惨さのなかで、もっとも悲惨なものを味わった。仲間は見下し殺してやったその畜生が、僕にしたことは、神をかたちどったこの人間の僕にしたことは、まったく耐え難いことだった。あぁ、昼夜をとわず、安息はなかった。この猫が、僕をかたときも一人にしておかないのだ。夜に僕が一時間ごとに言いようがないほど恐ろしい夢から目をさますと、僕の顔のところには温かい息をふきかける、ずっしり重いものがいて、それは夢の悪魔が実在のかたちをとったようで、僕にはふりはらうこともできず、永遠に僕の心に課せられた重荷のようだった。
こうした拷問にさらされていたせいで、僕の中にあったよい心のかすかな名残も消えさった。悪意こそが、それももっとも深く邪悪な悪意が、僕の唯一の友となった。ふつうのときから全てのものや人を憎むようになり、とつぜん、それもしばしば、抑えきれない憤怒の情にかられて、自分がまったく分からなくなり、そして文句をいわない僕の妻が、かわいそうに、いつもその被害をうけ耐えていた。
ある日、僕と妻はいっしょに家の用事を片付けに、貧乏ゆえに住まうことになった古い家の地下室にいった。猫は階段を降りるときも僕についてまわり、もうすこしで僕は階段から転げ落ちるところだった。そこで、怒りにわれを忘れてしまった。斧をふりあげると、今まで躊躇していた子供っぽい恐怖心も怒りゆえにすっかりわすれ、猫にむかってふりおろした。もちろん僕の思い通りになれば、即死だっただろう。でも妻が僕の手をつかんで邪魔をした。邪魔で、怒りは悪魔以上のものとなり、妻の手をふりはらうと、その頭めがけて斧を一刀両断うちおろした。妻はその場所に、うめき声ひとつあげずに倒れ、亡くなった。
(つづく) 後編はこちら