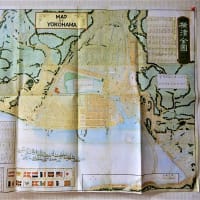大岡川に架かるのは、現存は大井橋・鶴巻橋・蒔田橋・山王橋・一本橋・道慶橋・太田橋・黄金橋・旭橋・長者橋・宮川橋・都橋の12橋。架替は越戸橋・観音橋・井土ヶ谷橋・清水橋・栄橋・末吉橋・大江橋・弁天橋の8橋。
大岡川も長者橋のあたりになるともう東京湾が近い。


現存・宮川橋。


夜が華やぐ街。


現存・都橋。


その先は桜川橋。


そして大江橋となる。

関東大震災復興橋梁・大江橋は市施工・復旧費災害土木費其他支辨橋梁16橋のひとつ。昭和48年に架け替えられた。



横浜震災復興誌によれば、當時の神奈川縣令大江卓氏の名に因みて大江橋と命名し開橋したり。とある。
ところで。大江卓氏ってだれ(?_?)
ざっくりと調べたところによれば。
土佐出身の幕末の志士。中岡慎太郎の陸援隊で討幕運動に参加。明治政府に出仕。同志であるところの当時神奈川県令だった陸奥宗光にスカウトされて神奈川県に赴任したという。横浜震災復興誌では縣令(知事)となっているが、正確には権令(副知事)だったようだ。が、忙しい陸奥に代わって実質的には知事だったようだ。
大江の日本近代史に残る業績は、「マリア・ルス号事件」の解決にあるという。
橋に個人名が付くだけあってなるほどに相当な傑物だった!!!
大江橋の歴史も横浜震災復興誌に詳しく記載されている。
明治3年起工
明治5年竣工
明治35年架け替え
この明治35年の橋は、プラット式構桁橋。171尺1径間。全幅47尺。担当技術者は綿貫工學士。
大正10年改築著手
大正11年竣工
この橋は、2鉸式鋼拱橋中央径間63尺両側径間54尺。全橋長32間。全幅員13間。担当技術者は朝倉工學士。
そしてこの時出た鐵材は大正11年に山下橋に使われたという。


関東大震災復興は、横浜震災復興誌によれば。
位置・中區櫻木町一丁目尾上町六丁目地先(第四號街路)
橋種・鋼拱(修繕)
橋長・58.78m
有效幅員・23.63m(車16.36歩3.63×2)
面積・1.389.32㎡
施工期・著手昭和三年二月十七日:竣功昭和三年七月十一日
總工費・17.759.31円
とある。
上だけの補修で車道は花崗岩で歩道はソリデチットで舗装したようだ。
親橋は、素っ気無い(^^;




旧橋はかなり装飾性があったようだが(^^;

それにしても(^^;
知事というのもずいぶんと小粒な仕事になったものであるなぁなんぞと思ってしまったりなんかした(^^;(^^;
神奈川の前知事なんて嫌煙が錦の御旗だったもんなぁ(^^;(^^;(^^;

大江橋の先は弁天橋。