
近くのいくつかの図書館をよく利用する。
中央、駅前、隣の市もカード共用なので、ありがたい。
自分の興味以外の分野にも一通り目を通せる点がいい。
1哲2歴3社4自5工6産7芸8語 それに雑誌、新聞コーナーを
一通り目を通す。
先週は、余り関心がなかったイギリスの本を借りてきたが、
一気に読み終えた。
井形慶子著「イギリス人の格」
そこには、日本の現状とはまったく違う生き方が
鋭い視点で示されている。
これまでなぜイギリスに興味がなかったか?
それは産業革命が生まれ、植民地で繁栄した後、
斜陽の国として、過去の遺産にしがみつく
保守的なイメージがあったから。
今の日本の問題:
格差、環境、社会保障、少子化、生きがいetc.
に対して、さすがに成熟したイギリスは、一歩進んだ点が
あるようだ。
(アメリカと一線を画している点に共感)
一番感心したこと:
「家庭生活を愉しむゆとり」
・年配者もオシャレで、ガーデニング、Do It Yourself
・散歩とTea Timeの紅茶
・家事の知恵(洗剤なし、残り物料理、美化清掃)
豊かになった日本の一般的な生活に無いものが、
いっぱいあるような気がする。
何でも買って済ます、休日はどこかに物見遊山、
ドラッグストアの多いこと!
食べ物のムダにも何も感じなくなっている。(飽食)
家庭団欒という場も少なくなり、これが社会問題を
生む元凶にもなっているという。(確かにそういう面がありそう)
ドイツ主婦連盟主催の「家事免許証取得コース」も紹介されている。
家庭省の「家事オーガナイズトレーニング」では、洗剤、オーブンの使い方など
生活の常識を啓蒙している。
当然イギリス人は率先して実行している。
ビクトリア時代の言葉:
「政治家が国づくりをしている間に、
優れた料理人だけで国をまとめることができる」
「わがままなムダは貧困をもたらす」
おばあちゃんから譲り受けたレシピ集にも、残り物で作る
スープやパイが多く紹介されているという。
日本でも、
核家族になる前、戦後すぐの時代までは
農家だけでなく、町屋でもよく見られた風俗だ。
(サラリーマンは勤め人と言って、公務員が主で極めて少数)
わが国のマイホーム主義も、
「家造り」だけでなく、「どう住まうか」が問題だろう。
ずっと前に新聞か何かで
18世紀ごろ、ドイツ・オーストリアを中心に「家父学」が
隆盛したという。言わば、家事の勧め。
例えば、・妻との人間的なつながり/協力の仕方/子供の教育/
野外での遊び方/家庭教師の選び方/薬草の見つけ方/
料理法/近隣との交際etc.
日本でも、同じような風俗・伝統があったが、
明治政府の「富国強兵」とともに、家事蔑視の方向に進み
現在に至ったと言えるだろう。
*参考「翁問答」中江藤樹著、「和俗童子訓」貝原益軒著、
「家庭の新風味」堺利彦著、「親子論」「育幼論」植木枝盛著*
いろんな社会問題の解決策のヒントが
イギリス人の生活スタイルの中に見出せる。
それは、
美しい国、日本人(国)の品格、そして団塊世代のテーマにも
つながるように思う。
中央、駅前、隣の市もカード共用なので、ありがたい。
自分の興味以外の分野にも一通り目を通せる点がいい。
1哲2歴3社4自5工6産7芸8語 それに雑誌、新聞コーナーを
一通り目を通す。
先週は、余り関心がなかったイギリスの本を借りてきたが、
一気に読み終えた。
井形慶子著「イギリス人の格」
そこには、日本の現状とはまったく違う生き方が
鋭い視点で示されている。
これまでなぜイギリスに興味がなかったか?
それは産業革命が生まれ、植民地で繁栄した後、
斜陽の国として、過去の遺産にしがみつく
保守的なイメージがあったから。
今の日本の問題:
格差、環境、社会保障、少子化、生きがいetc.
に対して、さすがに成熟したイギリスは、一歩進んだ点が
あるようだ。
(アメリカと一線を画している点に共感)
一番感心したこと:
「家庭生活を愉しむゆとり」
・年配者もオシャレで、ガーデニング、Do It Yourself
・散歩とTea Timeの紅茶
・家事の知恵(洗剤なし、残り物料理、美化清掃)
豊かになった日本の一般的な生活に無いものが、
いっぱいあるような気がする。
何でも買って済ます、休日はどこかに物見遊山、
ドラッグストアの多いこと!
食べ物のムダにも何も感じなくなっている。(飽食)
家庭団欒という場も少なくなり、これが社会問題を
生む元凶にもなっているという。(確かにそういう面がありそう)
ドイツ主婦連盟主催の「家事免許証取得コース」も紹介されている。
家庭省の「家事オーガナイズトレーニング」では、洗剤、オーブンの使い方など
生活の常識を啓蒙している。
当然イギリス人は率先して実行している。
ビクトリア時代の言葉:
「政治家が国づくりをしている間に、
優れた料理人だけで国をまとめることができる」
「わがままなムダは貧困をもたらす」
おばあちゃんから譲り受けたレシピ集にも、残り物で作る
スープやパイが多く紹介されているという。
日本でも、
核家族になる前、戦後すぐの時代までは
農家だけでなく、町屋でもよく見られた風俗だ。
(サラリーマンは勤め人と言って、公務員が主で極めて少数)
わが国のマイホーム主義も、
「家造り」だけでなく、「どう住まうか」が問題だろう。
ずっと前に新聞か何かで
18世紀ごろ、ドイツ・オーストリアを中心に「家父学」が
隆盛したという。言わば、家事の勧め。
例えば、・妻との人間的なつながり/協力の仕方/子供の教育/
野外での遊び方/家庭教師の選び方/薬草の見つけ方/
料理法/近隣との交際etc.
日本でも、同じような風俗・伝統があったが、
明治政府の「富国強兵」とともに、家事蔑視の方向に進み
現在に至ったと言えるだろう。
*参考「翁問答」中江藤樹著、「和俗童子訓」貝原益軒著、
「家庭の新風味」堺利彦著、「親子論」「育幼論」植木枝盛著*
いろんな社会問題の解決策のヒントが
イギリス人の生活スタイルの中に見出せる。
それは、
美しい国、日本人(国)の品格、そして団塊世代のテーマにも
つながるように思う。










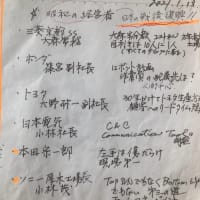
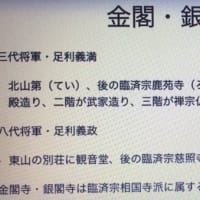
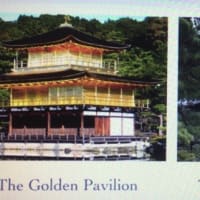
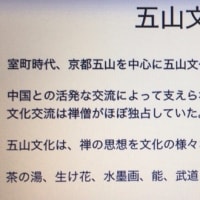
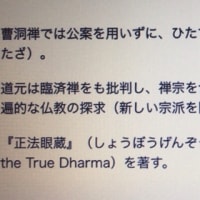
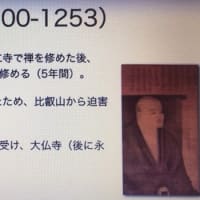
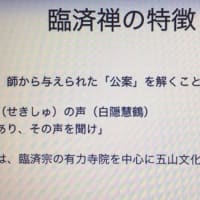
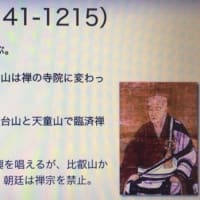
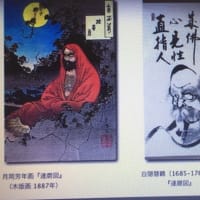
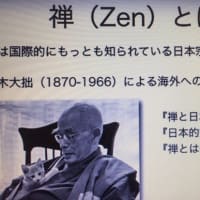
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます