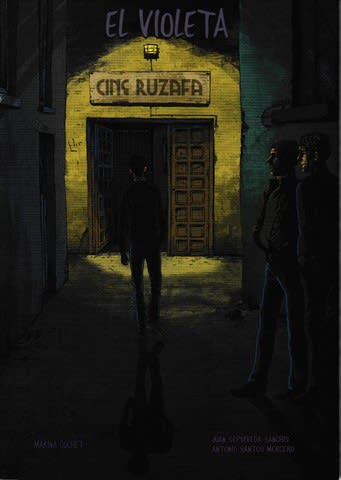グラフィックノベルというより本の袖にもあるようなコミックで、日本風に言えば四コマ漫画だけれど、必ずしも四コマとは限らない、要するに1ページのなかで完結した小話集。作者のラウラさんは絵画修復師としての経験もおありなのだとか。とにかく絵のセンスがよくて、リアリズム系のグラフィックノベルにありがちな土臭さとは無縁。こういうのを待っていました。
2011年の『レッツ・パチェコ~家族の一週間』と2013年の『セニョール・パチェコ~秘密情報員』は家族に題材をとったオートフィクションのグラフィックノベルのようだ。いまはエルパイス紙別冊やモード雑誌を中心に活躍中。
ご本人のHPの about でお話が聞けます。
ブログでは作品の中身も少し。
たとえば下のような感じ。
あるある、的なシチュエーション。
スペイン語知らなくても分かりますよね。

道ですれ違った知りあいに声をかけたら相手はアディオスと一言。まあ、そういうこともあるのだけれど、こっちはオラなのに、なんでそっちはアディオスなんだよ。
むむむ、あるある。
というようなシチェーションばっかり。
押しボタン信号をめぐる駆け引きとか。
そんな信号、スペインにもあるんだ。
数人の女性を中心にテーマごとに8つの章に分かれている。職場、恋人、家族、SNS、友だちと隣人、休暇。このうち休暇というのはヨーロッパ人の強迫観念的な休暇のことなので、働きマニアの日本人には少しわかりにくいかも。あとは私たちがふつうに読んで楽しめて、にやっとさせられるものばかり。
絵も可愛らしく、キャラの描き分けもきちんとできていて、吹き出しの文字も短く、きちんと落ちがあって、ややシニカルで、そうかといって変なメッセージ性はなく笑って読み飛ばせる。スペインの長谷川町子を目指してぜひ頑張ってもらいたいです。
下は「隣人」の章に出てくるマンション管理人のコンスエロさん。どこかにくめない意地悪ばあさんです。

どうも。私宛のはありました?/お部屋番号は?/4B。/ああ、それなら見たような気が…えっとたしか…。/もうポストに入れたってばさ。/銀行からの通知が二通と絵ハガキ一枚。差出人の名前までは見えなかったけど。/どうも、コンスエロさん。
Laura Pacheco, Problemas del primer mundo. 2014, Lumen, pp.159.