 テキストクリティックを行なっているカテドラ版(2016)のイントロに基づいてこの奇妙な本の変遷を簡単にまとめてみると、まず1973年に初版がバラル・エディトーレスから刊行された。同じ年に第二版が刊行されているが実質二刷でリタッチはなし。翌74年の第三版も同様で、これの現物が国内では京都外国語大学にあるようだ。翌75年にはグリハルボから新版が出ている。ちなみにキューバとチリではそれぞれ違う理由から発禁処分となっていて、チリでは粗悪な海賊版も出回っていたという。私はこれらの現物を実は見ていない。それが実は大問題なのだが、あとで説明するとして、ここまでは実質すべて「初版」と考えていいようだ。
テキストクリティックを行なっているカテドラ版(2016)のイントロに基づいてこの奇妙な本の変遷を簡単にまとめてみると、まず1973年に初版がバラル・エディトーレスから刊行された。同じ年に第二版が刊行されているが実質二刷でリタッチはなし。翌74年の第三版も同様で、これの現物が国内では京都外国語大学にあるようだ。翌75年にはグリハルボから新版が出ている。ちなみにキューバとチリではそれぞれ違う理由から発禁処分となっていて、チリでは粗悪な海賊版も出回っていたという。私はこれらの現物を実は見ていない。それが実は大問題なのだが、あとで説明するとして、ここまでは実質すべて「初版」と考えていいようだ。 実質上の第二版、つまり本文リタッチと文章の入れ替えと別原稿追加のある版が、上の写真のセッシュ・バラルから出た1982年版である。ここにはエドワーズによるイタリック体の前書き10ページ分が含まれている。また「パリ・エピローグ」と題する後書きが付されているが、これについてエドワーズは自ら次のような注釈をつけている。
<以下は1973年10月にバルセロナとカラフェルで書き上げたテクストである。チリの出来事を知った直後で、1971年と72年の個人ノートを書物の形で刊行する用意をしていたときのことだ。いくつかある初版ではこのエピローグにノートの最後の数ページを挿入していたが、今回はその初期版ではなく、本来の『ペルソナ・ノン・グラータ』を形成する71年と72年のノートと、そのオリジナルテクストが編集者の手に渡っていたときに書かれた「パリ・エピローグ」をすべて元の形で再現することにしたい。(1982, 375)>
よく意味が分からないのだが、初版ではエピローグという形ではなく本文に埋め込まれていて、キューバ体験を綴ったノートに書かれた文章の最後の数ページと合体していたという意味であろう。それがどういう状態か確かめないままこれまで来ているのが「大問題」だと昨夜反省していたのだが、この作家で論文を書いているわけではないので許してほしい。いずれにしても、この「初の完全版」をとりあえず第二版と考えよう。
第三版は中身リタッチはなしで、新たなプロローグが付されてトゥスケッツから1991年に出ている。チリの民政移管後というタイミングで、昨日まで紹介していた『さらば詩人』の刊行直後ということになる。エドワーズは1999年にスペイン語圏文学者に与えられるセルバンテス賞を受賞している(その関係で私にも翻訳の仕事が回ってきた)。それを受けて2000年に同じトゥスケッツの記憶の時代というシリーズに含められ、新たなプロローグと旧版すべてのプロローグ、エピローグが採録された、いわば完全な完全版みたいなのが出ていて、これは私も持っている。
ところが今度は2006年にアルファグアラから新版、これまでの経緯を考えると第五版とみなしていいだろう、が刊行され、これは旧版のすべてのプロローグとエピローグを削除したシンプルな構成で、新たに「二重の検閲」と題するエピローグだけが追加された。これが私が翻訳した版で、2012年頃の段階で著者とエージェントの指示に従ったものである。
最後は2015年にアルファグアラの文庫版が出て、これでは過去のあらゆる「ローグ」が削除されて新たにプロローグが付された。そして最新はカテドラの分厚いイントロダクション付きの版ということになり、これは過去の「ローグ」系をすべて掲載しているので、とりあえずプロはこれを読めと言うことなのでしょう。
初版の最終部の形状が気になるところではあるが、とりあえずそれは置いておき、まずはトゥスケッツに搭載された「パリ・エピローグ」の中身を紹介しておくことにする。
<バルセロナから電話でネルーダと話をした。私は神経をだいぶ痛めつけられたキューバでの体験から自分を癒そうとしていたところだったが、彼は翌日に予定されていたポンピドー大統領への信任状提出に立ち会えと言ってきた。T.,351)>ネルーダとしてはいちばん信頼できる部下が来てくれたので、バルセロナで文学仲間とつるんでないですぐにパリに来いということだったのだろう。ネルーダのパリ赴任は1971年3月、エドワーズが好ましからざる人物扱いされてハバナを出ていくのが同年の3月21日、まあ、フィデルのおかげで、ネルーダは赴任早々もともと希望していた優秀な部下を近くに置くことができたので、よかったじゃないか、と私は思う(とフィデルも言いそう)。
式典の後の数日間、エドワーズは上司ネルーダにキューバでの体験を事あるごとに語り聞かせた。
<「本を書きたいんです」と私はパブロに言った。「刊行はできなくてもいい。そうしないとこの強迫観念から逃がれられないんです」
「書くがいい!」とパブロは言った。「私に話したことをひとつ漏らさず書きとめておきなさい。世に出すことを考えてはいけないよ!いつかはそのチャンスも来る。それは重要な本に、必要不可欠な証言になるだろうから……」(T., 353)>
その後はキューバ追放とパディージャ事件の余波について、だいたい『さらば詩人』の第三部と同じようなこと、エドワーズの外務省内での立場を守ってくれたのがネルーダとクロドミーロ・アルメイダであったというようなことが書いてあって、またパディージャ事件の余波は、ペルーを公式訪問した際にはアジェンデ夫妻と談笑もしたマリオ・バルガス・リョサが、その後、チリ政府からの公式な招請を断ったというような情報も開示されている。
1971年、秋、いよいよノーベル賞の季節になる。いまはどうか知りませんが、スウェーデンのアカデミーのなかで特定の作家を推す人たち(詩の場合は翻訳者が多いよう)が関係者に内通する習慣があったのでしょうか、少なくともエドワーズはスウェーデン人の作家仲間からネルーダに決まり!の通知を電話で受け取っているようだ。その直後、パリを離れたがっていたネルーダに請われて、二人はノルマンディーに家探しに行く。このあたりの顛末は『さらば詩人』と同じです。ちなみにラ・マンケル購入に際して、これがチリの議会で問題視され、右派の政治家が「ネルーダ大使はノルマンディーで税金を投じてシャトーを買ったそうだが大丈夫なのか?」と発言し物議を醸したそうである。
それよりページが割かれているのはフランスの政治家たち。当時のチリは世界中の左派政治家たちにとってあこがれの国だった。日本も含めて、20世紀後半の世界の先進国の多くに万年野党「社会党」という人たちがいた。社会主義者たち。共産党やそれに類するもう少しドラスティックな政策を唱える左派もいたが、いずれも議会での多数派工作には失敗し続けている。しかしチリで人民連合という左派の大同盟が政権を取った。そんなことが可能なのか? 可能ならどうすれば実現できるのか? というわけで大勢の左派政治家たちがアジェンデ参りをしていた。フランスからは共産党のジャック・ドゥクロ、社会党のフランソワ・ミッテランがチリを訪れ、その後、いずれもパリでネルーダやエドワーズと会見している。
それを牽制すべく右派、このときはドゴール派の議員アラン・ペールフィットもキューバとチリを立て続けに訪問、急用で空港を通過するのみとなったサンティアゴで自国のプレスにフィデルとの会談の様子をリークする。<ペールフィットは、フィデル・カストロが、アジェンデはブルジョワ的合法性の狭すぎる枠組みに留まる限り自らの政治を実現することはできない、と言った、とメディアに語った。チリにおける社会主義への穏健な移行をフィデルが常々疑いの眼差しで見ていたことは周知の通りである。から鍋デモと、国家元首としては史上最長の滞在となったチリ訪問の最後をしめくくる、あの国立スタジアムでの演説でも、それは明らかだった。(365)>エドワーズは、おそらくペールフィットはチリと同じ左派の大同盟を期待する一部のフランス人に向けて、そういう道は必ず暴力を伴う、というメッセージをフィデルという分かりやすい道具を用いて伝えようとしたのだろう、と推測している。アメリカという国がチリの社会主義を転覆させようと暗躍していたのと同じころ、フランスでは一部の政治家たちがチリに倣おうとしていた状況が浮かび上がってくる。学者でもあったペールフィットはネルーダに、ドゴールはアルジェリアの独立と社会主義化を平気で容認したというのに、アメリカというのは奇妙な国だ、植民地でもないキューバやチリが社会主義化することが許せないらしい、と冗談半分で語ったそうである。いずれにしても、当時のフランスにおけるチリ大使館とは、左派も右派も、何らかの形でアジェンデ政権の今後に関心を持つ人たちが毎日のように押しかけてくる場所だったのだ。そりゃ、大使も、詩を書く暇はなくなりますわね。
1973年3月、もうネルーダは帰国後のことだが、たまたまフランスとチリの総選挙が重なった。ミッテランらの左派連合の勝利を恐れた右派はパリ市内に、ミッテランらの話をうのみにしているとチリのような暗い未来(内戦寸前)が待っている、とするビラを貼るなどし、エドワーズらを憤慨させたようだ。結局この選挙でフランス社会党は躍進、いっぽうチリでも人民連合が躍進、これについてエドワーズは<その数か月後にある情報通の人間から、あれでアジェンデの運命も煮詰まった、と聞かされた。アジェンデはキリスト教民主党と妥協する心づもりでいたが、この三月の結果を受けて、人民連合の最左派がいかなる取り引きにも応じなくなっていた。いっぽう選挙で権力を取り戻す望みが途絶えた右派はクーデターの本格的準備に取り掛かっていた(T., 368-369)>として、この選挙が、このあとチリがなし崩し的に動乱に巻き込まれていくきっかけになったとみているようだ。
クーデターに至るまでのアジェンデ政権に関するエドワーズの評価は本書の本文にも書かれている。このエピローグでも再度触れているが、73年のこの三月以降に本来そうすべきであったキリスト教民主党系の、つまり保守側の議員の取り込みと軍部のなかの話の分かる人たちの取り込みがまったく進まず、事態が逆の方向に動いたことがクーデターへの動きを加速させたということだ。サンティアゴ滞在中のフィデルがアジェンデその人や左翼革命運動の指導者たちに象徴として機関銃を手渡すパフォーマンスをしたことも、後々、軍事評議会がキューバの介入を口実にする根拠を与えた。内戦やクーデターを避けるという試みをあらゆる方向からつぶす動きが続き過ぎた、というのがエドワーズの見立てである。彼の言に従うならどうやら外務省はまだそうしたウルトラ左翼の影響を受けずにいる人間が多かったらしい。<アルメイダはアジェンデの閣僚のなかでおそらく最も賢明な人物だった。人民連合政権における彼の影響力は、不必要な挑発を回避するという方向に傾きがちだった。外交のスタンスは異なる勢力と等しく距離を置くというもので、国家としての独立を重視し、同盟には慎重だった。モスクワとの関係の調整についてはリアリズムに徹し、中国との関係を損なうこともなかった。(T., 377)>このクロドミーロ・アルメイダならニクソン政権とも渡り合えたろうが、向こうがそれどころか銅訴訟をたてに一切の外交を拒絶してきたので、それは実現せず、クーデター後はこの「アジェンデ政権内の数少ないまともな人」アルメイダもドーソン島に収容され、その後は亡命を余儀なくされることになる。 話は1972年に戻り、ラ・マンケルでの新年会。誰を呼ぶ、誰を呼ばない、の話がもつれて結局コロンビアの詩人アルトゥーロ・カマチョ・ラミレスとその妻、ネルーダ夫妻、エドワーズ夫妻の6人だけのパーティーになった。 <あれはとても明るいパブロ・ネルーダを私が目にする最後の機会になった。あの頃のネルーダはよく黙りこくって考え事をするようになっていた。午後のあいだを窓辺に腰掛け、蚤の市で買った船乗り用の双眼鏡で(大使館の窓から見える)彫刻が施された金色のドーム屋根を見つめていたものだ。「最初は気に入らなかったが」と彼は言った。「でもほら、あの形を見ているうちにだな、あの彫刻、あの金色、縦のラインが好きになりだしたのさ……」(T., 378-379)>
実はこのとき大使館には大変な業務がきていた。71年11月に銅の完全国有化のための憲法が改正され、その後、アメリカ企業(とCIAとエドワーズは指摘している)の圧力で銅の価格は下落、外貨がいっさい入ってこなくなったチリは対外債務の支払いを停止せざるを得なくなる。パリクラブ(という名の優雅な債権取り立て人たち、とエドワーズは書いている)は至急チリ大使を呼びたてた。ここからエドワーズは、ヘネシーという名のアメリカ通商代表の気どった男を相手にした交渉を説明するなかで、『さらば詩人』ではざっくりとしか書いていなかったチリの二大銅企業、つまりケネコットとアナコンダについて詳細に説明している。パリクラブ側の主張としては、これらの企業への補償金を払わない以上、それらはすべて債務として過去の借金に加算されることになるから、チリの債務問題は一からやり直しというものだった。もちろんチリの代表としてエドワーズらはアジェンデ政権の言い分も伝えなくてはならなかったが、『さらば詩人』でも触れられていたように、それは詩人ネルーダですら非現実的と評する言い分で、話にならなかった。
エドワーズはチリにケネコットが進出した19世紀に遡っている。スプリュール・ブレイデンがコンチャという地主が所有していた僻地エル・テニエンテを安値で買い取り、そこにケネコットの支社ブレイデン・コッパーを創業する。<あれはチリの19世紀を特徴づけた国内経済の発展がその動きを完全に止めてしまった時期だった。1891年の内戦でバルマセーダが敗北して以降、チリは経済的にも文化的にも究極の植民地化の時期を経ていた。国中が二束三文で売り飛ばされていた。エル・テニエンテに拠点を構えて以来、ブレイデン・コッパーは1930年に至るまでチリ政府に一センターボの税金すら納めていない。(T., 381)>という歴史もエドワーズは知らないわけではなかったが、この後もチリは銅資源をめぐって基本的には米国企業に負け続けて1971年を迎えてきたわけだ。歴史の課した不条理をそれこそ「従属理論」の立場から新興国の債務弁済を正当化する根拠として使用したくなる気持ちも分からないではなかったろうが、外交官としてその種の言上げが無理筋だという現実も忘れていなかっただろう。
いっぽうのネルーダはパリクラブのあと別のクラブ、今度はニューヨークの国際ペンクラブに招待され、開会の演説をすることになって、ついこのあいだ自分がいたパリクラブが自国チリの命運を勝手に決めている現実について話をする。<アメリカの代表——宴会のお酒を思わす名前の男——はコールリッジの詩でアホウドリを殺す船乗りを思い起こさせました。その船乗りはその後の一生を殺したアホウドリを背負って過ごすことになるでしょう。地図を見ればわかりますがチリは飛翔するアホウドリのような形をしているのです……。この演説でネルーダはミスター・ヘネシーに一生チリを背負い続けることになると警告した。その後パリクラブでの交渉をしていたあいだ、当のヘネシーが私に近づいてきて、ネルーダの自分に対する批判はひどくないかと言い出した。「私はチリに危害を加えようとしたことは一度もない。妻はパラグアイ国籍で、ネルーダさんの大ファンだ。我が家には彼の本がたくさんあるのに」。しかしながらネルーダの宣告は現実のものとなり、思うにヘネシー君も今ごろはそのことをよくわかっていると思う。コールリッジの教えに基づくなら、彼にとってただ一つの救いがあるとすれば、自然、あらゆる生き物への愛を知ることだ。そうすればアホウドリの重荷は彼の首から離れて海に沈んでくれるだろう。(T., 382)>とある。コールリッジ「老水夫の詩」に現れるアホウドリをチリになぞらえての演説ということだが、これは全集には採録されていなかった。パリクラブでの会合は最後はだいたい飲み会だったらしく、そこでアメリカ以外のチリに理解ある国の通商代表たちに慰められていたのだとか。そのなかでネルーダがこういうことを言ったとエドワーズは書いている。<アメリカの圧力はこれからも容赦ないだろう」と彼は言った。「甘い期待は少しも抱いてはいかん。政府の超過利潤という理屈は、我々にはどれだけ好ましいものであっても、奴らを納得させることはできない。あれは資本主義そのものを敵に回す理論だ。大資本というのはまさにその超過利潤で生きているのだからな。(T., 383)>ここでネルーダが言っている超過利潤、スペイン語で utilidad excesiva の理屈というのは、ガルセス『アジェンデと人民連合』(時事通信社)等によると、いわゆるアジェンデ・ドクトリン、すなわちチリ政府がチュキカマタやエル・テニエンテのような大銅山を国有化し、その補償額、すなわちケネコット等に支払うはずの推定金額のうち、1955年から70年までの平均で年14%を上回る超過利潤を差し引く、というものである。
ネルーダが言うように資源レントだけで食っているケネコット側が納得するはずもなかった。ケネコットは対抗策として、国有化されたエル・テニエンテから出荷された銅を運搬していた船を差し押さえ、パリの大陪審にチリ政府を相手にした訴訟を起こすことになる。というわけで今度はパリクラブから大陪審に場所を変え、ネルーダとエドワーズが呼び出されることになった。1972年末、ネルーダの病状はかなり悪化している。<主任判事と二人の副判事が代表するパリ大陪審の目にも状況は間違いようのないものだった。いっぽうには強大で巨大な触手を伸ばす多国籍企業ケネコットが、そしてもういっぽうにはチリという貧しい国がいて、その1972年10月の時点でその国の財政は危険なラインに触れるかもしくは超えようとしていた。ルネサンス風の高い窓から差し込む光に照らされた病気のチリ大使の厳しい表情は、深い、なにかその場の象徴的な憂鬱さを湛えていた。(中略)パブロは疲れたということを表情で示し、退出しようとした。難儀そうに立ち上がると、忍び足で出口を目指した。私は彼に付き添ってひとけのないホールを横切った。「こちらの弁護士の主張はよかったな」と彼は言った。「向こうの弁護士はマルクス主義がどうとか言って判事の気を引こうとしていたが」。しかしパブロは決して楽観主義に流されるような人ではなかった。「なんでもチリでは」と彼は言った。「奴らがあらかじめデモを動員して、すっかり満足しているそうだ、この裁判にも影響があるとでもいわんばかりにね…」。彼はチリ政府が向こうの要求する補償金を払わない限り、相手が手を緩めることは決してなく、最後には強硬手段に出てくると考えていた。「司法権外だとかどんなに理屈をこねてもここにいるフランス人たちを説得することはできない。彼らが知りたいのはチリが補償金を払ったか払ってないかだ。彼らにとって問題はそこにしかないのだ。(T., 385-386)>
結局、私企業が一独立国を訴えるというこの異常な訴訟についてパリ大陪審も扱い兼ねたのか、最終的に手術後のネルーダがアジェンデ政権からの伝言、独立国が他国の法廷で裁かれることを拒否する、を二度目の審議で渡した後で大陪審側が訴訟そのものから手を引く意思を示した、とエドワーズは書いている。彼は大陪審の動きにはおそらくケ・ドルセー、つまりフランス外務省の圧力がかかったことも間違いないと指摘したうえで、チリ外務省界隈では彼がフランスでチリを売り渡そうとしたとする噂も流れていたと書いている。
ゴシップも忘れない人です。
その裁判が実質終わってもネルーダは悲観的だった。<「わが国の資源の国有化が他国の法廷で審議されるなどもってのほかだ」と伝言を受け取ったパブロは言った。「とはいえ実質の審議は進行中なのだよ。例の銅は差し押さえられたままだ。世界中に銅を売りさばくことにこそ、わが国の主権が働くというのに!」(T., 389)>
エドワーズは当時のネルーダの世界情勢の見方ついても触れている。<そのころパブロはよく、真のベトナム、もうひとつの静かなるベトナムこそがチリである、と言っていた。そして改宗した根っからのソビエト信者として、ソ連には世界のどこが危うい状況にあるか正確な認識がないように見える、と、ほのめかすこともあった。彼らがベトナムで一月に使っている資源を一年でもいいからチリに向けてくれたら……。私は彼に、チリには戦車も対空砲も要りませんよ、と指摘した。チリに要るのはドルと小麦ですが、いまのソ連ではどのどちらも枯渇しています。するとパブロは黙ったまま唾を飲み、容赦なく聡明な眼差しで地平線上に重なる黒い雲をじっと見つめるのだった。チリではトラック運転手の危険なストが長引いていて、工員たちが多くの工場を占拠し、国全体が分断で麻痺し、決裂直前のように見えた。(T., 390)>ノーベル文学賞を受賞したわずか1年後にここまで深刻な立場に追い込まれた作家がいただろうか?
その後は債務をめぐる外交上の交渉の話題になっている。欧州諸国は左派が伸長したフランス以外のスペインやオランダやイタリアといった国々はチリに融和的、西ドイツは農地改革でチリ南部に所有していた土地を失った議員がいて危ういところだったが、社会民主党政権がチリに融和的な態度を示す。だが、債券の圧倒的多数を占めている米国が、てこでも動こうとしない。アジェンデはメキシコと国連本部を相次いで訪問し、米国通過時にはニクソンとの面会も打診するが当然無視され、そのままモスクワへ支援を求めに行く。クロドミーロ・アルメイダは中国に援助を求めに行くが、周恩来からチリのやり方は性急すぎる、中国が10年かけたことを2年でやろうとしているのはさすがに無茶ではないかと釘を刺されたりと、あまり外交面からアジェンデ政権の話をしている本を読んだことがなかったので、このあたりの情報は単純に面白い。
1972年のネルーダと枢機卿との対面、その後のネルーダのチリへの帰国、年が明けて1973年、3月の総選挙で人民連合が勝利していよいよ内戦かクーデターが避けられない(とエドワーズは考えた)情勢に差し掛かる直前、彼はパリでモスクワ訪問後の軍人一行を出迎えた。モスクワで二週間、現地の軍施設に実質監禁状態にあった彼らは酒を飲んで大いにはめをはずし、夜も更けたころ、うちのひとりがエドワーズに近寄ってくる。
<「思うに君は抵抗派なんだろうね?」
「さあ、いったい何に対する抵抗でしょうか?」
将校はやや困惑しながら片方の眉をあげ、それ以上は何も言わなかった。彼らはモスクワでの生活のこと、そこで感じた悲しみ、夜の九時を過ぎると遊ぶ場もなく、レストランはとにかくサービスが遅いことばかりを話題にしていた。
軍がまだ政府と共にあったそのころ、将校たちを率いていた長官は、自らを、残存する数少ない遵法派の軍人であると考えていた。彼は将校たちにアジェンデに対する忠誠を求め、チリでは「政治に鼻を突っ込まないこと」と繰り返し、そして「全チリ人の和解のために」働けと伝えていた。私は彼がアジェンデの名前を口にしただけで、将校たちのあいだに言葉にならず耳にも届かない絶望が引き起こされたことに気が付いた。(T., 395)>この辺はエドワーズにしてみたらすでに、キューバで練習船エスメラルダ(このあいだ万博のために大阪湾にもきていたよう)を出迎えて軍人らと話したときに気づいていたことが、さらに鋭く察知されるようになっていたということだろう。エドワーズはこの数週間後にやはりモスクワからの帰途についていたカルロス・プラッツもパリで迎えている。米国から兵器も輸入できなくなっていたチリ軍は次期兵器をソ連から導入することを検討せざるを得なくなっていたようだ。あのままチリが社会主義を続けていれば、キューバの次にミグが飛ぶ国になっていたというわけである。 パリクラブで債権国たちとの最後の交渉を終えた(そしてもはやどうしようもないことが改めて分かった)エドワーズはいよいよ執筆に専念するため休暇申請を友人で同僚でもあったオルランド・レテリエルに提出する。この時期、エドワーズは後にピノチェト政権下で秘密警察に殺害されることになる人物2名とすれ違っていることになる。エリゼ宮での最後の仕事の最中、各国の外交官たちに囲まれながら自分がこれから歩む道(役人ではなくなり、成功もおぼつかない作家になる)を想像して暗澹たる気分になっている。大使館での最後の日、彼は、チリから債務処理のためにやってきた大勢の経済官僚たちを目の当たりにしている。その多くはクーデター後にどうなったかもわからない。シカゴから連れてこられた新しい経済官僚たちが世界に先駆けた新自由主義的経済体制を構築するあいだ、社会主義を目指した旧政権がつくった膨大な債務の後始末に追われていた優秀な連中はどうなってしまったのだろうか。彼はスペインのカラフェルに移り住み、本書の執筆に専念することになる。 <いずれにせよ、1973年の9月11日まで、チリには何も起きないという、他のチリ人と同じ思考が私のなかにも働いていた。カラフェルの静かな海辺で私は毎朝のようにこの本の最終校正をはじめ、ときには夕方の四時か五時まで続けることもあった。そんなある日の午後、目を真ん丸にした娘が駆けつけてきて、途切れがちの声で、バルセロナから電話が来た、チリで革命が起きて飛行機がモネダ宮を爆撃したって、と言うのである。(T., 404)>
カルロス・バラルの自伝では海辺を歩いているとドノソが走ってきた、とあるが、これはエドワーズが娘を介して第一報に触れた後の出来事だったのだろう。エドワーズはアジェンデの自殺説を当初は信じたという。というのは、そこに至るまでの過去数年間、彼は19世紀末のチリ大統領バルマセーダのことを調べることが多く、アジェンデとバルマセーダをよく比較していたからだった。バルマセーダは1891年に内戦を引き起こす事態になった(チリにとってはパシフィコ戦争以上の大事件だったとエドワーズは位置づけているが、それはこの時期にブレイデン・コッパー等、後のチリ資源レントの大半をむしり取っていく外国企業が根付いた時期にも相当するからだ)後にアルゼンチン大使館へ亡命、そこで拳銃自殺している。このあたりにはネルーダの『大いなる歌』にも詳しいが、同じように、国を内戦にも近い緊急事態に導いたアジェンデも自殺したと考えたわけだ。しかし、このエピローグを書いた段階ではその第一印象を修正している。
<いまではむしろ、おそらくアジェンデは機関銃を手に自らの正当性を守り抜き、襲撃者たちによって撃たれて死んだように思われる。軍事評議会が出しているアジェンデの自死を示す証拠はごく脆弱なものだ。彼はこうしてわが国の英雄たちの霊廟にその名を連ねたというわけである。独立戦争で無政府主義者として頭角を現したカウディージョで、アルゼンチンへ渡ろうとしていたときにメンドーサで銃殺されたホセ・ミゲル・カレーラと、ホセ・マヌエル・バルマセーダと肩を並べたのである。三人ともかつての、そして直近のチリにおいて、その政治的リアリズムの欠如を咎められた人物だ。しかしながら、神話と歴史という闇の向こう側で、彼らはみな取り消しようもない業績を成し遂げてもいる。カレーラはチリ初の印刷所と国立高等学校を創設し、奴隷の子孫の解放にも関わった。バルマセーダは外国資本を管理する非常に近代的なアイデアに加えて、数々の公共事業と教育開発にも関わった。アジェンデは、かつては独立国であるにもかかわらず輸出額の70%を米国企業に吸い取られていた銅資源を完全国有化した。(T., 406-407)>
ヨーロッパのマスコミはいずれもヒステリックな論調でチリの事件を糾弾しているとエドワーズは言う。カタルーニャでは地元出身の司祭ジョアン・アルシナが軍部に殺害された事件が大々的に報道されていた。10月。エドワーズのもとへもチリからの知らせが続々と届いてくる。 <著名な共産主義者の技術者が国立スタジアムで撃たれた数日後に病院で死亡していた。別の人物は見せしめのために同じスタジアムで遺体のまま二十四時間放置されていた。私の知り合いの知り合いであるひとりの友人男性は、本当はそうでないのに左翼革命運動の一員とみなされて、義理の母親との食事中に拉致され、その遺体が翌朝現場から数ブロックのところで見つかった。歌手のビクトル・ハラが殺されていた。別の友人は電気技師である夫の息子を探しにモルグへ行き、そこで小さな部屋に積み重なる、死んだばかりの170人分の遺体を目撃していた。知り合いの医者のひとりは警官に殴られていた。アンヘル・パラについては何の情報もなかった。美術評論家で平和的市民の模範、スターリン時代に社会主義リアリズムを敵に回して戦った猛者であるエンリケ・ベジョも逮捕されていた……。(T., 408-409)>
ビオレタ・パラの息子にして歌手のアンヘル・パラは国立スタジアムに拘束後、紆余曲折を経て解放され、その後はメキシコ等へ亡命、2017年まで生きてその歌手人生を全うすることになる。アルゼンチンで『スル』が全盛のころにチリで文芸誌『プロ・アルテ』を主宰していたエンリケ・ベジョのその後はよくわからないのだが、この論考によるとやはり「よくわからない」と言っていて、1974年にベルリンで死んだとだけあるので、亡命するところまでは行ったのだと思う、今度サンティアゴに言ったら人づてに聞いてみよう。 こうして見てくると、外交官としてのエドワーズはアジェンデ政権のやり方にどちらかと言うと批判的で、急進的な左派の言説には辟易しているようだし、そもそも本書自体が反革命キューバの本であるが、作家としてのエドワーズは多くのリベラルな表現者たちと交流があり、この73年の1~2か月で多くの友人たちを失ったことが分かってくる。彼自身のサンティアゴの家の地下室、そこには蔵書が隠してあり、捜査の対象になったが、軍部が間違って二度とも隣家の地下室を強襲したため、ネルーダ等の本も難を逃れたという。近所には裏切り者もいたようだ。
<私も知っている、若いころにはアジェンデに一票を投じたこともある男が、自分の町の左翼を密告しようと身構えていた。奴らに死を!というわけだ。映画作家のパトリシオ・グスマンも近所に住む人々の密告で国立スタジアムに送られた。若いころには作家になりたくて仕方なかったある読書愛好家は、政治的に疑わしいと思われる本を庭で燃やしていた。(T., 409-410)>
そしてパリに住むひとりのチリ人女性の手紙を介して、エドワーズは、ネルーダの遺体が軍部によってすっかり荒されたラ・チャスコーナの家に届けられた顛末と、葬儀の場に集まった人々のあいだから、誰ともなく「同志ネルーダ」と呼びかける声が上がったということを知る。
エドワーズは1972年に帰国したネルーダと二度と会うことはなかった。前に紹介したように、あとは手紙のやり取りだけがあった。73年3月の総選挙、エドワーズがむしろ「終わりの始まり」と考えたあの人民連合の大勝利も、もちろんネルーダは言祝ぐ手紙をエドワーズに寄こしていた。しかし、と、エドワーズは1970年の秋口のことを振り返る。
<しかしまだ戦いが始まる前から、つまり1970年10月のあの昼過ぎに私がサン・クリストバルの丘の麓にある彼の家を訪れたときから、パブロ・ネルーダは、その毛穴とアンテナのすべてを使って、海底深く胎動する破壊的な波を予見していたように見えた。彼は物質の呼吸を、粘土のなめらかな曲面を、板の木目を、庭の動かぬ植物たちの暗い生命を、それらの木々の震えて尖って湿り気を帯びた葉を感じ取り、そして、見たこともない野蛮な力が外部からやってきて、そうして事物や自然の均衡を乱そうとしているという考えにとらわれ、強い、言葉にはできない苦しみを覚えていた。「すべてが真っ黒に見える」と彼が言ったことがある。その数か月後、ハバナを発つ前日にフィデルと革命の困難について語り合っていたとき、私がそのエピソードを彼に紹介すると、フィデルはすぐさま「ネルーダはよくわかっているな」と答えたものだ。(T., 414)>
ここでエドワーズによるネルーダ関係のコメントは終わりである。エピローグの締めは、エドワーズ流の反ロベスピエール主義、すなわち「敵か味方か」という思考法への嫌悪感の表明になっていて、彼の著作を読んできている人間には特に新しいことはない。
今回再読して気付いたことがある。
アジェンデ政権とクーデターについての見解でもう新しいものはないが、今回分かったのは、エドワーズという作家が、二人の父、というより厄介な兄と言ったほうがただしいかもしれない存在として、フィデルとネルーダという、好対照であると同時に、どこか似ている極端な二人を捉えているということだ。エドワーズは外交官として悩めるネルーダの姿を間近で見てきた。逡巡し、自らが同盟者だと感じている政治勢力の勝利にも本心では浮かれるどころか「真っ黒な」未来を予見していた。だが詩人としてのネルーダは彼にとって乗り越え難い存在でもあったろう。外交官ネルーダの姿を同じ外交官として回想することで、と言ってもそれは本書ではなく『さらば詩人』で達成されることになるが、エドワーズは表現者ネルーダに一社会人としての姿を加味し、それを評価するでも批判するでもなく、ただ回想として差し出している。これとはうって変わって、エドワーズのフィデルに対する態度には、完全な批判のなかにもどこか必ず共感めいたものを私は感じる。あくまで私の印象に過ぎないが、エドワーズはネルーダに対してよりフィデルに対して「よりシンパシーを」感じていたように思われる。エドワーズは同じ文学者としてネルーダにはどこか距離を保っていたように見えるが、あからさまに「文学は敵」とみなしてくるフィデルに対しては完全なる外交官として実直に接しているように見える。現にエドワーズはフィデルが自分の父親とよく似ていると書いていた。愛憎半ばする、というのとは一味違う交流がフィデルとのあいだにはあって、それが、本書が革命キューバ批判の本でありつつも、なんだか「フィデル面白エピソード本」化してしまっている大きな要因のひとつであろう。まあ、フィデルという人間が、それだけ面白い人でした、ということなんでしょうけど。
追記:題の「パリのエピローグ」とはパリで書かれたという意味ではなく(カラフェルで書かれているので)、パリの大使館時代のエピソードを追加しました、という意味みたいなので、強いて訳すなら「パリ時代に関するエピローグ」でしょうか。
(了)
 積読状の小説が約30冊ほどあって、ここ数年の怠惰を反省させられるのだが、今夏は引きこもり状態になるので、夕暮れから酒を飲むまでの1時間は必ずこの人たちと付き合うことにしたいと思う。午前中はせいぜい仕事をしたいと思います。思うだけなら誰でもできますけど。
積読状の小説が約30冊ほどあって、ここ数年の怠惰を反省させられるのだが、今夏は引きこもり状態になるので、夕暮れから酒を飲むまでの1時間は必ずこの人たちと付き合うことにしたいと思う。午前中はせいぜい仕事をしたいと思います。思うだけなら誰でもできますけど。 積読状の小説が約30冊ほどあって、ここ数年の怠惰を反省させられるのだが、今夏は引きこもり状態になるので、夕暮れから酒を飲むまでの1時間は必ずこの人たちと付き合うことにしたいと思う。午前中はせいぜい仕事をしたいと思います。思うだけなら誰でもできますけど。
積読状の小説が約30冊ほどあって、ここ数年の怠惰を反省させられるのだが、今夏は引きこもり状態になるので、夕暮れから酒を飲むまでの1時間は必ずこの人たちと付き合うことにしたいと思う。午前中はせいぜい仕事をしたいと思います。思うだけなら誰でもできますけど。 刊行されたときには著者とその近い知人も含めて少数の人が手に取ることはあっても、その後は歴史の闇に埋もれてゆき、日本だったら残るのは国立図書館のデータとISBNだけという風にして消えていく本が世の中にはたくさんある。私のような学者がなんとか書いたほとんど自費出版に近い本もそれに該当するかもしれないし、ましてや私がしてきた海外詩の翻訳本などは「もうすでに消えている」と言っても過言ではない。
刊行されたときには著者とその近い知人も含めて少数の人が手に取ることはあっても、その後は歴史の闇に埋もれてゆき、日本だったら残るのは国立図書館のデータとISBNだけという風にして消えていく本が世の中にはたくさんある。私のような学者がなんとか書いたほとんど自費出版に近い本もそれに該当するかもしれないし、ましてや私がしてきた海外詩の翻訳本などは「もうすでに消えている」と言っても過言ではない。 テキストクリティックを行なっているカテドラ版(2016)のイントロに基づいてこの奇妙な本の変遷を簡単にまとめてみると、まず1973年に初版がバラル・エディトーレスから刊行された。同じ年に第二版が刊行されているが実質二刷でリタッチはなし。翌74年の第三版も同様で、これの現物が国内では京都外国語大学にあるようだ。翌75年にはグリハルボから新版が出ている。ちなみにキューバとチリではそれぞれ違う理由から発禁処分となっていて、チリでは粗悪な海賊版も出回っていたという。私はこれらの現物を実は見ていない。それが実は大問題なのだが、あとで説明するとして、ここまでは実質すべて「初版」と考えていいようだ。
テキストクリティックを行なっているカテドラ版(2016)のイントロに基づいてこの奇妙な本の変遷を簡単にまとめてみると、まず1973年に初版がバラル・エディトーレスから刊行された。同じ年に第二版が刊行されているが実質二刷でリタッチはなし。翌74年の第三版も同様で、これの現物が国内では京都外国語大学にあるようだ。翌75年にはグリハルボから新版が出ている。ちなみにキューバとチリではそれぞれ違う理由から発禁処分となっていて、チリでは粗悪な海賊版も出回っていたという。私はこれらの現物を実は見ていない。それが実は大問題なのだが、あとで説明するとして、ここまでは実質すべて「初版」と考えていいようだ。
 南米のアルゼンチンかウルグアイと思しき(スペイン語の特徴で分かる)どこかの港湾都市。作者情報があれば明らかにモンテビデオだと思われるのだが、最後まで特定されることはない。ある日、大きな湾のような川に大量の魚が浮く。魚の死骸は来る日も来る日も浮かび、やがて川面には誰も見たことがないようなピンク色の汚泥が浮かぶようになる。それが風にあおられて赤い風となって街に吹き寄せる。やがて鳥が消えた。このころから街では奇妙な伝染病が広がりだす。余裕のある市民は街の郊外へと郊外へと非難するようになり、やがて隔離された街には郊外へ行けなかった人たちだけが取り残されるようになった……。
南米のアルゼンチンかウルグアイと思しき(スペイン語の特徴で分かる)どこかの港湾都市。作者情報があれば明らかにモンテビデオだと思われるのだが、最後まで特定されることはない。ある日、大きな湾のような川に大量の魚が浮く。魚の死骸は来る日も来る日も浮かび、やがて川面には誰も見たことがないようなピンク色の汚泥が浮かぶようになる。それが風にあおられて赤い風となって街に吹き寄せる。やがて鳥が消えた。このころから街では奇妙な伝染病が広がりだす。余裕のある市民は街の郊外へと郊外へと非難するようになり、やがて隔離された街には郊外へ行けなかった人たちだけが取り残されるようになった……。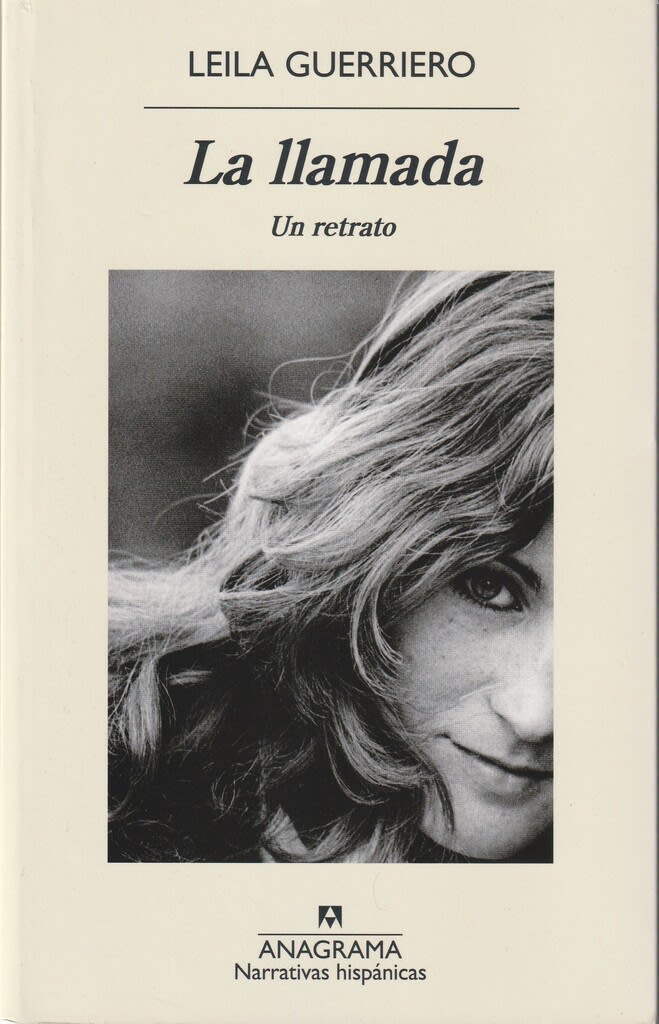 レイラ・ゲリエーロはアルゼンチンの現代作家、どちらかというとジャーナリストと呼ばれがちで文学のカテゴリーに入れてもらえていない印象がある。日本では「ライター」という言葉でくくられている物書きたちに近い立ち位置であろうか。雑誌などに書いた記事をまとめた本も数冊あり、ラテンアメリカの実在した作家や犯罪者の伝記を様々な現役作家に書かせたのを編集した本や、キューバ内外の作家による旅行記をまとめた『岐路に立つキューバ』などもある多彩な人だが、少し長めの伝記ものは2006年のクロニカ、記録として題された『世界の果ての自殺者たち-パタゴニアのある村の記録-』以降、出版サイドからは常に小説であるかのように発表されてきた。最新作で、エルパイス紙で去年の本1位に選出された本書もアナグラマの白いシリーズなので、いちおう小説という建付けである。
レイラ・ゲリエーロはアルゼンチンの現代作家、どちらかというとジャーナリストと呼ばれがちで文学のカテゴリーに入れてもらえていない印象がある。日本では「ライター」という言葉でくくられている物書きたちに近い立ち位置であろうか。雑誌などに書いた記事をまとめた本も数冊あり、ラテンアメリカの実在した作家や犯罪者の伝記を様々な現役作家に書かせたのを編集した本や、キューバ内外の作家による旅行記をまとめた『岐路に立つキューバ』などもある多彩な人だが、少し長めの伝記ものは2006年のクロニカ、記録として題された『世界の果ての自殺者たち-パタゴニアのある村の記録-』以降、出版サイドからは常に小説であるかのように発表されてきた。最新作で、エルパイス紙で去年の本1位に選出された本書もアナグラマの白いシリーズなので、いちおう小説という建付けである。