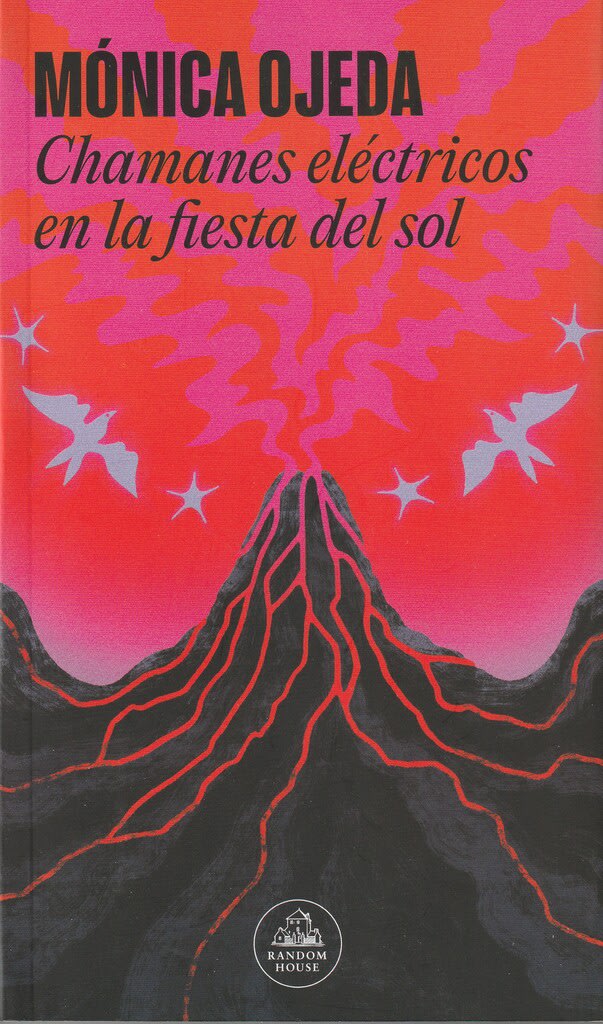
モニカ・オヘーダは1988年生まれのエクアドル作家。現代翻訳文学未踏の地と言ってもいい国で、私たちが目を通す文学史の類でもホルヘ・イカサという20世紀の先住民主義小説の嚆矢くらいしか記憶になく、いわば完全なる空白地帯になっているが、近年はこのオヘーダを中心としたグアヤキル出身の女性作家の活躍が目立つというところまでは情報として把握している。
エクアドルはその名の通り赤道直下の国だが、熱帯性気候なのはグアヤキルなどの太平洋岸だけで、首都キトやその背後にあるアンデス山脈はもちろん高地、しかもコトパクシなど活火山が数多くある火山国である。人種構成はペルーとよく似た混血文化で、グアヤキルは黒人もいてコロンビアのカリブ地域の色を備えた開けた文化の地。
オヘーダはこれまでに長編小説を三つ出していて、うちの一種の学園ものといえる作風の『顎』がスペイン語圏では話題になり、これは英訳も刊行された。詩集に加えて短篇集『空を飛ぶ女たち』も出していて、現役世代としては、私が関わった作家でいうとメキシコの(+米国の)バレリア・ルイセリやチリのパウリーナ・フローレスらと同じ世代にあたる。
本書は四作目の長編小説で、風変わりな題名が示すようにエクアドルのアンデス山中で開催されたインティ・ライミを思わせる複合音楽フェスティバルを背景に、そこへ向かうノエという少女の物語を、彼女に同行することになった男女、グアヤキルからの親友ニコル、内気なマリオ、音楽にマニアックなペドロ、容姿にコンプレックスを持つパメラという四人のティーンエイジャーが交互に語り手となって紡いでいく。というよりそれが1・3・5・7の奇数部の構成で、あいだにフェスで歌われていると思しき歌が混じったりして、このカントーラ(歌い手)たちのよるコーラスは古典劇の作法を思わせる。
いっぽう2・4・6の偶数章は幼いころのノエを捨てて山中の森に暮らすようになった音楽家の父エルネストの手記という形をとり、娘のことより飼い犬サンソンのことばかり気にかけているこの愚かなのか賢いのか分からない「人外魔境に旅立った」男の手記がほとんど詩なので、読んでいて面白い。<はじめに言葉ありき、言葉は父にして、父は言葉であった(99)>といういかにもキリスト教的でマッチョな言葉で始まるエルネストの手記は、ヤチャクと呼ばれるシャーマンたちとの出会いによって徐々にアンデスという女性的地母神の世界へと引き寄せられてゆく。
背景にあるのはこちらでも報道されるようになったエクアドル都市部での治安悪化で、メキシコやコロンビアのカルテルがこの国に拠点を移したことで殺人件数が飛躍的に増加、若者にとって都市が極めて危険な環境になったことがあるらしく、四人の言葉やエルネストの手記からアンデスの森に隠遁した人々の存在が浮かび上がってくる。相次ぐ火山の爆発や地震国としての背景も見えてくる。いろいろなものが爆発寸前になっているところで、四人がアンデスのフェスを目指しているという設定だ。
ひとりの少女の成長譚、というのはなにも珍しい物語ではなく、それについてはイサベル・アジェンデのような先達もいるし、さらにその先達も探せば見つかるだろうが、この小説はそこに音楽やアンデスの土着文化とエクアドルの現在情勢なども絡めてしかも構成が多声的、単純な女ビルドゥングスロマンになっていないどころか、一読した限りでは「いったいこの小説は何を語っていたんだ?」とすら思わせるカオスが逆に魅力となっていると言えようか。
もう少し他の作家も見なければならないが、現代エクアドル文学、できれば死ぬまでに1冊くらいは翻訳紹介してみたいものです。












 メキシコの忘れられた画家マルティン・ラミレス(Martín Ramírez)。1925年に米国へ越境、職を転々とするが29年の恐慌で行き場を失う。家族を残してきたハリスコ州はクリステロスの乱という紛争によって大混乱に陥っていた。マルティンは分裂病を発症し入院、その後、治療の一環として描き始めた絵が米国内で評判を呼ぶ。本人はメキシコに残る家族に会うこともないまま肺がんで死亡した。
メキシコの忘れられた画家マルティン・ラミレス(Martín Ramírez)。1925年に米国へ越境、職を転々とするが29年の恐慌で行き場を失う。家族を残してきたハリスコ州はクリステロスの乱という紛争によって大混乱に陥っていた。マルティンは分裂病を発症し入院、その後、治療の一環として描き始めた絵が米国内で評判を呼ぶ。本人はメキシコに残る家族に会うこともないまま肺がんで死亡した。



