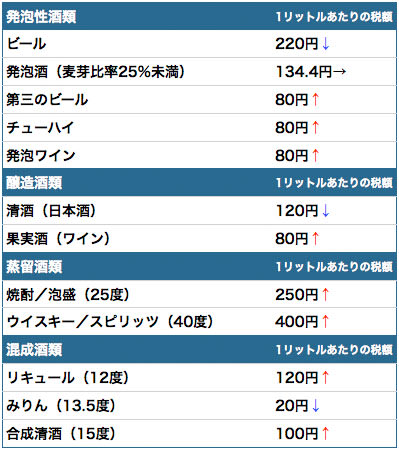先日に当ブログ「泡盛なかゆくい」が1周年を迎えたことに関連して、ここまで書いた記事を書籍化しようと思っています。幸いにして、本業でDTPアプリケーションを使いこなしたりしていますので、Adobe InDesignでレイアウトして、PDF/X-1aで印刷・製本するところまで、きちんとやりたいと思っています。大きさは新書サイズ。索引なども付けて、だいたい200ページぐらいになることが予想されています。グレースケールですが写真も入るので、わりと本格的なものになるだろうと思っています。
そして、きちんとした印刷所で刷ろうと思っていますが、問題は何冊つくるか?です。
もちろん最終コストにも依りますが、50冊だと寂しい気もするし、100冊作ってもきっと処分に困るよなーと思ったり。そこでみなさんにお尋ねします。オンラインで読めるこのブログが新書になったとして、多少の出費が発生するとしても「ぜひ手元に欲しい」という方はいらっしゃるものでしょうか。私的にはこれで儲けるつもりもないですし、自力で入稿データを作れる状況にあるので単純に自分が書いたものを手元に残しておきたい、というそれだけなのですが、もしこんなブログでも新書で持っておきたいと思われる方がいたら、まとめて刷ってしまおうかなと。
「出費額にも依るけど、現時点では欲しいかも!」という方は、この記事にコメントしていただけませんか?
私のメールアドレスをご存じの方は、直接メールをくださっても結構です。
本業その他の合間をぬってのDTP作業はちょっと時間がかかると思いますので、入稿データが完成する頃に集計して印刷部数の目安にしたいと思います。もちろん、そのときになって「やっぱりいらない」とお断りいただくのもアリということで。
こういう記事を書いて、結果としてコメントゼロだったらどうするつもりなんでしょうか?
まあ、それはそのときに考えることにしますね(笑)
そして、きちんとした印刷所で刷ろうと思っていますが、問題は何冊つくるか?です。
もちろん最終コストにも依りますが、50冊だと寂しい気もするし、100冊作ってもきっと処分に困るよなーと思ったり。そこでみなさんにお尋ねします。オンラインで読めるこのブログが新書になったとして、多少の出費が発生するとしても「ぜひ手元に欲しい」という方はいらっしゃるものでしょうか。私的にはこれで儲けるつもりもないですし、自力で入稿データを作れる状況にあるので単純に自分が書いたものを手元に残しておきたい、というそれだけなのですが、もしこんなブログでも新書で持っておきたいと思われる方がいたら、まとめて刷ってしまおうかなと。
「出費額にも依るけど、現時点では欲しいかも!」という方は、この記事にコメントしていただけませんか?
私のメールアドレスをご存じの方は、直接メールをくださっても結構です。
本業その他の合間をぬってのDTP作業はちょっと時間がかかると思いますので、入稿データが完成する頃に集計して印刷部数の目安にしたいと思います。もちろん、そのときになって「やっぱりいらない」とお断りいただくのもアリということで。
こういう記事を書いて、結果としてコメントゼロだったらどうするつもりなんでしょうか?
まあ、それはそのときに考えることにしますね(笑)