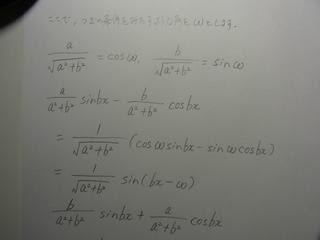前回の最後の部分の引用、
“a city and a tower, whose top may reach unto heaven” と、
“nothing will be restreined from them, which they have imagined to do.”
は、「創世記 第11章」からの、それだ。
『THE TRUE BELIEVER』の冒頭には、パスカルの『パンセ』とともに、「創世記」の “And slime had they for mortar.” の一行が引用されている。
その説明の前に、著者である「エリック・ホッファー」を紹介しておこう。
私の手元にある、「HARPER PERENNIAL MODERN CLASSICS」の版には、こう書かれている。
ERIC HOFFER (1902-1983) was self-educated and lived the life of a drifter through the 1930s. After Pearl Harbor, he worked as a longshreman in San Francisco for
twenty-five years. He is the author of ten books, including The Passionate State of Mind, The Ordeal of Change, and The Temper of Our Time. He was awarded the Presidential
Medal of Freedom in 1983 and died later that year.
さて、承前の “And slime had they for mortar.” であるが、『聖書』の原文は、旧約のほとんどがヘブライ語で、新約はギリシア語だ。「創世記」は旧約の冒頭にあるので、ヘブライ語だ。引用されたその一文の日本語は、“彼らはしっくいの代わりにアスファルトを用いた” と、新共同訳ではなっている。
アスファルト! である。私が子供だった頃はまだ、砂利道がのこっていたが、かの地ではもう、創世記の時代からアスファルト道路になっていたのか、と思ってしまうが、道ではなく、塔に使ったのである。あの「バベルの塔」だ。後でこの話は、もう少し全体がわかるように載録するが、ここで問題にしたいのは、英語の“slime” である。
「slime」
①どろどろ〔ねばねば, ぬるぬる〕したもの, 粘着物, 軟泥, 泥砂, ヘドロ;
〔しばしば複数形で〕岩石の粉, スライム;
《カタツムリ・魚などの》粘液, のろ;
《変性したハムなどに生じる》ねと.
②いやなもの, 悪臭のあるもの;
《俗語》悪の世界, 暗黒街;
《口語》げす根性, おべんちゃら;
《俗語》不名誉な事態, 腐敗;
《俗語》いやなやつ, げす.
例によって、『リーダーズ英和辞典 第3版』で引いたが、この辞典の「英語の意味に肉薄」しようとする恐ろしいまでの意思は、この一語だけでもよくわかる。
「slime」には、(軟泥や、岩石の粉がやや近いが)「アスファルト」という意味はない。
ヘブライ語の原文は、もちろん私はわからないが、英訳の「slime」のほうが、原意に近いのではないかと思う。
なぜなら、「バベルの塔」の文意は、肯定的なものではないからだ。
そして、ホッファーが冒頭に置いたこの語で提示、暗示したかった意味もわかる。
それは断然、「アスファルト」のイメージとは、違う。
「創世記 第11章(バベルの塔)」 新共同訳
世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。
東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。
彼らは、「れんがを作り、それをよく焼こう」と話し合った。石の代わりにれんがを、しっくいの代わりにアスファルトを用いた。彼らは、「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」と言った。
主は降って(くだって)来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て、
言われた。「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない。
我々は降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。」
主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱(バラル)させ、また、主がそこから彼らを全地に散らされたからである。
ここまで写してみたら、3行目からの「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。」という訳は、英訳の “a city and a tower, whose top may reach unto heaven” に比べると、意味が少し通らない気がする。しかし私はヘブライ語が読めないのだから、仕方ない。
「ひとつの都市とひとつの塔、その(塔の)いただきが天に届くように」 (石川八十一 英訳からの重訳)
次回は、もうひとつ『THE TRUE BELIEVER 』冒頭へ引用された文章、パスカルの『パンセ』についてを、すこし書く。
“a city and a tower, whose top may reach unto heaven” と、
“nothing will be restreined from them, which they have imagined to do.”
は、「創世記 第11章」からの、それだ。
『THE TRUE BELIEVER』の冒頭には、パスカルの『パンセ』とともに、「創世記」の “And slime had they for mortar.” の一行が引用されている。
その説明の前に、著者である「エリック・ホッファー」を紹介しておこう。
私の手元にある、「HARPER PERENNIAL MODERN CLASSICS」の版には、こう書かれている。
ERIC HOFFER (1902-1983) was self-educated and lived the life of a drifter through the 1930s. After Pearl Harbor, he worked as a longshreman in San Francisco for
twenty-five years. He is the author of ten books, including The Passionate State of Mind, The Ordeal of Change, and The Temper of Our Time. He was awarded the Presidential
Medal of Freedom in 1983 and died later that year.
さて、承前の “And slime had they for mortar.” であるが、『聖書』の原文は、旧約のほとんどがヘブライ語で、新約はギリシア語だ。「創世記」は旧約の冒頭にあるので、ヘブライ語だ。引用されたその一文の日本語は、“彼らはしっくいの代わりにアスファルトを用いた” と、新共同訳ではなっている。
アスファルト! である。私が子供だった頃はまだ、砂利道がのこっていたが、かの地ではもう、創世記の時代からアスファルト道路になっていたのか、と思ってしまうが、道ではなく、塔に使ったのである。あの「バベルの塔」だ。後でこの話は、もう少し全体がわかるように載録するが、ここで問題にしたいのは、英語の“slime” である。
「slime」
①どろどろ〔ねばねば, ぬるぬる〕したもの, 粘着物, 軟泥, 泥砂, ヘドロ;
〔しばしば複数形で〕岩石の粉, スライム;
《カタツムリ・魚などの》粘液, のろ;
《変性したハムなどに生じる》ねと.
②いやなもの, 悪臭のあるもの;
《俗語》悪の世界, 暗黒街;
《口語》げす根性, おべんちゃら;
《俗語》不名誉な事態, 腐敗;
《俗語》いやなやつ, げす.
例によって、『リーダーズ英和辞典 第3版』で引いたが、この辞典の「英語の意味に肉薄」しようとする恐ろしいまでの意思は、この一語だけでもよくわかる。
「slime」には、(軟泥や、岩石の粉がやや近いが)「アスファルト」という意味はない。
ヘブライ語の原文は、もちろん私はわからないが、英訳の「slime」のほうが、原意に近いのではないかと思う。
なぜなら、「バベルの塔」の文意は、肯定的なものではないからだ。
そして、ホッファーが冒頭に置いたこの語で提示、暗示したかった意味もわかる。
それは断然、「アスファルト」のイメージとは、違う。
「創世記 第11章(バベルの塔)」 新共同訳
世界中は同じ言葉を使って、同じように話していた。
東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。
彼らは、「れんがを作り、それをよく焼こう」と話し合った。石の代わりにれんがを、しっくいの代わりにアスファルトを用いた。彼らは、「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしよう」と言った。
主は降って(くだって)来て、人の子らが建てた、塔のあるこの町を見て、
言われた。「彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは、彼らが何を企てても、妨げることはできない。
我々は降って行って、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。」
主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱(バラル)させ、また、主がそこから彼らを全地に散らされたからである。
ここまで写してみたら、3行目からの「さあ、天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。」という訳は、英訳の “a city and a tower, whose top may reach unto heaven” に比べると、意味が少し通らない気がする。しかし私はヘブライ語が読めないのだから、仕方ない。
「ひとつの都市とひとつの塔、その(塔の)いただきが天に届くように」 (石川八十一 英訳からの重訳)
次回は、もうひとつ『THE TRUE BELIEVER 』冒頭へ引用された文章、パスカルの『パンセ』についてを、すこし書く。