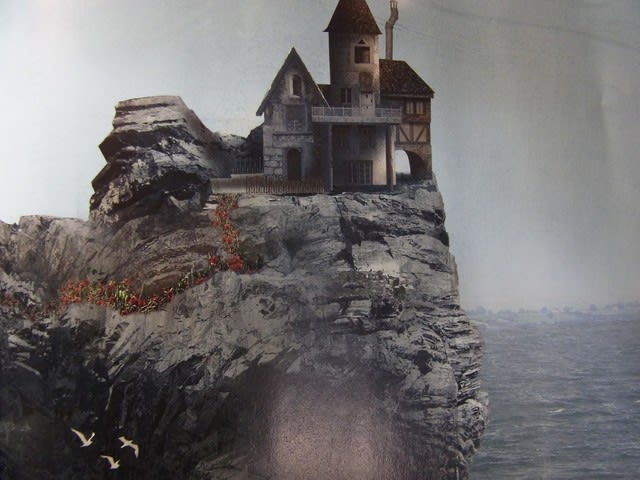【現在の改憲論議の概要】
〔イ〕 与党が考える改憲案
〔ロ〕 現行憲法の精神を守るための改憲案
〔ハ〕 現行憲法を守るという考え方
現在の改憲論議を大きく分けると以上の三つになる。
〔イ〕の与党が考える改憲案は、簡単に言うと、現行憲法の持つ三大原則(国民主権,基本的人権の尊重,平和主義)を後退させるためものだ。嘘だと思う方は、自民党の「日本国憲法改正草案」を読んで、ご自身で判断してほしい。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf
〔ロ〕の現行憲法の精神を守るための改憲案はいろいろあるが、ここでは、最近目にした「山尾案」を紹介しておく。
〔ハ〕の現行憲法を守るという考え方の代表としては、このツイートを埋め込んでおく。
まず与党の〔イ〕案は、国民の権利を縮小させるためのものだから、普通に考えると、国民の側から「我々の権利が多すぎるからそれを少しでも削ってくれ!」というようなデモが起こる可能性はほとんどない。そこで「隣国の脅威」や「不当に得をしている者」などへ“注意を別のところに向けさせることはできる。”『バーニー・サンダース自伝 (p.217)』
議論の傾向として、〔イ〕は〔ハ〕を、「非現実的」,「お花畑」とみなすことが多い。不思議なことに、本来は手を結べるはずの〔ロ〕も〔ハ〕に対して同様の言葉を向けることが少なからずある。〔イ〕も〔ロ〕も〔ハ〕も、言論は自由であるからどんどんそれぞれの議論を深めるべきであるが、相手を攻撃して相対的な優劣を競うのはあまり意味がないので、それはお互いに控えたほうが冷静な論議になるだろう。
この〔イ〕〔ロ〕〔ハ〕のなかで、私が賛同する考えは、ここまで「1946年の精神」に書いてきたように〔ハ〕である。この「71年間」への評価は、例えば〔イ〕で示した改憲草案の委員に名を連ねていない、引退された谷垣 禎一氏等とも一部共有できるのではないかと思っている。

“次の戦争が起こったら、遺体袋に入って帰ってくるのは誰か?(p.230)”
“民主主義社会の選挙運動は、多大な教育的側面を持つべきだ。(p.235)”
“私はネガティブ宣伝を放送したことは一度もない。(p.321)”
“誤解を招く宣伝は放置してはならない。(p.322)”
“投票に意味があると思えば、貧困層は投票する。(p.229)”
“政治の世界では、学びつづけないとどんどん不利になる。(p.180)”
〔イ〕 与党が考える改憲案
〔ロ〕 現行憲法の精神を守るための改憲案
〔ハ〕 現行憲法を守るという考え方
現在の改憲論議を大きく分けると以上の三つになる。
〔イ〕の与党が考える改憲案は、簡単に言うと、現行憲法の持つ三大原則(国民主権,基本的人権の尊重,平和主義)を後退させるためものだ。嘘だと思う方は、自民党の「日本国憲法改正草案」を読んで、ご自身で判断してほしい。
https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf
〔ロ〕の現行憲法の精神を守るための改憲案はいろいろあるが、ここでは、最近目にした「山尾案」を紹介しておく。
真っ当な論、有能な政治家であると思う山尾志桜里議員「自衛権に歯止めかける改憲を」 立憲的手法で“透明人間”を縛る https://t.co/DF76pZymiO
— さとう まさのり (@satoh_masanori) 22 November 2017
〔ハ〕の現行憲法を守るという考え方の代表としては、このツイートを埋め込んでおく。
安倍政権の「憲法クーデター」を許すな福島瑞穂・社会民主党副党首に聞くhttps://t.co/V2nUaQAQu4
— 社民党OfficialTweet (@SDPJapan) 20 November 2017
まず与党の〔イ〕案は、国民の権利を縮小させるためのものだから、普通に考えると、国民の側から「我々の権利が多すぎるからそれを少しでも削ってくれ!」というようなデモが起こる可能性はほとんどない。そこで「隣国の脅威」や「不当に得をしている者」などへ“注意を別のところに向けさせることはできる。”『バーニー・サンダース自伝 (p.217)』
議論の傾向として、〔イ〕は〔ハ〕を、「非現実的」,「お花畑」とみなすことが多い。不思議なことに、本来は手を結べるはずの〔ロ〕も〔ハ〕に対して同様の言葉を向けることが少なからずある。〔イ〕も〔ロ〕も〔ハ〕も、言論は自由であるからどんどんそれぞれの議論を深めるべきであるが、相手を攻撃して相対的な優劣を競うのはあまり意味がないので、それはお互いに控えたほうが冷静な論議になるだろう。
この〔イ〕〔ロ〕〔ハ〕のなかで、私が賛同する考えは、ここまで「1946年の精神」に書いてきたように〔ハ〕である。この「71年間」への評価は、例えば〔イ〕で示した改憲草案の委員に名を連ねていない、引退された谷垣 禎一氏等とも一部共有できるのではないかと思っている。

“次の戦争が起こったら、遺体袋に入って帰ってくるのは誰か?(p.230)”
“民主主義社会の選挙運動は、多大な教育的側面を持つべきだ。(p.235)”
“私はネガティブ宣伝を放送したことは一度もない。(p.321)”
“誤解を招く宣伝は放置してはならない。(p.322)”
“投票に意味があると思えば、貧困層は投票する。(p.229)”
“政治の世界では、学びつづけないとどんどん不利になる。(p.180)”