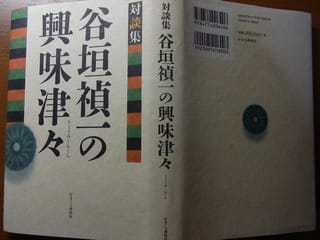ミシェル・オバマ米国大統領夫人が先月投稿されたツイートである。
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
ミラノ万博へ訪れた際、その近くにある寺に、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』の壁画を観に行かれたそうだ。
私はこの絵について何か書いてあるかもしれないと思い、『イタリア古寺巡礼』を読んでみた。

『イタリア古寺巡礼』は1950年に刊行された本だが、その基になったのは、著者の1927~28年にかけてのイタリア旅行中、家族へ宛てた手紙である。
1927~28年といえば昭和2~3年で、対外的に強硬な田中義一内閣の時代であり、昭和3年には関東軍が張作霖を爆殺した「満州某重大事件」も発生しており、その数年前の1925年には「治安維持法」も成立している。
こういう時代状況のなかで、のんびりとイタリアをひとめぐりして美術を観てまわっているのは不思議な気もするが、これは山田監督が『小さいおうち』で描いたように、時代が戦争へと傾くなかで、あらゆる文化が奇妙に興隆した時でもあったのだ。
フィレンツェで和辻はこう書いている。
“午食後町へ出ると、ファシストの少年隊が黒シャツのそろえで行進して行く。何事かと思って見ていると、やがて中学生くらいの年輩の青年隊が続いてくる。皆楽隊を先に立てている。それでもまだ気づかずに、寺を一つ見物してからこの広場に出たのであるが、見ると警官が四方を固めて普通人を中へ入れない。そこへいろいろな職業組合の連中が、旗を先立ててのり込んでくる。ファシストの武装隊が銃を持ってやってくる。いずれも青年と老人の入り混じったものである。ことに驚いたのは、職業組合の労働者らしいのが、あとからあとからいくつでも旗を立てて乗り込んでくることであった。二時間近く見物していた間じゅう、それが続いた。イタリア人は祭り好きのせいでこういうことをやるのでもあろうが、しかしそれにしてもファシズムがこんなに繁昌(はんじょう)していようとは、全く案外であった。見ていて一番かわいらしかったのは少年隊である。白い上衣の女の先生が引率していて、幼稚園くらいの小さい子供たちが、いかにも楽しそうに、ファッーーショ、ファッーーショという号令に合わせて歩調を取っていた。教育が根本だというところへ、ムッソリーニは眼をつけているらしい。”
わずか10数年後のイタリア王国と大日本帝国の結末を知る我々から見ると、いかにものんびりとした観察のようにも思える。同時期の日本には、石橋湛山のように未来が見えて警告を発する言論人もいたが、大半の「文化人」たちは和辻のように時代の波に流されていった。
 この本の目次を見た時ミラノがないのでおかしいと思ったのだが、読んでみたら、ちょうどミラノで病気になってしまい『最後の晩餐』はよく観ていないということだった(笑)。
この本の目次を見た時ミラノがないのでおかしいと思ったのだが、読んでみたら、ちょうどミラノで病気になってしまい『最後の晩餐』はよく観ていないということだった(笑)。