
前回の神代文字繋がりで、もうずいぶん前の話しですが巨石や神社、縄文遺跡探訪などで気の合う同じ趣味を持つメンバーたちと多摩地域の神社巡りをした際に訪れたのが阿伎留神社(東京都あきる野市五日市)でした。


阿伎留神社
☞関連記事:祭神など以下の過去記事参照
その時にいろいろご案内をして頂いた宮司さんにわざわざ貴重な版木から刷って頂戴したのが阿伎留神社に伝わる「神字歌」の写しでした。


阿伎留神社に伝わる「神字歌」の写し(転載厳禁)とその版木
いわゆる「神代文字」で書かれている貴重なもので、字体は「阿比留文字(草書体)」と言われているものです。(一部変異体文字もあり)
この「神字歌」の出所は、境外末社の琴平神社に伝わっていたものなのだそうです。
以前この神字歌の解読を自分なりに試みてみましたが「武勇の神」である「八千戈神」から『矛で大地を削ったら大地が轟き一つの海が出来た』国生み神話のように感じたのですが、神社側も特に言及されておらず自分もそのままお蔵入りしておりました。
ところが、たまたま覗いた古本屋で「地球ロマン復刊5号 総特集神字大全/絃映社(1977)」を入手して驚きの記事を発見!!

地球ロマン/絃映社 1976~1977頃まで刊行されていた異端偽史・空飛ぶ円盤・偽天皇・秘教・神代文字・綺想科学分野を嚮導する垂涎雑誌でした。琴線を刺激させてくれるマニアックな内容でバックナンバーが欲しいところです。

この巻頭記事になんと!「阿伎留神社神字歌考」として解析内容が掲載されていたのです。
解析の結果は要約して文末に記しますが、興味深いのが阿伎留神社には、夷丘(ヒナオカ)という場所から出土した銅板に阿比留草文字で印刻されたヒフミ歌が、かつて存在していたそうです。

文字種: 阿比留草書体系列文字 一部変体あり
名 称: 「夷丘(ヒナヲカ)銅鍥古字」「阿伎留文字」
出 所: 武蔵国畔切(アキルノ)神社(延喜式では阿伎留神社と記帳)所蔵
・慶長八年夷丘より出土 銅版に印刻されたヒフミ四十七音字
・現在は、天保元年火災により紛失
・初掲載 『文字考』落合直澄
【考察】
夷丘というのは、阿伎留神社の旧跡があった場所と言った情報がありましたが具体的な場所までは、特定出来ませんでした。(境外末社の琴平神社という説もあり)ただ、現在も阿伎留神社の崇敬者たちで構成される講の名称が「夷丘講」と、呼ばれている事から特定の地域ではないのかも知れません。
近代の神代文字研究家「吾郷清彦」氏によればアヒルクサモジは各所より見出されており、『日文伝』や『古字考』その他に多数記載されているが、この銅鍥古字ほど古雅荘重、天衣無縫にして、神韻緲恾たるものを見ない。けだし神人の作品にして、古今独歩の絶品である。形体美の完璧、流麗にして枯淡なること、まさに古代和字中唯一無双というべく、格調高く、全く他の追従を許さないものがある。と、大絶賛されています。
(以上 日本神代文字研究原点 愛蔵保存版 吾郷清彦著 新人物往来社 1996年)
文字種は、一見して阿比留文字草書体ですが全体的に太くて印刻しやすいよう一筆書きになっています。最も類似している出雲文字と比較しても全く異なる部分があるため「阿伎留文字」として別に分類されています。

この文字種は、意外と目にしており字体自身が栄えるのか前述の「日本神代文字研究原点」のケースカバーのデザインや関連書籍でも良くみかけます。
【神字歌解析結果】
(読み下し文)
第一首:稲倉戸(きつみと)ゆ 比蚕倉(このおこくら)は八千矛(やちほこ)が(カ)鉾(ほこ)の穂先(ホサキ)で(て) 突(つ)きつさ統(す)べ(へ)む
第二首:比蚕(このおこ)は 直虫(たたむし)ならす大麻豆乃(おほまつの)神(かみ)の産(う)みます 神(かみ)の蚕(おこ)なり
注釈:キツミ=キスミ 古語で蔵(キス)める 収蔵庫のたぐいをさす。 八千矛=大国主の別名。オコ=蚕。すべむ=方法、手段。 タタムシ=ただの虫けら。 大麻豆乃神=吉凶を占う太占を司る神。
宮司さん曰く何でもこの神字歌は「御守り」として配布されていたんだそうで、読み下し文から「養蚕神」と密接に関わっていた事は理解に難しくはありません。
出元の琴平神社のあきる野市一帯の地域もかつて養蚕業が盛んだった地域で八王子から奥多摩に鎮座する神社には必ずと言ってもいいほど「蚕神」を祀る石碑や祠を見かけます。
琴平神社と言うと海に関連する神社と思いがちですが、なぜ海からほど遠い山中にも琴平神社が鎮座していて養蚕の神様を祀っているのでしょうか?
そこで、ChatGTPに聞いてみました。
金毘羅さんと養蚕の関係は、特に江戸時代に顕著です。香川県は養蚕業が盛んで、蚕の生育に必要な天候や環境が金毘羅宮の祈願と結びついていました。多くの蚕業者が金毘羅宮に祈願し、蚕の繁栄を願っていたと言われています。また、金毘羅宮には「蚕の神様」として、蚕にまつわる神事も行われていたことから、養蚕業と神社の信仰が深く関連していたことが伺えます。養蚕業は、日本の農村経済において非常に重要な産業であったため、金毘羅宮への参拝も業務の一環として行われたと考えられます。つまり、金毘羅さんは、航海安全の神様としてだけでなく、養蚕業の繁栄を祈る場所としても多くの人々に信仰されていたのです。
なるほど。そういえば、海のない我が山梨にも琴平神社が数社鎮座していて、不思議に思っていたのですが由緒に機織の神様をお祀りすると言った記述もありこれで、謎が解けました。




















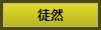



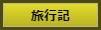
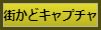

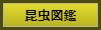


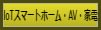

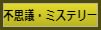
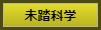
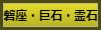


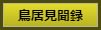
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます