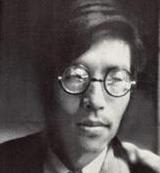興味のあるなしに関わらず目にし、耳にしているでしょうから、その内容は説明するまでもないかもしれませんが、この物語は、大変なイケメンで才能もあり身分も高い貴族・光源氏の誕生から死、そしてその後の子孫の生活までを、54の小物語(五四帖)にわけて描いた世界最初の連作長編小説です。
渋谷区でも、商工会館にて、東洋大学名誉教授 神作光一氏による古典文学講座として、源氏物語読解が行われていました。(“『宇治十帖』を読む〜「四十九帖 宿木」「五十帖 東屋」~” 2011年の6/17~9/30までの間に全12回行われていました。)
「源氏物語は、その時代の人間の生や死に関わる様々な感動や思考、あるいは憧憬や苦悩、喜怒哀楽といったことがらが描かれており、平安時代に誕生してから、時を超えて現代でも多くの人々に愛され続けています。」これは講座案内のチラシの文句。
『源氏物語』は多くの読者から愛されるがゆえに、様々なアーティストたちにより映画化・コミカライズされてきました。
最近ではジャニーズJr.の生田斗真くんが主演で映画化(映画「源氏物語~千年の謎~」2011年12月10日公開、鶴橋康夫監督)の話もありますね。
コミカライズでは、中でも原文に忠実な大和和紀先生の『あさきゆめみし』があまりにも有名ですが、2005年の時点では13巻で1600万部も売れているとのこと。さらにこの漫画は、すでに英語版だけでなくドイツ語、中国語訳も存在しています。
この物語に大きく魂を揺さぶられているのは、決して日本人だけではないのです。

(画像はlivedoor Booksよりお借りしました)
ということで!
今回わたしが紹介するのは、『源氏物語』に感銘を受けた外国人作家の作品たちです。
そもそも『源氏物語』が海外の読者に紹介された最初の例は、おそらく、末松謙澄の英訳で、1882年にロンドンで出版されたとされていますが、外国人による英訳は、1925年 Arthur Waley(アーサー・ウェイリー) がロンドンで出版した『The Tale of Genji』が最初であると言われています。(『ウェイリー版 源氏物語』平凡社ライブラリ:N33/ム)

ウェイリーは1925年~33年にかけてこれを出版し、西洋に大きな衝撃を与えました。
その後も様々な国の人々に翻訳されていますが、訳する外国人は誰もがまずはウェイリーの英訳を読んでいると言っても過言ではありません。
彼の英訳により、“西洋諸国のその後の日本研究は格段の飛躍を見せた”(『世界の源氏物語』ランダムハウス講談社)とされています。
訳以外では、『病むことについて』(みすず書房・2002)にも掲載されている、ヴァージニア・ウルフ(映画『めぐりあう時間たち』でニコール・キッドマンが演じた人)の書いた『源氏物語』の感想などもよく読まれているようです。
さらに、この物語に対する情熱は、訳や感想だけにとどまりませんでした。
物語の続編を違う作者が書く、いわゆる《偽書》が多々発見されています。わかりやすく言うと同人誌…?
例えば、ライザ・ダルビーが紫式部のフィクションという形で描いたものが、『紫式部物語―その恋と生涯』(光文社・2002)
紫式部の死後、彼女の娘が遺品を片付けていると『源氏物語』の続編を見つけたとし、ライザ・ダルビー自らその続編を作っています。
そして、偽書の中でも興味深いのが、フランスの女流作家マルグリット・ユルスナール(1903年生「ハドリアヌス帝の回想」でフェミナ賞受賞)による『源氏の君の最後の恋』(原題:Le Dernier amour du Prince Genghi)
わたしたちのよく知る源氏の世界に、フランス的スパイスが利いています。
紫式部による『源氏物語』はその後半、最愛の妻・紫上を亡くし哀しみにくれる光源氏が雲隠れし、主人公が次の世代(源氏の息子・薫)に変わります。
そしてこの源氏が雲隠れする帖は、『雲隠』という帖名のみが伝わっているだけで、本文は白紙という、なんとも粋な方法で表現されています。
この『雲隠』という名前は、高貴な人の死、つまり源氏の死を象徴的に表していますが、この帖については、『もともとが帖名だけで意味を示し、本文は書かれなかったとする説と、本文は書かれたのだが紛失したとする説がある。(略)この幻の帖の内容については様々な説があるが、今でも真実は明らかになっていない。』(『面白くてよくわかる!源氏物語/根元浩 著)とされ、日本でも、六帖もの読者の創作『雲隠六帖』が伝えられているほど。
読み手側の数だけの源氏の最期を考えさせるのも、作者、紫式部の担いであったのではないだろうかとも考えられます。
そしてユルスナールの『源氏の君の最後の恋』は、まさにこの、白紙になっている『雲隠』の帖を想定して書かれたお話です。
さらに主人公は、『源氏物語』の数多の魅力的なヒロインたちの中でも最も地味で控えめで登場機会も少ない花散里という、非常に目の付け所のおもしろい作品です。
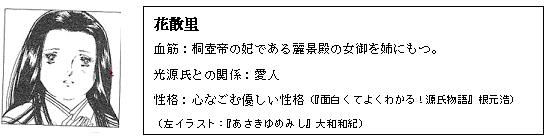
紫上の死や己の老いによりすっかり心をふさいでしまい、過去の輝いていた頃の自分を知る者とは誰にも会いたくない源氏。
どうにかしてもう一度お顔を見たい花散里が、尼さんからお姫様まで様々な人物に扮装して、へこたれずに何度も源氏のもとへお見舞いに行くところはまるで西洋のコメディ風。
そしてまた懲りずにこの花散里の扮するお姫様と関係をもってしまう源氏がおかしい。
そして最後。源氏が死に際に、自分と関係をもった女性たちをひとりひとり順に回想していくのですが、こんなに一生懸命通いつめた花散里の名は最後まで出てこなかった…という、いかにもフランス的ユーモアの効いたストーリー。
全体的にもの哀しい空気のお話のはずなのに、フランス映画のような皮肉なおかしさが。
訳にしても偽書にしても、日本語でしか表せない微妙な言い回しや独自の風習なんかを海外の言葉にするのは本当に大変…というか不可能だと感じました。
現代の私たちでさえ古文を読解することは容易ではないのですから、外国人にとって古典文学を本当に理解するということはかなりの難関でしょう。
しかしそれぞれのお国柄が非常によく現れた表現は、原作とは別物として楽しめます。
そしてやはり愛は世界共通!
表現は面白いほど変わりますが、このように『源氏物語』は日本人だけでなく様々な国の人々が引き込まれた愛と人生の物語であり、日本文学ではなくもはや世界文学となっていることがわかります。
語り出せばきりがありませんが…
例のしどけなくまねばむも なかなかにやとて こまかに書かず
(自分などがだらしなく書いていっては、立派なものをかえって壊してしまう結果になるのがこわいので、細かには書きません。)
引用・参考資料
『ウェイリー版 源氏物語』平凡社ライブラリ:N33/ム(中央所蔵)
『あさきゆめみし』大和和紀/講談社(他館所蔵)
『世界の源氏物語』ランダムハウス講談社:L/N33/ム(中央所蔵)
『病むことについて』ヴァージニア・ウルフ/みすず書房・2002(他館所蔵)
『紫式部物語―その恋と生涯』ライザ・ダルビー/光文社:933ダル(中央所蔵)
『東方綺譚』マルグリット・ユルスナール/白水社:953ユ(中央所蔵)
『面白くてよくわかる!源氏物語』根元浩/アスペクト:N33/ム(中央所蔵)
『世界文学としての源氏物語』笠間書院:N33/ム(中央所蔵)
『新編 日本古典文学全集 源氏物語③』小学館:N33/ム(中央所蔵)


























 「折口信夫所縁の地」より(Google)
「折口信夫所縁の地」より(Google)