まだ図書館業務になれていない時期に、お客様から「大人が楽しめる絵本を探しているのですが、何かオススメはありますか?」と声をかけられました。この質問を受けた時、正直軽いパニックが起きました(汗)。何しろ、当時はろくに絵本を読んでなく、日々業務になれることで精一杯でした。その時は焦りながらもWのセクションにある数冊の資料を提供した記憶があります。今はようやく何冊か大人向け絵本を紹介できるようになりました。
私が今回ご紹介したい作家は、「木を植えた男」のイラストを手がけたフレデリック・バック氏についてです。渋谷区にも数冊資料がありますのでご紹介致します。また、東京都現代美術館では、「フレデリック・バック展」を夏の特別企画展として開催しております。1000点以上の作品が展示されており、原画、セルはもちろん、水彩画やたくさんの映像作品もあります。展覧会の雰囲気や展示品も独特で、ワクワクするような仕掛けがたくさんあります。バック氏だけの大規模な展覧会は世界で初ということもあり、とても貴重な作品ばかりです。また今回のために、ご高齢でありながらも緊急来日されました。

左からフレデリック・バック氏,高畑勲監督,竹下景子さん(女優)7月1日、内覧会にて
全ての展示品を見た後は、バック氏の人柄、そして人生そのものを感じとれることでしょう。
<ご紹介したい資料>


(あらすじ)
フランスの荒れた山岳地帯に一人とどまる羊飼い、エルゼア-ル・ブッフィエ。何十年もの間、一人で木の実を植え続ける。その不屈の精神と無償の行為が緑あふれる森を茂らせる感動の名作。
第60回アカデミー賞短編映画アニメーション受賞
(コメント)
去年まで、渋谷区でお薦め50に入っていた資料です。本町図書館には、映像も所蔵してあります。文章も長いので、小さな子供よりも中学生から大人が読むのに適当な量です。
バック氏は、ジャン・ジオノの原作に感銘し、短編映画制作を決意したようです。5年半の歳月をかけ2万枚の原画を作成しました。映像は、まるで水が流れているようにスムーズで透明感があります。これぞまさしく、アートアニメーションです。一つ残念なお知らせとしては、主人公のエルゼア-ル・ブッフィエは実在の人物ではないと言うことです。バック氏自身も、このアニメーション制作中にこの事実を知って、途方に暮れて完成させるか迷ったそうです。それはブッフィエが実在しないことで、この物語が寓話になってしまう危険性があったからです。しかし、調べてみると、このブッフィエのような人物は世界中にいて、日本にもいたようだとバック氏はのち語っております(世界のアニメーション作家たちp.150)。私自身もこの事実を知った時はショックをうけました。しかし、この物語のメッセージは永遠なものであり、語り継がれるべきだと思います。
著者のジオノは、ブッフィエを創りだした意図について、「人々に木を好きになってもらうこと、より正確には、木々を植えるのを好きになってもらうこと」だと語っております(木を植えた男を読むp.82)。


(あらすじ)
舞台は北米を流れる大河セントローレンス川。自然に恵まれた美しい川が文明によって徐々に汚染されながらも力強く再生する姿がドキュメンタリー風に描かれています。
アカデミー賞短編アニメーション部門ノミネート作品 (受賞しなかったことが信じられない!)
(コメント)
これぞまさしく、大人の絵本!残念ながら渋谷図書館のみ所蔵。パステルや色鉛筆で彩られた原画は美しく、また優しさに溢れています。が、環境問題について強く訴えているメッセージ性の強い作品です。読み終わると、心に残り、そして考えさせられます。人間は地球によって生かされていることを、決して忘れてはならないと強く思いました。現在、渋谷区にこの映像を所蔵する館はありません。映像はまるでナショナルジオグラフィックのドキュメンタリーを見ているように美しいです。特に海の中のシーンは脱帽です。


(あらすじ)
あるロッキングチェアの一生と、失われるケベックの伝統や文化を一緒に盛り込んで描いた作品。バック氏らしい優しい色彩がみごとに表現されています。こちらの作品も、短編映画として制作されました。
第54回アカデミー賞短編アニメーション賞受賞
(コメント)
この作品はバック氏の娘さんが小学生の時、ロッキングチェアについて書いた文章がきっかけになったようです。バック氏は家族や親戚からこの椅子についての歴史を聞き、そしてケベックの歴史、文化などの資料を集め、まとめたものが「クラック!」として誕生しました。この作品制作中にケベックの美しい自然や文化が失われていくことに気づいたようです。この作品の後、「大いなる河の流れ」を制作しました。
この資料を読むと、良いものを大切に末永く使いたいと思います。日本人は、新しいものを好むことが多いので、古くても大切なもの、伝統的なものを残す気持ちを忘れてはいけないと思います。
*「クラック」とは、木が折れる音を表現したものです。
映像にはセリフがなくキャラクターの動きと愉快な音楽で構成されております。この作品をスタジオジブリの高畑勲監督はアメリカの映画館で初めて見て感動したようです。
この三作品は、現代美術館に映像と共に原画も展示されております。本を読んでから行くと、かなり面白いと思います。原画を直接見る機会はとても珍しいことです。この機会を逃さないでください。また、バック氏が「私たちに伝えようとしているのは何か?」感じとってみて下さい。
<ジブリと作家の関係>
「フレデリック・バック展」は、スタジオ ジブリの宮崎駿監督と高畑勲監督がバック氏を敬愛していることから、企画され、ジブリの協力のもと開催される運びになりました。高畑監督は以前からバック氏の作品に感銘を受け、1990年には「木を植えた男を読む」を出版し、バック氏とも友人関係を築いています。
また、宮崎駿監督の場合は、色鉛筆で描かれるバック氏の独特な表現方法や制作方法に影響を受け、「崖の上のポニョ」では似たような表現方法が使われています。展覧会期間中は、高畑監督の講演や、たくさんのイベントが開催される模様です。ジブリの気合が感じられます。
<アクティヴィストとして>
バック氏は、「木を植えた男」を世界に広めただけではなく、それと同時に沢山の木を植え、自然や動物の保護活動もしてきました。彼のアニメーションによって、カナダでは植樹運動が活発になり、90年代には伐採された木よりも植えた木のほうが多くなったようです。バック氏はこういった地道な活動やメッセージを今でも世界に発信しております。
<作家の素顔>
バック氏は、とてもチャーミングでユーモアあふれる愛すべき作家です。
(ジブリのディレクターがおしえてくれたエピソードその1)
今回の展覧会を開催するためにカナダのアトリエを訪れた際、バック氏がアトリエから現れた姿に驚いたそうです。
それはなんと!鼻に丸い赤いスポンジを付けて出て来たそうです。来客を喜ばせるために、ユーモア溢れるピエロのように現れたようです。
(来日中のエピソードその2)
カナダでは、愛犬マリーといつも一緒なバック氏。今回の来日には、もちろん愛犬を連れて来られません。さびしくなるので、段ボール紙で作った愛犬マリー人形を持って日本へ。美術館へは人形を抱えて登場。バック氏は、とてもチャーミングで、嬉しそうに犬を紹介していました。段ボール紙のマリーはほぼ等身大で、2Dですが手と足が動きます。 首輪も付けていました。犬種で言うとテリア系かな?人形を連れている姿がなんとも可愛らしかったです。
バック氏は人を喜ばせるのが大好きなのです。
作品も素晴らしいですが、自然保護活動の行動力と発信力、そして愛らしい人柄で、私もバック氏に魅了されました。人としても、見習いたいと強く思いました。
フレデリック・バック
1924年、ザールブリュッケン(現ドイツ領)生まれ。
ブルターニュ地方レンヌの美術学校で画家マテュラン・メウに師事した後、カナダのモントリオールに移住。
1952年 カナダの国営放送 ラジオカナダでグラフィック アート部門に就職する。
1968年 アニメーション部門に異動。以来、色鉛筆を使用した独特な映像作品を制作。
1982年、「クラック!」と88年、「木を植えた男」でアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞。現在もモントリオール在住。創
作活動を行いながら、自然保護団体の活動にも参加している。
オフィシャルホームページ:http:// www.fredericback.com
参考資料
「クラック!」(著)フレデリック・バック あすなろ書房 1987年
「木を植えた男」(著)ジャン・ジオノ あすなろ書房 1989年
「大いなる河の流れ」(著)フレデリック・バック あすなろ書房 1996年
「木を植えた男を読む」(著)高畑勲 徳間書店 1990年
「世界のアニメーション作家たち」(著)小野耕世 人文書院 2006年
私が今回ご紹介したい作家は、「木を植えた男」のイラストを手がけたフレデリック・バック氏についてです。渋谷区にも数冊資料がありますのでご紹介致します。また、東京都現代美術館では、「フレデリック・バック展」を夏の特別企画展として開催しております。1000点以上の作品が展示されており、原画、セルはもちろん、水彩画やたくさんの映像作品もあります。展覧会の雰囲気や展示品も独特で、ワクワクするような仕掛けがたくさんあります。バック氏だけの大規模な展覧会は世界で初ということもあり、とても貴重な作品ばかりです。また今回のために、ご高齢でありながらも緊急来日されました。

左からフレデリック・バック氏,高畑勲監督,竹下景子さん(女優)7月1日、内覧会にて
全ての展示品を見た後は、バック氏の人柄、そして人生そのものを感じとれることでしょう。
<ご紹介したい資料>


(あらすじ)
フランスの荒れた山岳地帯に一人とどまる羊飼い、エルゼア-ル・ブッフィエ。何十年もの間、一人で木の実を植え続ける。その不屈の精神と無償の行為が緑あふれる森を茂らせる感動の名作。
第60回アカデミー賞短編映画アニメーション受賞
(コメント)
去年まで、渋谷区でお薦め50に入っていた資料です。本町図書館には、映像も所蔵してあります。文章も長いので、小さな子供よりも中学生から大人が読むのに適当な量です。
バック氏は、ジャン・ジオノの原作に感銘し、短編映画制作を決意したようです。5年半の歳月をかけ2万枚の原画を作成しました。映像は、まるで水が流れているようにスムーズで透明感があります。これぞまさしく、アートアニメーションです。一つ残念なお知らせとしては、主人公のエルゼア-ル・ブッフィエは実在の人物ではないと言うことです。バック氏自身も、このアニメーション制作中にこの事実を知って、途方に暮れて完成させるか迷ったそうです。それはブッフィエが実在しないことで、この物語が寓話になってしまう危険性があったからです。しかし、調べてみると、このブッフィエのような人物は世界中にいて、日本にもいたようだとバック氏はのち語っております(世界のアニメーション作家たちp.150)。私自身もこの事実を知った時はショックをうけました。しかし、この物語のメッセージは永遠なものであり、語り継がれるべきだと思います。
著者のジオノは、ブッフィエを創りだした意図について、「人々に木を好きになってもらうこと、より正確には、木々を植えるのを好きになってもらうこと」だと語っております(木を植えた男を読むp.82)。


(あらすじ)
舞台は北米を流れる大河セントローレンス川。自然に恵まれた美しい川が文明によって徐々に汚染されながらも力強く再生する姿がドキュメンタリー風に描かれています。
アカデミー賞短編アニメーション部門ノミネート作品 (受賞しなかったことが信じられない!)
(コメント)
これぞまさしく、大人の絵本!残念ながら渋谷図書館のみ所蔵。パステルや色鉛筆で彩られた原画は美しく、また優しさに溢れています。が、環境問題について強く訴えているメッセージ性の強い作品です。読み終わると、心に残り、そして考えさせられます。人間は地球によって生かされていることを、決して忘れてはならないと強く思いました。現在、渋谷区にこの映像を所蔵する館はありません。映像はまるでナショナルジオグラフィックのドキュメンタリーを見ているように美しいです。特に海の中のシーンは脱帽です。


(あらすじ)
あるロッキングチェアの一生と、失われるケベックの伝統や文化を一緒に盛り込んで描いた作品。バック氏らしい優しい色彩がみごとに表現されています。こちらの作品も、短編映画として制作されました。
第54回アカデミー賞短編アニメーション賞受賞
(コメント)
この作品はバック氏の娘さんが小学生の時、ロッキングチェアについて書いた文章がきっかけになったようです。バック氏は家族や親戚からこの椅子についての歴史を聞き、そしてケベックの歴史、文化などの資料を集め、まとめたものが「クラック!」として誕生しました。この作品制作中にケベックの美しい自然や文化が失われていくことに気づいたようです。この作品の後、「大いなる河の流れ」を制作しました。
この資料を読むと、良いものを大切に末永く使いたいと思います。日本人は、新しいものを好むことが多いので、古くても大切なもの、伝統的なものを残す気持ちを忘れてはいけないと思います。
*「クラック」とは、木が折れる音を表現したものです。
映像にはセリフがなくキャラクターの動きと愉快な音楽で構成されております。この作品をスタジオジブリの高畑勲監督はアメリカの映画館で初めて見て感動したようです。
この三作品は、現代美術館に映像と共に原画も展示されております。本を読んでから行くと、かなり面白いと思います。原画を直接見る機会はとても珍しいことです。この機会を逃さないでください。また、バック氏が「私たちに伝えようとしているのは何か?」感じとってみて下さい。
<ジブリと作家の関係>
「フレデリック・バック展」は、スタジオ ジブリの宮崎駿監督と高畑勲監督がバック氏を敬愛していることから、企画され、ジブリの協力のもと開催される運びになりました。高畑監督は以前からバック氏の作品に感銘を受け、1990年には「木を植えた男を読む」を出版し、バック氏とも友人関係を築いています。
また、宮崎駿監督の場合は、色鉛筆で描かれるバック氏の独特な表現方法や制作方法に影響を受け、「崖の上のポニョ」では似たような表現方法が使われています。展覧会期間中は、高畑監督の講演や、たくさんのイベントが開催される模様です。ジブリの気合が感じられます。
<アクティヴィストとして>
バック氏は、「木を植えた男」を世界に広めただけではなく、それと同時に沢山の木を植え、自然や動物の保護活動もしてきました。彼のアニメーションによって、カナダでは植樹運動が活発になり、90年代には伐採された木よりも植えた木のほうが多くなったようです。バック氏はこういった地道な活動やメッセージを今でも世界に発信しております。
<作家の素顔>
バック氏は、とてもチャーミングでユーモアあふれる愛すべき作家です。
(ジブリのディレクターがおしえてくれたエピソードその1)
今回の展覧会を開催するためにカナダのアトリエを訪れた際、バック氏がアトリエから現れた姿に驚いたそうです。
それはなんと!鼻に丸い赤いスポンジを付けて出て来たそうです。来客を喜ばせるために、ユーモア溢れるピエロのように現れたようです。
(来日中のエピソードその2)
カナダでは、愛犬マリーといつも一緒なバック氏。今回の来日には、もちろん愛犬を連れて来られません。さびしくなるので、段ボール紙で作った愛犬マリー人形を持って日本へ。美術館へは人形を抱えて登場。バック氏は、とてもチャーミングで、嬉しそうに犬を紹介していました。段ボール紙のマリーはほぼ等身大で、2Dですが手と足が動きます。 首輪も付けていました。犬種で言うとテリア系かな?人形を連れている姿がなんとも可愛らしかったです。
バック氏は人を喜ばせるのが大好きなのです。
作品も素晴らしいですが、自然保護活動の行動力と発信力、そして愛らしい人柄で、私もバック氏に魅了されました。人としても、見習いたいと強く思いました。
フレデリック・バック
1924年、ザールブリュッケン(現ドイツ領)生まれ。
ブルターニュ地方レンヌの美術学校で画家マテュラン・メウに師事した後、カナダのモントリオールに移住。
1952年 カナダの国営放送 ラジオカナダでグラフィック アート部門に就職する。
1968年 アニメーション部門に異動。以来、色鉛筆を使用した独特な映像作品を制作。
1982年、「クラック!」と88年、「木を植えた男」でアカデミー賞短編アニメーション賞を受賞。現在もモントリオール在住。創
作活動を行いながら、自然保護団体の活動にも参加している。
オフィシャルホームページ:http:// www.fredericback.com
参考資料
「クラック!」(著)フレデリック・バック あすなろ書房 1987年
「木を植えた男」(著)ジャン・ジオノ あすなろ書房 1989年
「大いなる河の流れ」(著)フレデリック・バック あすなろ書房 1996年
「木を植えた男を読む」(著)高畑勲 徳間書店 1990年
「世界のアニメーション作家たち」(著)小野耕世 人文書院 2006年














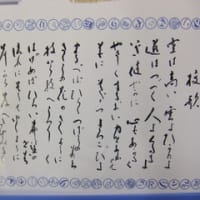





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます