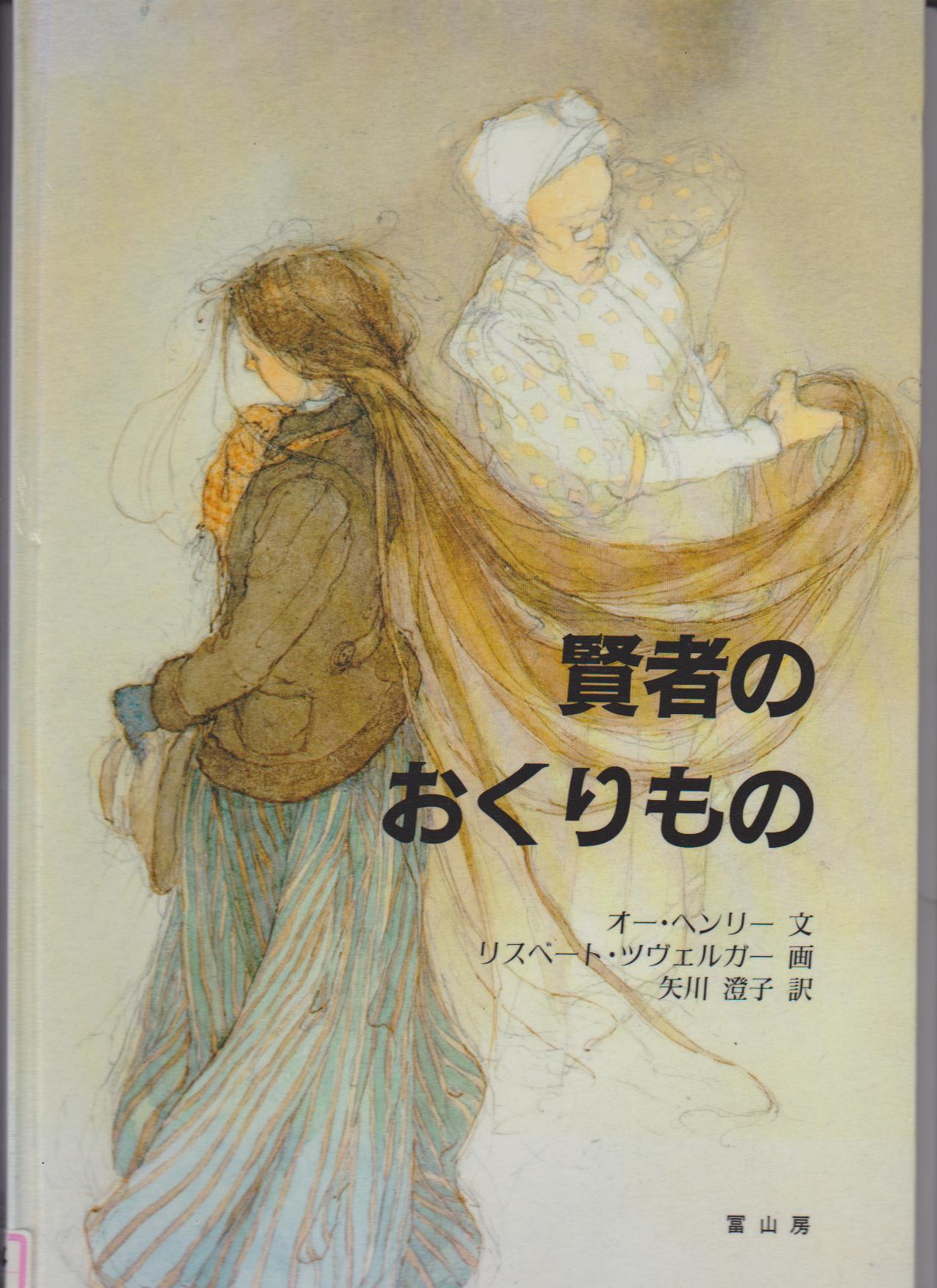1.はじめに
渋谷という街ほど、里帰りという単語と、なかなかそう結び付けづらい街は無いだろう。そもそも、渋谷はずっと流行の発信地であるし、ショッピングや料理や映画、そういった様々な文化や遊びを楽しむ町だ。と、この本を手に取った人は、誰もが思うはずだ。
それでも、渋谷という場所が、昔からこのように派手で明るくて騒々しい場所だったわけではない。その昔、渋谷を代表する2つの坂、宮益坂と道玄坂が、旅人を接待する町場として栄え始める。そこから、神泉谷、丸山花街が色町として発展。そして商業空間として、百軒店が繁盛し、第二次世界大戦後には駅前にヤミ市ができた。賑わいの中心地を少しずつ移動させながら、1960年あたりから、若者が渋谷のセンター街に集まってきて、1975年頃からファッショナブルな街として認識されるようになった。時代ごとに、人々を引き付けるものは変わっていったが、新しい情報や文化の発信地であったことは確かである。結果、今ではセンター街だけでも、一日に6万人前後の人が訪れるほど、日々多くの人が行き交う繁華街となったのだ。
オシゴト系青春小説という一見爽やかそうなキャッチコピーを掲げた、この「渋谷に里帰り」という作品は、たとえば出稼ぎに出ていて実家に帰ってきた話でも、昔は渋谷でやんちゃしていて、社会人になって久しぶりに遊びに来た、とかいう話でもない。渋谷で生まれ育った主人公、峰崎稔が、子供のときについたうそが原因で、引越して以来、足を遠のかせていた地元に、仕事を理由に久しぶりに帰ってきたという話である。帰ってきたところで、特に大きな出来事があるわけでもなく、感動の再会があるわけでもない。たんたんと進む話の中で主人公は、鬼門として遠ざかっていた約20年の間に、あまりのも様変わりしている渋谷に、寂しさを通り越して最早新しい街だと認識する。それでも、見覚えのある場所に出会うたびに、郷愁を感じるのだ。だから、里帰り、なのである。
2.今より少しだけ昔の渋谷
「渋谷に里帰り」というタイトルにあるだけあり、作中には渋谷の様々な場所が描かれている。でも、そこはすでに今の渋谷ではない。この作品が書かれたのは2006年から2007年の間で、単行本が発売されたのが2007年10月である。つまり、ここに描かれているのはおよそ5年前の渋谷なのだ。たった5年と思われるかもしれないが、されど5年。下に、作中で渋谷やその周辺について触れた部分をいくつか抜粋してみた。作中ではまだ存在し、登場している店や建物が、今ではもう無いものもある。今の渋谷をよく知る人は、今の渋谷を、昔の渋谷を知る人は昔の渋谷を思い出しながら、辿ってみるのも面白いだろう。
・「山手線を降りて、ハチ公口をでると、スクランブル交差点だ。」(p.30)
・「右手に『三千里薬品』があるのに気づく。」(p.30)
・「前方の『渋谷西村』へ向かって歩いた。左手に『マルナン』を見つけた。」(p.30)
・「青地に白で大きく「1」と書いてあるビルがある。昔、ここはデパートだったように思うが、その名前までは思い出せない。」(p.31)
・「東急本店が見えてきた。ここがBunkamuraか。」(p.31)
・「いまふたりがいるのは渋谷の交差点間近の『マクドナルド』だ。」(p.45)
・千駄ヶ谷の改札口を出て、明治通りへ向かっている途中の神社。(p.53)
・宮下公園の手前の歩道橋から見える、ほぼ同じ高さを走る山手線。その向こうに見える電力館。(p.57)
・「『タワーレコード』のビルが見えるが、あれは昔からあそこにあったのだろうか。」(p.58)
・「恵比寿駅を降りたら、『第三の男』のテーマ曲が流れていた。」(p.72)
・「恵比寿にきたのはいったい何年ぶりか、見当がつかない。ホームから階段をのぼり、改札口をでて左に折れた。いくつかの店が立ち並ぶ通路を渡り、今度はえらく長いエスカレーターで下った。」(p.73)
・「宮益坂下の交差点で信号待ちをしているとき、銀座線の電車が高架の線路を走っていくのが見えた。地下鉄であるにもかかわらず、建物の三階にホームがあることが、昔はメビウスの輪にも似た奇妙な現象のように思えた。」(p.89)
・「銀座線の下に、渋谷駅から東急文化会館を繋げていた高架通路があるのが目に入った。」(p.90)
・渋谷駅東口のロータリーを右手、フェンスを左手に進み、右の方角にそびえる塔のような高層ビル『セルリアンタワー』。(p.92)
・「『恋文横丁此処にありき』と記された看板を掲げた薬局のビルが、取り壊されていた。その脇にあったレストランやゲームセンターも姿を消している。そこを通り抜けていくと道玄坂に面しているザ・プライムの裏口へ入れた。ビルの狭間というか隙間のような道があった。」(p.142)
・「京王線の笹塚駅を抜けて、甲州街道を渡って、さらに商店街に入っていった。米屋に魚屋、酒屋に靴屋、洋品店、八百屋に電気屋、寿司屋、中華料理屋にトンカツや。手作りのせんべい屋もある。個人経営の店が狭い道の両脇にずらりと立ち並び、チェーン店があっても、町の風情を乱す事なく、じょうずにとけこんでいた。」(p.165)
・ハンズの近く、NHKへむかう坂をあがる途中の輸入盤のレコード店『シスコ』
(p.201)
・東急東横店東館の屋上、『ちびっ子プレイランド』と『東横稲荷神社』。(p.211、p.214)
・円山町の映画館、ユーロスペース。(p.223)
・センター街の位置口左の『大盛堂書店』。(p.224)
・センター街の『HMV』や『さくらや』。(p.225)
・地下鉄半蔵門線の手前の『旭屋書店』。(p.226)
・「鉄仮面のような形の建物は交番だ。」(p.227)
・交番の裏にある、中華料理屋と台湾料理屋『龍の髭』。(p.228)
・「井の頭通りをすぐ右に折れ、えっちらおっちら坂をあがる。左手にパルコパート3が見えてくると、そこをまた左へ曲がる。そこの角のビルがなくなっていた。東急文化会館と同様に工事中をしめす白いフェンスに囲まれている。そのならびに『東急ハンズ』がある。」(p.232)
・「オルガン坂をくだり、井の頭通りにもどると、『東急ハンズ』を左手にまっすぐ、やがて右に折れ、BEAMを左手に歩いていくと、文化村通りへでた。」(p.242)
・「犬の顔が前の部分に描かれた小型のバスが、こちらにむけて走ってくる。」(p.247)
・「ハチ公バスは明治通りから渋谷駅東口に入る。左に東急文化会館の跡地が見える。こちらのバス停もバスターミナルにはなく、その通り沿いにある。そこから青山通りへとバスは走っていく。」(p.251)
・「バスは細い道を通り終え、ふたたび広い通りにでた。明治通りだ。曲がる瞬間、角に小さな神社を見つけた。」(p.253)
3.東急文化会館と電力館
2003年に閉館し、なくなってしまった東急文化会館に思いを馳せ、その跡地を囲む白いフェンスに憤りを感じる主人公は作中で32歳。20年渋谷を離れているから、彼の思い出の中にある昔の渋谷は、1980年代の渋谷だ。そのころの渋谷といえば、バブルの真っ只中。1981年に渋谷センター街が整備され、同じ年にパルコパート3ができた。1987年には109-2(2011年に109MEN’Sに改称)も建ち、ファッションブランドを中心とした商業施設が次々とうまれる。渋カジ、ボディコンといった新しいファッションが広がり、渋谷全体が明るく華やかだった。そうして新しく大きなビルがいくつもできる中、主人公の周りの友だちも家の土地を高く売って、他の土地へと移り住んでいってしまう。そして、同級生の女の子が泣くのだ。町には誰もいなくなって、学校もなくなってしまう、と。
作中では工事中だった東急文化会館の跡地には、今年2012年に新たな複合ビル、「渋谷ヒカリエ」が誕生した。ちなみに「渋谷ヒカリエ」ができることが発表されたのは2010年だそうなので、作中ではそのことについては何も触れていない。
そして、営業先の顧客との待ち合わせ時間までに出来た空きに、営業の先輩に連れられて休憩しに入った電力館。ここは、2010年に大規模な改装工事で各階が順次閉鎖されていき、2011年3月20日に新装開館が予定されていたが、直前の2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴い、再オープンを延期した後、閉館となった。
4.おわりに
慌しく忙しい日々を過ごしていて、渋谷のような人ごみの中では、周囲をきょろきょろと見て歩く余裕もない。立ち止まろうものなら、後ろの人に迷惑そうに避けられる。けれどそんな風に少し目を離している間に、大きな変化も含めて、渋谷という街は日々店が入れ替わり、そのたびにまた多くの人が訪れるのだ。この本が出て5年がたち、作中に存在する建物や場所も、実際にいくつも建て変わって様相を変えている。昔の記憶を持つ本として、この本は貴重な作品となるだろう。
「渋谷に里帰り」は2011年に文庫版となって、主人公のその後の様子がちらりと描かれた「女房が里帰り」が書き下ろしで収録されている。峰崎稔は、今の渋谷を見てどう思うだろうか。来年2013年3月には、東急東横線が副都心線と直通運転を行うため、渋谷駅は地上ではなく地下となる。渋谷駅の外観や周辺の光景は、更に新たな変化を遂げていくはずだ。
また、東急百貨店東横店は老朽化を理由に、東館を2013年3月末にて営業終了させる事を発表したので、作中に登場したデパート屋上遊園地『ちびっ子プレイランド』もなくなってしまうらしい。その前に一度行って、上から渋谷の町並みを眺めて、東横稲荷神社に参拝したい。
参考資料
「渋谷に里帰り」山本幸久 日本放送出版協会 x/ヤマ (中央他所蔵)
「2011年 渋谷区勢概要」渋谷区企画部広報課 S41 (全館所蔵)
「歴史のなかの渋谷 ―渋谷から江戸、東京へ― (渋谷学叢書第2巻)」上山和雄 雄山閣 291.3/ウ (中央他所蔵)