愛する子供たちへ
1485年、リチャード3世はイングランドの王座に就いていました。政情の不安定な時期で、リチャード王は、王座を守るために一度ならず戦わなければなりませんでした。しかし、王は戦いの経験を積んだ軍人であり、8,000人から1万人の軍隊を持つ勇猛で抜け目のない戦士でした。
同じ年、イングランドの王位をねらうリッチモンド伯ヘンリー・チューダーがリチャード王に戦いを挑み、ボズワース・フィールドで戦います。「ボズワース・フィールドの戦い」と呼ばれる戦いです。ヘンリーはリチャードと違って戦いの経験がほとんどなく、兵力も5,000人しかありませんでした。ただし傍らに良き助言者たちがいました。身分が高く、リチャードとの戦いを含む同様な戦いに出たことのある人たちでした。戦いの朝が来ると、何もかもがリチャード王の勝利を予告しているかのようでした。
1485年8月22日の出来事は、よく知られている衝撃的な言い伝えに要約されています。その日の朝、リチャード王は従者とともにヘンリーの軍隊と戦う準備をしていました。この戦いの勝者がイングランド王になるのです。戦いがまさに始まろうというとき、リチャードは愛馬の用意ができているかどうか、僕を送って確認させました。
「蹄鉄を早く付けろ」と僕は蹄鉄工に命じました。「王はこの馬を駆って軍の先頭を行かれるのだぞ。」
蹄鉄工は待ってくださいと答えました。「この数日間、わたしは王の軍のすべての馬に蹄鉄を付けてきました。ですから、もっと鉄を持って来ないといけません。」
気の短い僕は、待てないと言いました。「王の敵は今にも攻めて来る。我々は戦場で敵を迎え撃たねばならないのだぞ。あるもので間に合わせろ。」
蹄鉄工は命じられたとおり、最善を尽くして鉄の棒から4個の蹄鉄を作りました。蹄鉄をハンマーでたたいて作ると、3つまで馬に取り付けました。ところが、4つ目を馬に取り付けようとしたとき、打ちつける釘が足りないことに気づき、僕に言いました。
「あと1、2本釘が必要です。ハンマーで打って作るには、少しお時間を頂かないと。」
しかし、僕はもう待てないと言います。「もうラッパが鳴っている。とにかくあるものでどうにかできないのか。」
最善は尽くしますが4番目の蹄鉄が外れないという保証はできません、と蹄鉄工は言いました。
僕は命じました。「とにかく釘で留めろ。そして急げ。さもないと、おまえもわたしもリチャード王のお怒りを買うことになるぞ。」
間もなく戦いが始まりました。兵士を奮い立たせるために、リチャード王は戦場を駆け巡って戦い、「進め、進むんだ」と叫んで兵を戦に駆り立てました。
しかし、リチャード王が戦場を見回すと、自分の軍から何人かが敗走するのが目に入りました。ほかの兵士も敗走を始めるのではないかと恐れ、王は奮起させるために敗走兵の出ている戦線目がけて馬を駆りました。ところが、たどり着く前に王の馬がつまずいて転び、王は地面に投げ出されてしまったのです。王が必死で馬を走らせるうちに、蹄鉄工が恐れていたとおり、蹄鉄の一つが外れて飛んでしまったのでした。
リチャード王は地面から飛び起きましたが、愛馬は全速力で走り去ってしまいました。ヘンリーの軍が突進して来るのを見て、リチャード王は剣を宙に高々と上げて叫びました。
「馬を、馬をよこせ。代わりに我が王国をくれてやる。」
しかし、手遅れでした。そのころにはヘンリーの軍が向かって来ていたので、リチャード王の兵士は震え上がって逃げて行ってしまいました。こうして王は戦いに敗れます。以来、人々は次の詩を口ずさむようになりました。
釘がなくなり、蹄鉄はなくなった。
蹄鉄がなくなり、馬はいなくなった。
馬がいなくなり、戦いに敗れた。
戦いに敗れ、王国を失った。
すべて、馬蹄を留める釘が1本なかったために。■
小さなことをおろそかにすることにより、国王の座を失い、国をも失ってしまったという悲しい教訓の物語です。リチャード王の敗北の理由は、もちろん味方の裏切りも含めてそれだけはありませんが、小事に忠実でなかったということは間違いないと思われます。
主は次のように語っています。
「主は小さな手段によって大いなることを成し遂げられることが分かるのである。」(モルモン書1ニーフィイ16章29節)
「記録を保存するのはわたしが愚かだからであると、あなたは思うかもしれない。しかし見よ、わたしはあなたに言う。小さな、簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。そして、小さな手段が度々知者を辱める。主なる神は偉大な永遠の目的を達するために、様々な手段によって事を行われる。また、ごく小さな手段によって、主は知者を辱め、また多くの人を救われる。」(モルモン書アルマ37章6~7節)
神のみわざを推し進めるに当たっても、主は「小さな、簡単なこと」によって「大いなることを成し遂げられる」と約束されています。
預言者スペンサー・W・キンボール大管長が、まだご健在の頃、常に「歩みを速めなさい」と語っておられました。多くの教会員が、信仰をもってそのチャレンジに応えました。そして、、教会は全世界に向けて多くの宣教師を送り出し、著しい成長を遂げました。現在、預言者トーマス・S・モンソン大管長は、教会史上かつてない8万人を越える宣教師を全世界に送り出し、毎年30万人以上の方々をバプテスマへ導き、教会員として迎え入れています。しかしながら、主や預言者のビジョンは、はるかに大きなものです。「み業を速めなさい」とのチャレンジの下、さらに多くの教会員と宣教師が思いを一つに多くの人々に主の祝福を分かつべく励んでいます。
さて、非常に興味深いことに「歩みを速めなさい」の元々の英語は「Lengthen your stride!」です。それは、「歩幅を広めなさい」という意味です。実は預言者スペンサー・W・キンボール大管長は、そのチャレンジと共に次のような意味深長な言葉を同時に述べています。「If hurry less, you will move faster.」それは、「もし、急がなければ、速く進むことができる」(急がば、回れ)という意味なのでしょう。
「歩みを速めなさい(歩幅を広げなさい)」と「もし、急がなければ、速く進むことができる」という相矛盾するようなことを同時に述べた真の狙いは何なのでしょうか。どういう意味で、預言者はそのように語ったのでしょうか。
お父さんが沖縄にいた当時、アジア北地域会長であったエドワード・L・ブラウン長老が来沖されて、沖縄の教会員との特別集会を持たれました。その際、彼は「If hurry less, you will move faster.」について次のように説明されました。
「『歩みを速めなさい(歩幅を広げなさい)』、『もし、急がなければ、速く進むことができる』とは、これまでの2倍も3倍もがむしゃらに働きなさいということではありません。福音の基本的な教えや原則を今まで以上に着実に実践することにより、私たちの信仰や霊性を高め、喜びに満ち溢れるその当然の結果としてみ業をさらに力強く推し進める力が増し加わるようにしなさいという意味です。」
預言者エズラ・タフト・ベンソン大管長も次のように語っています。
「わたしたちはよくステークでの活動のレベルを高めようと、大変な努力をします。また聖餐会の出席率を上げるために一生懸命働きかけます。さらに宣教師の数や神殿結婚の数を増やそうと努力します。もちろんこうした努力は立派なことですし、王国の発展のために大切なことです。けれども、もし個人や家族が定期的に続けて熱心に聖典を読むならば、これらの様々な領域の活動は自動的に成し遂げられます。もっと証が深まり、人々はさらに熱心に参加するようになるでしょう。家族が強められ、個人のうえに啓示が注がれることでしょう。」(エズラ・タフト・ベンソン大管長「聖徒の道」1986年7月号p.81)
すなわち、日々真心込めて主に祈り、個人として家族として聖典を研究し、毎週教会に集って聖餐にあずかり、「家庭の夕べ」を定期的に行い、愛ある奉仕を日々心がけ、神殿に参入して神聖な聖約と儀式にあずかりつつ、先祖の救いのために喜んで奉仕するなど、自分にできる小さくて簡単なひとつひとつの主の教えを地道に続けていくことが祝福にあずかる重要な鍵なのです。いわゆる凡事徹底です。そこには御霊による大きな喜びと平安があり、神への深い感謝があります。そうする中で増し加わる信仰と霊的な力は、私たちの「歩幅を今まで以上に広げる」力となり、ペースは変わらずとも霊的な歩幅が広がる分、み業を速める力となるのです。聖く、謙遜で忠実な生活を送る息子や娘たちに、御父は確かに天の窓を開き、豊かな恵みと力を溢れるばかりに注いで下さいます。
それらの日々なすべきひとつひとつの課題は、あの戦いに出で立った馬の「馬蹄を留める釘の1本1本」です。おろそかにすることなく努め励むならば、このみ業を速める大いなる力となり、ヘンリー王のように、熾烈な戦いすなわちサタンとの「魂の戦い」に勝利を得る力となることでしょう。(おやじより)
 「にほんブログ村」お役に立てたらクリックお願いしま~す!より多くの方々に記事を読んで頂けます!1日1回のクリックで OKで~す!
「にほんブログ村」お役に立てたらクリックお願いしま~す!より多くの方々に記事を読んで頂けます!1日1回のクリックで OKで~す!
1485年、リチャード3世はイングランドの王座に就いていました。政情の不安定な時期で、リチャード王は、王座を守るために一度ならず戦わなければなりませんでした。しかし、王は戦いの経験を積んだ軍人であり、8,000人から1万人の軍隊を持つ勇猛で抜け目のない戦士でした。
同じ年、イングランドの王位をねらうリッチモンド伯ヘンリー・チューダーがリチャード王に戦いを挑み、ボズワース・フィールドで戦います。「ボズワース・フィールドの戦い」と呼ばれる戦いです。ヘンリーはリチャードと違って戦いの経験がほとんどなく、兵力も5,000人しかありませんでした。ただし傍らに良き助言者たちがいました。身分が高く、リチャードとの戦いを含む同様な戦いに出たことのある人たちでした。戦いの朝が来ると、何もかもがリチャード王の勝利を予告しているかのようでした。
1485年8月22日の出来事は、よく知られている衝撃的な言い伝えに要約されています。その日の朝、リチャード王は従者とともにヘンリーの軍隊と戦う準備をしていました。この戦いの勝者がイングランド王になるのです。戦いがまさに始まろうというとき、リチャードは愛馬の用意ができているかどうか、僕を送って確認させました。
「蹄鉄を早く付けろ」と僕は蹄鉄工に命じました。「王はこの馬を駆って軍の先頭を行かれるのだぞ。」
蹄鉄工は待ってくださいと答えました。「この数日間、わたしは王の軍のすべての馬に蹄鉄を付けてきました。ですから、もっと鉄を持って来ないといけません。」
気の短い僕は、待てないと言いました。「王の敵は今にも攻めて来る。我々は戦場で敵を迎え撃たねばならないのだぞ。あるもので間に合わせろ。」
蹄鉄工は命じられたとおり、最善を尽くして鉄の棒から4個の蹄鉄を作りました。蹄鉄をハンマーでたたいて作ると、3つまで馬に取り付けました。ところが、4つ目を馬に取り付けようとしたとき、打ちつける釘が足りないことに気づき、僕に言いました。
「あと1、2本釘が必要です。ハンマーで打って作るには、少しお時間を頂かないと。」
しかし、僕はもう待てないと言います。「もうラッパが鳴っている。とにかくあるものでどうにかできないのか。」
最善は尽くしますが4番目の蹄鉄が外れないという保証はできません、と蹄鉄工は言いました。
僕は命じました。「とにかく釘で留めろ。そして急げ。さもないと、おまえもわたしもリチャード王のお怒りを買うことになるぞ。」
間もなく戦いが始まりました。兵士を奮い立たせるために、リチャード王は戦場を駆け巡って戦い、「進め、進むんだ」と叫んで兵を戦に駆り立てました。
しかし、リチャード王が戦場を見回すと、自分の軍から何人かが敗走するのが目に入りました。ほかの兵士も敗走を始めるのではないかと恐れ、王は奮起させるために敗走兵の出ている戦線目がけて馬を駆りました。ところが、たどり着く前に王の馬がつまずいて転び、王は地面に投げ出されてしまったのです。王が必死で馬を走らせるうちに、蹄鉄工が恐れていたとおり、蹄鉄の一つが外れて飛んでしまったのでした。
リチャード王は地面から飛び起きましたが、愛馬は全速力で走り去ってしまいました。ヘンリーの軍が突進して来るのを見て、リチャード王は剣を宙に高々と上げて叫びました。
「馬を、馬をよこせ。代わりに我が王国をくれてやる。」
しかし、手遅れでした。そのころにはヘンリーの軍が向かって来ていたので、リチャード王の兵士は震え上がって逃げて行ってしまいました。こうして王は戦いに敗れます。以来、人々は次の詩を口ずさむようになりました。
釘がなくなり、蹄鉄はなくなった。
蹄鉄がなくなり、馬はいなくなった。
馬がいなくなり、戦いに敗れた。
戦いに敗れ、王国を失った。
すべて、馬蹄を留める釘が1本なかったために。■
小さなことをおろそかにすることにより、国王の座を失い、国をも失ってしまったという悲しい教訓の物語です。リチャード王の敗北の理由は、もちろん味方の裏切りも含めてそれだけはありませんが、小事に忠実でなかったということは間違いないと思われます。
主は次のように語っています。
「主は小さな手段によって大いなることを成し遂げられることが分かるのである。」(モルモン書1ニーフィイ16章29節)
「記録を保存するのはわたしが愚かだからであると、あなたは思うかもしれない。しかし見よ、わたしはあなたに言う。小さな、簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。そして、小さな手段が度々知者を辱める。主なる神は偉大な永遠の目的を達するために、様々な手段によって事を行われる。また、ごく小さな手段によって、主は知者を辱め、また多くの人を救われる。」(モルモン書アルマ37章6~7節)
神のみわざを推し進めるに当たっても、主は「小さな、簡単なこと」によって「大いなることを成し遂げられる」と約束されています。
預言者スペンサー・W・キンボール大管長が、まだご健在の頃、常に「歩みを速めなさい」と語っておられました。多くの教会員が、信仰をもってそのチャレンジに応えました。そして、、教会は全世界に向けて多くの宣教師を送り出し、著しい成長を遂げました。現在、預言者トーマス・S・モンソン大管長は、教会史上かつてない8万人を越える宣教師を全世界に送り出し、毎年30万人以上の方々をバプテスマへ導き、教会員として迎え入れています。しかしながら、主や預言者のビジョンは、はるかに大きなものです。「み業を速めなさい」とのチャレンジの下、さらに多くの教会員と宣教師が思いを一つに多くの人々に主の祝福を分かつべく励んでいます。
さて、非常に興味深いことに「歩みを速めなさい」の元々の英語は「Lengthen your stride!」です。それは、「歩幅を広めなさい」という意味です。実は預言者スペンサー・W・キンボール大管長は、そのチャレンジと共に次のような意味深長な言葉を同時に述べています。「If hurry less, you will move faster.」それは、「もし、急がなければ、速く進むことができる」(急がば、回れ)という意味なのでしょう。
「歩みを速めなさい(歩幅を広げなさい)」と「もし、急がなければ、速く進むことができる」という相矛盾するようなことを同時に述べた真の狙いは何なのでしょうか。どういう意味で、預言者はそのように語ったのでしょうか。
お父さんが沖縄にいた当時、アジア北地域会長であったエドワード・L・ブラウン長老が来沖されて、沖縄の教会員との特別集会を持たれました。その際、彼は「If hurry less, you will move faster.」について次のように説明されました。
「『歩みを速めなさい(歩幅を広げなさい)』、『もし、急がなければ、速く進むことができる』とは、これまでの2倍も3倍もがむしゃらに働きなさいということではありません。福音の基本的な教えや原則を今まで以上に着実に実践することにより、私たちの信仰や霊性を高め、喜びに満ち溢れるその当然の結果としてみ業をさらに力強く推し進める力が増し加わるようにしなさいという意味です。」
預言者エズラ・タフト・ベンソン大管長も次のように語っています。
「わたしたちはよくステークでの活動のレベルを高めようと、大変な努力をします。また聖餐会の出席率を上げるために一生懸命働きかけます。さらに宣教師の数や神殿結婚の数を増やそうと努力します。もちろんこうした努力は立派なことですし、王国の発展のために大切なことです。けれども、もし個人や家族が定期的に続けて熱心に聖典を読むならば、これらの様々な領域の活動は自動的に成し遂げられます。もっと証が深まり、人々はさらに熱心に参加するようになるでしょう。家族が強められ、個人のうえに啓示が注がれることでしょう。」(エズラ・タフト・ベンソン大管長「聖徒の道」1986年7月号p.81)
すなわち、日々真心込めて主に祈り、個人として家族として聖典を研究し、毎週教会に集って聖餐にあずかり、「家庭の夕べ」を定期的に行い、愛ある奉仕を日々心がけ、神殿に参入して神聖な聖約と儀式にあずかりつつ、先祖の救いのために喜んで奉仕するなど、自分にできる小さくて簡単なひとつひとつの主の教えを地道に続けていくことが祝福にあずかる重要な鍵なのです。いわゆる凡事徹底です。そこには御霊による大きな喜びと平安があり、神への深い感謝があります。そうする中で増し加わる信仰と霊的な力は、私たちの「歩幅を今まで以上に広げる」力となり、ペースは変わらずとも霊的な歩幅が広がる分、み業を速める力となるのです。聖く、謙遜で忠実な生活を送る息子や娘たちに、御父は確かに天の窓を開き、豊かな恵みと力を溢れるばかりに注いで下さいます。
それらの日々なすべきひとつひとつの課題は、あの戦いに出で立った馬の「馬蹄を留める釘の1本1本」です。おろそかにすることなく努め励むならば、このみ業を速める大いなる力となり、ヘンリー王のように、熾烈な戦いすなわちサタンとの「魂の戦い」に勝利を得る力となることでしょう。(おやじより)










 あまりにも多くを失い、生きていくのさえ精一杯だった沖縄の終戦直後の厳しい時代、子育てで大変だったおばあちゃんを支えた珠玉の黄金言葉がありました。
あまりにも多くを失い、生きていくのさえ精一杯だった沖縄の終戦直後の厳しい時代、子育てで大変だったおばあちゃんを支えた珠玉の黄金言葉がありました。 おばあちゃんの大好きなクガニクトゥバに以前にも紹介した「てぃんさぐぬ花」があります。先人の深い洞察と知恵に基づいて語られた格言のひとつです。
おばあちゃんの大好きなクガニクトゥバに以前にも紹介した「てぃんさぐぬ花」があります。先人の深い洞察と知恵に基づいて語られた格言のひとつです。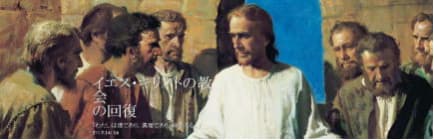

 藤林氏は、当初仮名入りの14文字は横書きには無理と思っていました。ところが不思議なことに、その頃、関西に住む友人から、神戸女学院大学の会議室に「真理令爾得自由」という厳谷一六の書があることを知らせてきました。一六は明治の有名な書家で藤林氏の岳父 「厳谷小波」 の父です。クリスチャンではなかったのですが、多分頼まれてこのヨハネ8章32節の聖句を漢語で書いたものであろうと、藤林氏は自書「法律家の知恵」 で述べておられます。
藤林氏は、当初仮名入りの14文字は横書きには無理と思っていました。ところが不思議なことに、その頃、関西に住む友人から、神戸女学院大学の会議室に「真理令爾得自由」という厳谷一六の書があることを知らせてきました。一六は明治の有名な書家で藤林氏の岳父 「厳谷小波」 の父です。クリスチャンではなかったのですが、多分頼まれてこのヨハネ8章32節の聖句を漢語で書いたものであろうと、藤林氏は自書「法律家の知恵」 で述べておられます。
 「イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた、『もしわたしの言葉にうちにとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに自由を得させるであろう』。」(ヨハネ8章31~32節)
「イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた、『もしわたしの言葉にうちにとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理は、あなたがたに自由を得させるであろう』。」(ヨハネ8章31~32節) 愛する子供たちへ
愛する子供たちへ 愛する子供たちへ
愛する子供たちへ
 今回は、程順則(ていじゅんそく)シリーズ第3編です。
今回は、程順則(ていじゅんそく)シリーズ第3編です。 私が、父や母の姿を思い浮かべる時、それぞれに心に浮かぶ4つの姿があります。
私が、父や母の姿を思い浮かべる時、それぞれに心に浮かぶ4つの姿があります。 ユダヤ人の成功する商法には一定の法則があるといいます。
ユダヤ人の成功する商法には一定の法則があるといいます。 日本一長寿の県であるわが沖縄県。
日本一長寿の県であるわが沖縄県。