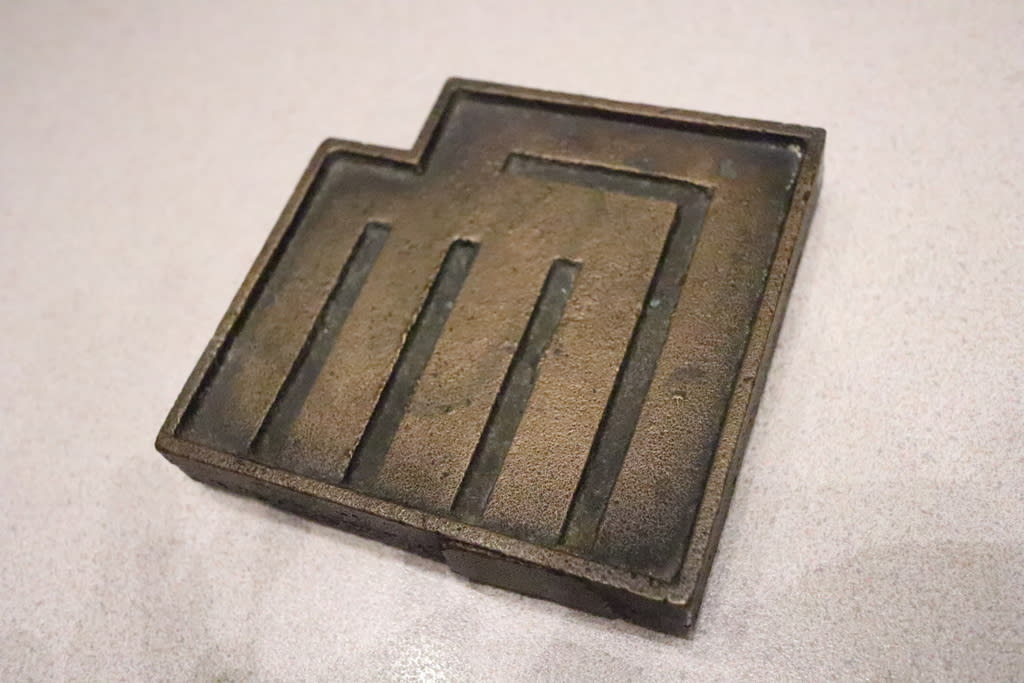2025年大阪万博のシンボルマークが発表されました。
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
最初は「えっ?」と驚いたものの、最近でいう「キモカワ」風、印象的なシンボルマークですね。
「1970年の大阪万博は人生という地図の出発点・再出発点だ」という方はたくさんいて、私もその一人です。老いも若きも、日本人を広い世界へと目を開かせ、目を向けさせてくれた素晴らしいイベントでした。
2025年のシンボルマーク製作者も「太陽の塔」に多大な影響を受け、そのオマージュとしてマークを作成したとおっしゃっています。桜のシンボルマークに似ている(全体の形がですか?)という方もいらっしゃいますね。
さて、家族が2005年愛知万博(愛・地球博:テーマは自然の叡智)に関わっていたこともあって、愛知万博のシンボルマークを再確認してみました。
「モリゾー・キッコロ」のキャラクターが際立っていたので、シンボルマークは覚えていないんですね。確認すると愛称ロゴマークとのバランスは良いのですが、残念ながら単独では印象が薄い気がしました。
自然との共生、それでいいのでしょう。何かが際立つより全てが調和することに価値を持つ、「世界に一つの花」が流行った平成日本の思想の現れでしょう。それはそれで価値あるものだと思います。
「花月」には、大阪万博「日本館」貴賓室の正面でお客様をお迎えした「書」があります。書家の名は安東聖空(1893-1983)、かな書道の第一人者です。
読んでみてください。「花は誇らず その美 見る人にあり」、書体も意味も日本館にふさわしいものです、そして終の棲家になった「花月」にもふさわしい言葉です。
月刊 神戸っ子 連載 神戸秘話 ⑨
海外で働いた経験があります。海外に出ると自分が「日本を知らない」ことがよく分かり、帰国後はまず良き日本人になろうと思いました。まだまだ修行中ですが、国際人への第一歩は英語の習得ではなく、日本人になることだと思います。
この書にある日本的な価値観、外国人がいう「サムライ」的な価値観は日本の誇る美徳でもあります。「みんな違って、みんないい」という意味を軽くとらえない方がいい、誰もがそれぞれの自己を主張すればいいという意味ではなく、人に認められても認められなくても、それぞれが黙々と、おのれの努力を重ねる日本人の美意識をこの言葉に探ることもできます。
いまいち分かりにくければ、同じく神戸ゆかりの作家、山本周五郎の『蕭々十三年』などを読んでみられてはいかかでしょうか。
2025年の大阪万博を個人的にはとても大変楽しみにしています。
そして「その現場で働いてみたいな」と夢見ています。世界・自然・宇宙・人類・体内・・・・・スケールの違いはありますが、構造が似ているように思います。2025年の万博は人間の体内、生命の可能性を探ることがテーマだと思いますが、その中でウィルスとの共生も見えてくるかもしれません。大阪万博、今から期待が持てます!
==============================
【公式】神戸須磨の会席料理ランチ・ディナー │ 味と宿 花月
ホームページ:https://www.suma-kagetsu.com
Facebook:https://www.facebook.com/suma.kagetsu.sakura
【公式】神戸須磨の会席料理ランチ・ディナー │ 味と宿 花月
ホームページ:https://www.suma-kagetsu.com
Facebook:https://www.facebook.com/suma.kagetsu.sakura