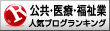「宇宙の外には何がある、と聞かれて大人ははてなと考えこむが子供は即座に夢があると答えた」とある新聞の社説に紹介されていた。
そこで介護制度の外には何がるのでしょうかと考えてみるのも面白い、答えはさまざま。制度の外に希望があるというのはどうだろう、そこには制度には望めないという絶望感が見えるかもしれない。または制度を利用しないからそこに健康・元気があると思うか、ちょっと視点を変えるのも面白い。
そこで介護制度の外には何がるのでしょうかと考えてみるのも面白い、答えはさまざま。制度の外に希望があるというのはどうだろう、そこには制度には望めないという絶望感が見えるかもしれない。または制度を利用しないからそこに健康・元気があると思うか、ちょっと視点を変えるのも面白い。