介護職確保の方法をめぐって議論が盛んらしい、その1つかどうか、介護労働者を1つの法人で雇用するのではなく、ある程度のまとまりで雇用し各法人にいわば派遣するという議論があるのか、どうか。
その際
法人としての特徴はどのように確保するのか
リスクを担保する方法は
最終責任はどこに所属するのか
契約行為の主体と提供主体の乖離は生じないのか
いかがお考え。
この議論の根底には介護労働者の給与の低さ、離職率の高さ、介護労働の不足という問題があり、その対策として議論されているのかも。
介護サービス特に訪問介護の場合
人件費は業務内容×業務時間×時給
業務内容とは排泄介助とか入浴介助とか
業務時間とはその業務内容を遂行するに必要な時間
そして時給
要は人件費の適正化、もしくは労働生産性という議論。
個々の業務内容は変数でなく、業務時間は変数といえる。
つまり、1つの業務にかかる時間は能力によって変数となるわけで、ここに注目すると
労働生産性の向上が見える。
作業の細分化と作業の標準化を行い、その到達度がその労働者の能力、この能力を評価するのが時給。
きわめて単純な事柄、介護労働の生産性という考えがあればいいだけの話。
ですから社福のやり方を踏襲するなといったはず、社協の待遇を模倣するなといったはず、
介護事業者はサービス提供を自分の問題として取り組んで欲しい、いやそんなことは言われなくともやっているという反論があろう、しかし労働生産性という切り口での議論はいかがでしょう。
優良なサービスを提供するという覚悟が欲しい、これもやっているという反論がありますよね、では自社のブランドということに取り組まないのかなぁと思う。
収入の増加方法は先ほどの労働生産性から導きだすことが可能。
業務時間の短縮が時給の高さに反映されるが、業務時間の短縮は業務内容の増加に結びつく、よって介護量の総数が増加、収入が増加する。
介護量の増加とは件数の増加。
ただし移動にかかる時間はロスですから、このロス対策は別途講じなければなりません。
介護職を一箇所に雇用して各法人に割り振るという議論よりこういう議論をしましょうよ、この議論をするようになると裏づけがという議論になるのかな、そうしたらいままでの事業の業務量、時間、を調査したら数値がでてきて議論が前に進む、介護労働の生産性が向上し介護労働者の待遇がよくなる、という思い。
事業者は単に事業を行っているだけでは従業員に対して責任がとれない、経営者は従業員の生活を守る義務がある。
従業員が生活に不安を感じるとそのしわ寄せはお客様に、従業員が幸せの実感を感じるとお客様が喜ぶ。
事業を行う者の責任があるのではないかと思う。自戒の念を込めて。
その際
法人としての特徴はどのように確保するのか
リスクを担保する方法は
最終責任はどこに所属するのか
契約行為の主体と提供主体の乖離は生じないのか
いかがお考え。
この議論の根底には介護労働者の給与の低さ、離職率の高さ、介護労働の不足という問題があり、その対策として議論されているのかも。
介護サービス特に訪問介護の場合
人件費は業務内容×業務時間×時給
業務内容とは排泄介助とか入浴介助とか
業務時間とはその業務内容を遂行するに必要な時間
そして時給
要は人件費の適正化、もしくは労働生産性という議論。
個々の業務内容は変数でなく、業務時間は変数といえる。
つまり、1つの業務にかかる時間は能力によって変数となるわけで、ここに注目すると
労働生産性の向上が見える。
作業の細分化と作業の標準化を行い、その到達度がその労働者の能力、この能力を評価するのが時給。
きわめて単純な事柄、介護労働の生産性という考えがあればいいだけの話。
ですから社福のやり方を踏襲するなといったはず、社協の待遇を模倣するなといったはず、
介護事業者はサービス提供を自分の問題として取り組んで欲しい、いやそんなことは言われなくともやっているという反論があろう、しかし労働生産性という切り口での議論はいかがでしょう。
優良なサービスを提供するという覚悟が欲しい、これもやっているという反論がありますよね、では自社のブランドということに取り組まないのかなぁと思う。
収入の増加方法は先ほどの労働生産性から導きだすことが可能。
業務時間の短縮が時給の高さに反映されるが、業務時間の短縮は業務内容の増加に結びつく、よって介護量の総数が増加、収入が増加する。
介護量の増加とは件数の増加。
ただし移動にかかる時間はロスですから、このロス対策は別途講じなければなりません。
介護職を一箇所に雇用して各法人に割り振るという議論よりこういう議論をしましょうよ、この議論をするようになると裏づけがという議論になるのかな、そうしたらいままでの事業の業務量、時間、を調査したら数値がでてきて議論が前に進む、介護労働の生産性が向上し介護労働者の待遇がよくなる、という思い。
事業者は単に事業を行っているだけでは従業員に対して責任がとれない、経営者は従業員の生活を守る義務がある。
従業員が生活に不安を感じるとそのしわ寄せはお客様に、従業員が幸せの実感を感じるとお客様が喜ぶ。
事業を行う者の責任があるのではないかと思う。自戒の念を込めて。










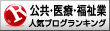
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます