http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BC%E8%B2%B7%E5%8A%9B%E5%B9%B3%E4%BE%A1%E8%AA%AC
より
購買力平価説(こうばいりょくへいかせつ, Purchasing Power Parity Theory ,PPP)とは、外国為替レートの決定要因を説明する概念の一つで、為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決定される、という説である。1921年にスウェーデンの経済学者グスタフ・カッセルが外国為替の購買力平価説として発表した。
購買力平価
基準になるのは、米国での商品価格とUSドルである。
物やサービスの価格は、通貨の購買力を表し、財やサービスの取引が自由に行える市場では、同じ商品の価格は1つに決まる(一物一価の法則)。
一物一価が成り立つとき、国内でも海外でも、同じ商品の価格は同じ価格で取引されるので、2国間の為替相場は2国間の同じ商品を同じ価格にするように動き、均衡する。この均衡した為替相場を指して、購買力平価ということもある。
購買力平価=(1海外通貨単位(基軸通貨であるUSドルが使われることが多い)あたりの円貨額(やその他の海外通貨)で表示した)均衡為替相場=日本での価格(円)÷海外(米国)での価格(現地通貨)
実際には、為替相場が厳密に購買力平価の状態になっていて、かつ2つの貨幣による経済のインフレ、デフレなどがそのまま為替相場に反映され購買力平価の状態が保たれる、ということはないと考えられている。為替相場は購買力の他にも様々な要因によって影響されるためである。但し、購買力平価から大きく乖離した状態が長期的に続くことは難しいと考えられている。
理論上は対USドルだけではなく、どの通貨に対しても購買力平価は算出可能。
相対的購買力平価
為替相場は2国における物価水準の変化率に連動するという考え方。またはそれによって求められる為替相場。 正常な自由貿易が行われていたときの為替相場を基準にして、その後の物価上昇率の変化から求められる。現在はこの求め方が主流となっている。
相対的購買力平価=基準時点の為替相場×日本の物価指数÷海外の物価指数
基準時点については、(日米間の場合)日米ともに経常収支が均衡し、政治的圧力も無く自然に為替取引が行われていた1973年(特に4-6月期の平均=1ドル265円)が選ばれている。
PPPレートの推計
多くの研究者によって推計が試みられているが、国際連合の提唱により国際比較プログラム(ICP)が実施され[1][2]、現在は主にこの結果が利用されている。
ICP事業は主にGDP比較の目的で1969年から実施されており、1993年(1990年を対象とした調査)以降は OECD / Eurostat のみで続けられたが、2005年を対象に再び世界規模の調査が実施され、2007年末に世界銀行より結果が公表された。(ただし2005年のみならず、過去一度も調査に参加していない国も多数ある。)
OECDが発表する2010年における各国通貨の対ドルの購買力平価から計算
アメリカドル 111.39円/ドル
オーストラリアドル 73.64円/豪ドル
ユーロ(フランス) 126.45円/ユーロ
イギリスポンド 170.97円/ポンド
スイスフラン 73.75円/スイスフラン
http://ecodb.net/ranking/bigmac_index.html
※2011年07月25日時点の価格(為替レート: 78.43円/ドル)。
ビッグマック指数(BMI: Bigmac Index)とは、各国の経済力を測るための指数。ビッグマック指数と為替レートを比較して為替相場を推理する一つの指標として用いることができる。イギリスの経済専門誌「エコノミスト」によって考案された。

http://www.gaitame.com/market/indicator_usa.html
指数
http://kabu123fx.blog16.fc2.com/blog-entry-54.html
日本経済関係
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E6%8C%87%E6%95%B0
ビッグマック指数(ビッグマックしすう、Big Mac index)は、各国の経済力を測るための、仮想的な通貨レート。マクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格を比較することで得られる。
「指数」という言葉を使うが、本来の意味の指数(無単位)ではない。単位は各国の通貨単位である。たとえば、日本では「円」、韓国では「ウォン」、中国では「元」を単位とする。当然、単位の異なる各国のビッグマック指数を比較しても、何の意味もない。ビッグマック指数(≒実効レート)が意味を持つのは、一つの国においてのことだ。ある国において、「現在の為替レートと比べて実効レートがどのくらいあるか」という比較でのみ、意味を持つ。
%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB(1980%EF%BD%9E2012%E5%B9%B4)%7C%E5%8D%98%E4%BD%8D%3A%2010%E5%84%84%20US%E3%83%89%E3%83%AB%20%20(c)%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%82%BF%E5%B8%B3&chxt=x%2Cy&chxl=0%3A%7C1980%7C%7C%7C%7C%7C1985%7C%7C%7C%7C%7C1990%7C%7C%7C%7C%7C1995%7C%7C%7C%7C%7C2000%7C%7C%7C%7C%7C2005%7C%7C%7C%7C%7C2010%7C%7C&chdlp=b&chdl=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%7C%E6%97%A5%E6%9C%AC%7C%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%7C%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%7C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%7C%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB&chco=3399CC%2C80C65A%2CFF0000%2CFFCC33%2CBBCCED%2C3399CC&chxr=1%2C147.38%2C15609.697&chd=e%3ABPBUBcBdBpB5CJCVCcCqCpCyC2DGDYDpD0EDEGELEfErE6FFFkF8GbHEHpHtIcI4JS%2CDgEFEiE6FXF8GRGxHkIVJMJ4KOKeKzLRL0MPMHMSM3NNNeOBOuPfQSRKRXQjRhRwSY%2CK7MVM2OBPqQ1R2S.UfWEXZYLZoa-cteEf0h3jxmGokp9rbtfwczn2v5c6h5E7g92..%2CAAAFAIAJAOATAWAaAfAlApArAwA1A8BBBIBOBVBcBkBqBzB7CFCPCaCpCzC5DBDLDV%2CAaAkAwA9BRBlB1CMCnC4DKDpEXFMGFG-H5I2JsKpL3NNOtQmS1VlZNduhYk5pTuJyp%2CBPBUBcBdBpB5CJCVCcCqCpCyC2DGDYDpD0EDEGELEfErE6FFFkF8GbHEHpHtIcI4JS)
http://www.iima.or.jp/research/index.html
国際通貨研究所
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
NHKWORD
http://ronri2.web.fc2.com/
詭弁など
http://pub.ne.jp/bbgmgt/?cat_id=67447
電力関係
http://www.kawase-higai.com/
為替 法律相談
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
政府統計
円の史上最高値は2011年10月31日に記録した75.31円
http://www.ustream.tv/recorded/22091003
20120424 第7回大阪府市エネルギー戦略会議
http://www.nisa.meti.go.jp/stresstest/stresstest.html
ストレステスト
http://www.inss.co.jp/
原子力安全システム研究所
http://www.pref.osaka.jp/attach/15927/00096670/kaitouzenntai.pdf
関電回答
http://www.pref.osaka.jp/attach/15927/00096670/bettenn.pdf
大飯発電所周辺斜面の安定性評価報告書
愛川欽也パックインニュース 2012-04-21 kinkin.tv
愛川欽也パックインニュース 2012-04-28 kinkin.tv
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
より
検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
より
検察審査会法
(昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号)
最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六〇号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 検察審査員及び検察審査会の構成(第五条―第十八条の二)
第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第十九条・第二十条)
第四章 検察審査会議(第二十一条―第二十九条)
第五章 審査申立て(第三十条―第三十二条)
第六章 審査手続(第三十三条―第四十一条の八)
第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等(第四十一条の九―第四十一条の十二)
第八章 建議及び勧告(第四十二条)
第九章 検察審査員及び補充員の保護のための措置(第四十二条の二)
第十章 罰則(第四十三条―第四十五条)
第十一章 補則(第四十五条の二―第四十八条)
附則
http://gogakuru.com/english/phrase/vocabulary/power.html
語学
より
購買力平価説(こうばいりょくへいかせつ, Purchasing Power Parity Theory ,PPP)とは、外国為替レートの決定要因を説明する概念の一つで、為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決定される、という説である。1921年にスウェーデンの経済学者グスタフ・カッセルが外国為替の購買力平価説として発表した。
購買力平価
基準になるのは、米国での商品価格とUSドルである。
物やサービスの価格は、通貨の購買力を表し、財やサービスの取引が自由に行える市場では、同じ商品の価格は1つに決まる(一物一価の法則)。
一物一価が成り立つとき、国内でも海外でも、同じ商品の価格は同じ価格で取引されるので、2国間の為替相場は2国間の同じ商品を同じ価格にするように動き、均衡する。この均衡した為替相場を指して、購買力平価ということもある。
購買力平価=(1海外通貨単位(基軸通貨であるUSドルが使われることが多い)あたりの円貨額(やその他の海外通貨)で表示した)均衡為替相場=日本での価格(円)÷海外(米国)での価格(現地通貨)
実際には、為替相場が厳密に購買力平価の状態になっていて、かつ2つの貨幣による経済のインフレ、デフレなどがそのまま為替相場に反映され購買力平価の状態が保たれる、ということはないと考えられている。為替相場は購買力の他にも様々な要因によって影響されるためである。但し、購買力平価から大きく乖離した状態が長期的に続くことは難しいと考えられている。
理論上は対USドルだけではなく、どの通貨に対しても購買力平価は算出可能。
相対的購買力平価
為替相場は2国における物価水準の変化率に連動するという考え方。またはそれによって求められる為替相場。 正常な自由貿易が行われていたときの為替相場を基準にして、その後の物価上昇率の変化から求められる。現在はこの求め方が主流となっている。
相対的購買力平価=基準時点の為替相場×日本の物価指数÷海外の物価指数
基準時点については、(日米間の場合)日米ともに経常収支が均衡し、政治的圧力も無く自然に為替取引が行われていた1973年(特に4-6月期の平均=1ドル265円)が選ばれている。
PPPレートの推計
多くの研究者によって推計が試みられているが、国際連合の提唱により国際比較プログラム(ICP)が実施され[1][2]、現在は主にこの結果が利用されている。
ICP事業は主にGDP比較の目的で1969年から実施されており、1993年(1990年を対象とした調査)以降は OECD / Eurostat のみで続けられたが、2005年を対象に再び世界規模の調査が実施され、2007年末に世界銀行より結果が公表された。(ただし2005年のみならず、過去一度も調査に参加していない国も多数ある。)
OECDが発表する2010年における各国通貨の対ドルの購買力平価から計算
アメリカドル 111.39円/ドル
オーストラリアドル 73.64円/豪ドル
ユーロ(フランス) 126.45円/ユーロ
イギリスポンド 170.97円/ポンド
スイスフラン 73.75円/スイスフラン
http://ecodb.net/ranking/bigmac_index.html
※2011年07月25日時点の価格(為替レート: 78.43円/ドル)。
ビッグマック指数(BMI: Bigmac Index)とは、各国の経済力を測るための指数。ビッグマック指数と為替レートを比較して為替相場を推理する一つの指標として用いることができる。イギリスの経済専門誌「エコノミスト」によって考案された。

http://www.gaitame.com/market/indicator_usa.html
指数
http://kabu123fx.blog16.fc2.com/blog-entry-54.html
日本経済関係
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E6%8C%87%E6%95%B0
ビッグマック指数(ビッグマックしすう、Big Mac index)は、各国の経済力を測るための、仮想的な通貨レート。マクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格を比較することで得られる。
「指数」という言葉を使うが、本来の意味の指数(無単位)ではない。単位は各国の通貨単位である。たとえば、日本では「円」、韓国では「ウォン」、中国では「元」を単位とする。当然、単位の異なる各国のビッグマック指数を比較しても、何の意味もない。ビッグマック指数(≒実効レート)が意味を持つのは、一つの国においてのことだ。ある国において、「現在の為替レートと比べて実効レートがどのくらいあるか」という比較でのみ、意味を持つ。
http://www.iima.or.jp/research/index.html
国際通貨研究所
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
NHKWORD
http://ronri2.web.fc2.com/
詭弁など
http://pub.ne.jp/bbgmgt/?cat_id=67447
電力関係
http://www.kawase-higai.com/
為替 法律相談
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
政府統計
円の史上最高値は2011年10月31日に記録した75.31円
http://www.ustream.tv/recorded/22091003
20120424 第7回大阪府市エネルギー戦略会議
http://www.nisa.meti.go.jp/stresstest/stresstest.html
ストレステスト
http://www.inss.co.jp/
原子力安全システム研究所
http://www.pref.osaka.jp/attach/15927/00096670/kaitouzenntai.pdf
関電回答
http://www.pref.osaka.jp/attach/15927/00096670/bettenn.pdf
大飯発電所周辺斜面の安定性評価報告書
愛川欽也パックインニュース 2012-04-21 kinkin.tv
愛川欽也パックインニュース 2012-04-28 kinkin.tv
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
より
検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
より
検察審査会法
(昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号)
最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六〇号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 検察審査員及び検察審査会の構成(第五条―第十八条の二)
第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官(第十九条・第二十条)
第四章 検察審査会議(第二十一条―第二十九条)
第五章 審査申立て(第三十条―第三十二条)
第六章 審査手続(第三十三条―第四十一条の八)
第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等(第四十一条の九―第四十一条の十二)
第八章 建議及び勧告(第四十二条)
第九章 検察審査員及び補充員の保護のための措置(第四十二条の二)
第十章 罰則(第四十三条―第四十五条)
第十一章 補則(第四十五条の二―第四十八条)
附則
http://gogakuru.com/english/phrase/vocabulary/power.html
語学















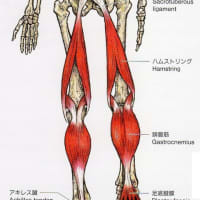




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます