祈祷の時間に、ロザリオを手に静かに瞑想する老人の姿。
その老修道士が、杖を手に、よちよちと僧房に入ってくる。
木のテーブルに手を付き、その脇にある籐の椅子をぎこちなくまさぐり、
そしてようやく腰をかける。
閉じられた両眼、湿ったまつ毛、たれた目じり、深いしわ・・・
老いた修道士の顔のアップが、しずかに映し出される。
暗い室内で、窓から差し込む日の光に照らし出される、
白く長い眉毛ショット…。
そして顔のアップ。
口角がわずかにあがり、微笑んだような穏やかな表情。
言葉での説明がなくても、この老修道士が盲目であることを
見ているものは知る ― いや、知らされるのである。
映画の後半部で、この老修道士だけが、言葉を発する。
『わたしは死を恐れない、というのも、死ぬことで
神にお目にかかり、
一緒になることができるからである。
過去のことや現在のこと、それは人間の考えることである、
しかし神においては現在しかない。
全知全能の神は、つねにわれわれの安寧を願っているはずである。
わたしが盲目であるのも、神がわたしに与えてくださった恩恵である。
それによって、わたしは安寧をえているのだから』
この老修道士のいう、『安寧』とは、英語では wellbeing である。
「幸福」という意味もあるが、いわゆる、happiness と wellbeing には
微妙にして大いなる相違がある、とわたしは思う。
ハッピー、というとき、人は「五感の幸せ」や「満足」を言うのだろう。
つまり、楽しい、うれしい、という刹那的な幸せである。
しかし、ウェルビーイング、という言葉は、人が精神的に恒久的に
満足な状態をいうのだろう、とわたしは思うのである。
この老修道士がいう、神がわれわれにもたらそうとしていること、
それは、生きていける希望を持ち続ける勇気を与えてくれる
精神状態なのではないか。
つまり、われわれは自分の意思で生きているのではなく、
生かされていることを知ることによって、心の安寧を得る、
そういうことではないか。
この老修道士の部屋は廊下の隅の、角部屋である。
窓からは外の光が差し込んでくるが、彼には見えない。
しかし窓の下には、旧式だが、大きなラジエータが置かれている。
盲目の老人には鉄製のストーブは危険だし、
薪をくべることもできない。だから電気あるいはガス暖房である
ラジエータを設置してある、
そういう目に見えない配慮があるように思われる。
礼拝堂では、彼の脇にいる中年の修道士が、
祈りのあいだの、立ったり座ったりの動作などを助け
そして、長い廊下を付かず離れずともに歩いて
老修道士が僧房に入るまで、手をかしてあげている光景が
なにげなく映し出されている。
こういう光景は、映画を一度見ただけでは見逃してしまうことだろう。
一日の大半を、独房のような僧房で一人で過ごす修道士たちも
実際には「孤独」ではない。
神のために祈りをささげる人生、しかしそれはやはり一人っきりでは
不可能な行為なのである。
この白い眉毛の老修道士は人生の大半をこの修道院で
過ごしてきたのだろう。
そして先輩たちを何人も看取ってきたのだろう。
今は自分が神の御許に召されることを、最高の幸せ、
として待ち望んでいる。
映画ではもう一人、老いた修道士を紹介している。
上半身半裸の、やせ細った老人の姿が大写しされる。
まだ若い修道僧が、老人の黄色がかった皮膚に軟膏を塗り、
ていねいにマッサージしている。
二人とも無言である。
おそらくその老人は不治の病に冒され、死期が近づいているのだろう。
その老修道士の顔のアップが、映画の最後のほうに映し出される。
じっとカメラを見つめる老修道士のまなざしは、おだやかで、そして
静かに笑みさえ浮かべてみせるのだ。
しかし、かつては80人ほども修道士がいたこの
グランド・シャルトルーズ修道院は
今では15人ほどに減ってしまっている、という。
厳しい戒律のカルトゥジオ会、というが、この
グランド・シャルトルーズ修道院での修道士たちの
表情を見ると、決して戒律を強いられてこなしているようには
見えないのだ。
印象に残ったシーンの一つは、冬のある日曜日の午後の
自由時間である。
若い修道士たちが、嬉々として雪のつもる山肌を
話しながら歩いていく。
修道院の建物を見下ろす急なスロープの上まで
あの長い僧服のまま歩いていき、
そしてしりもちをつくようにしてスロープを滑り降りる。
大きな笑い声が雪山にこだまする。
なんて無邪気なんだろう。
そう、無邪気、という言葉、それが映画に映し出される
修道士の行動や表情を端的に表している、と思う。
わたしが手に入れたDVDは、映画のほかに、ボーナスとして
映画では見られない映像画像や、資料を満載したDVDが
もう一枚ついている。
その中にある写真の一枚に、修道院の雪に覆われた裏庭に
立っている、粗末な十字架の列がある。
おそらく、この修道院で半生を祈りに捧げ、
心安らかにこの世を去って行った修道士たちの
墓なのであろう。
彼らは結婚もせず、子供も持たず、
世俗的な一般人の幸せな人生とは
かけ離れていたかもしれない。
でもだからこそ、世俗的な一般人の苦悩を
知らず、ただひたすら神への愛を貫くことで
幸せであったのかもしれない。
ところで、そのボーナスDVDでは、真夜中の聖務の模様を
聖歌楽譜および聖書の大写しの静止画像とともに、
音声のみで約一時間にわたって聞くことができる。
ラテン語とフランス語であるが、真夜中の祈り
臨場感たっぷりで、ありがたいことである。
また、なにより興味深かったのは、グランド・シャルトルーズ修道院の
歴史あるリキュールの製造に関する映像が見られることである。
130種の薬草や香草をミックスして、それにアルコールを加え、
蒸溜し商品化し、それを販売することで利益を得て、
修道院の経済は成り立っているのである。
もちろん、蒸留酒にする過程は、既存の企業にまかせているが、
薬草、香草の調合の割合は、修道院でも三名の修道士のみが知る
「企業秘密」だそうである。
シャルトルーズ、というリキュール酒である。
中世においては修道士のみが、おそらくささやかな楽しみとして
たしなんでいたのであろうが、それがやがて、薬酒、として
国王からも認証され、市販されるようになった、という。
カルタジオ会は、キリスト教の伝道を目的としないから、
信徒をもたない、つまり、いわゆる日本でいう「檀家」ではない。
篤志家からの喜捨はあるのかもしれないが、やはり
経済的に存続していくには、いろいろと知恵をめぐらせなければ
ならないのだろう。
このリキュールが今後も売れ続け、このアルプスのふもとの
修道院で、神への祈りにのみ専念する修道士たちの生活が
今後も続いていくことを、祈るばかりである。
というわけで、映画を何度も繰り返し見ながら、
聖書の引用など、深く感銘することもたびたびであったが、
そういうことについては、また折に触れて書いていくことにして、
とりあえずは、この映画のご紹介を終えたいと思う。
ただ最後に、端的にわたしが感動したことを申し上げておく。
「はじめに言葉ありき」とはヨハネの福音書における
有名な言葉であるが、この「言葉」とは神の言葉である。
だから、その「言葉」とは人間が生み出した言葉では
決してないのである。
どのようにして「神の言葉」を見出すか。
それは沈黙、あるいは静寂のなかから現れてくる言葉を
待たなければならない。
まず言葉があるのでない。まず沈黙があるのだ。
それを破るのが神、である。その言葉を見出すことが
信仰である。
あらゆるものを捨てることができなければ、
わたしの弟子にはなれない・・・。それは財産のみならず
人間の言葉をも捨てることである、完全に無私に
なることである、とわたしはこの映画を見て感じた。
言葉で理解できないもの、それが神である。
頭で理解しようとしても、決して理解させてくれないのが
神である。
DVDの中で、醸造会社の重役が言った言葉。
修道士たちは神に祈る毎日の中で、知識と科学を
見出したのである。
欧州における近代における科学の発達で、それまでの
キリスト教の「神」の概念は大きく変わった。
「神は死んだ」とニーチェは言った。それでも
全知全能の神を信じ、無私に祈りを捧げる修道士たちに
とっては、人間が発見する新たな真実は、すべて
神からの恩寵なのであろう。














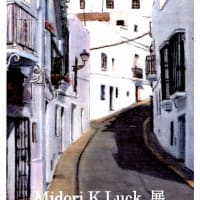





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます