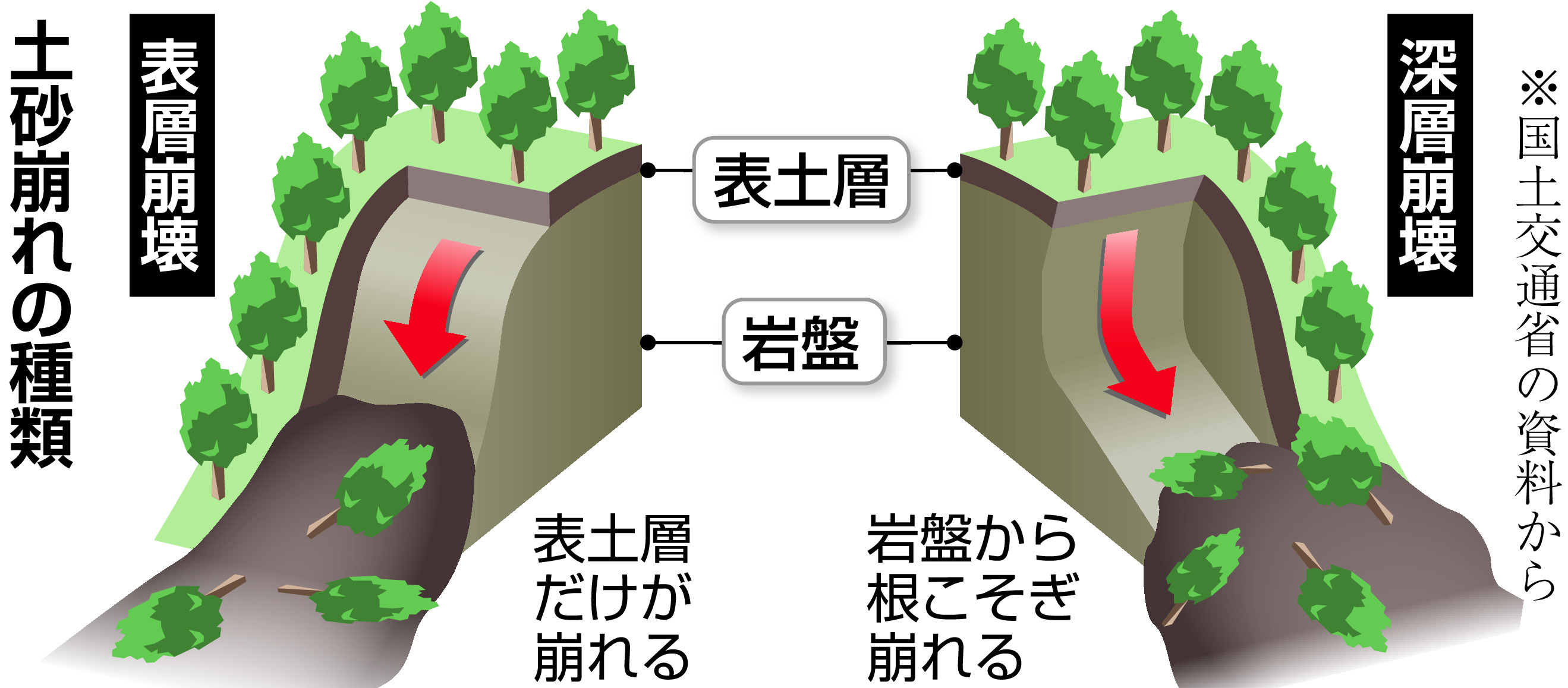電子マネーをだまし取る特殊詐欺が続発している。うその話を持ち掛けてコンビニなどで購入させ、利用番号を聞き出す手口だ。県警が今年把握した被害は47件(28日時点)に上り、前年同期から25件増加した。一方、犯人が県内を訪れ、被害者から現金を受け取る手渡し型は1件だけ。新型コロナウイルスの感染拡大で詐欺グループが広域移動を控え、「非接触型」にシフトしたとみている。
県警によると、特殊詐欺全体の被害は70件。電子マネーの手口は7割近くを占め、前年同期の4割強を大きく上回った。他は▽金融機関からの振り込み 18件▽コンビニ端末で送金 2件▽郵送 1件―だった。
19年に23件、20年に19件を確認した手渡し型が大幅に減ったのは、コロナ禍が背景にあると推測する。
捜査幹部は「詐欺グループの現金受け取り役が県をまたぐ移動を控えている可能性がある。人流がないと犯人は人混みに紛れにくい。感染リスクを踏まえ、対面を避けたい意識も働いたのだろう」と話す。
電子マネーを悪用した手口は「パソコンのセキュリティー対策が必要」「高額の当せん金が当たった」といった作り話から始まる。
犯人側はパソコン画面に偽の警告を表示させるほか、架空の内容のメールを送って連絡を求める。その後、実在企業を名乗る人物が携帯電話で手数料などの支払いを要求。コンビニのレジで電子マネーカードを購入させ、カード裏に記された英数字のプリペイド番号を伝えるよう指示する。
振り込み、手渡しは一度で数十万~数百万円の現金を詐取されることが多い。電子マネーの被害は数万~数十万円規模が多いものの、だまされていると気付かず深刻化するケースもある。今月中旬は大分市内の60代女性が約80回購入し、計400万円分を失った。
県警は過去10年間、電子マネー詐欺犯の摘発に至っていない。匿名性の高いサイバー空間で取引され、利用番号をたどっても容疑者に行きつかないという。
「姿を現さない犯人の追跡は難しい」と別の捜査幹部。目撃情報や防犯カメラ映像を頼れず、現金の受け取り場所などで警察官が待ち構える「だまされたふり作戦」も通用しにくい。
特殊詐欺事件で摘発したのは1~5月で14人にとどまり、前年同期(29人)から半減。実行役は口座から現金を引き出した1人だけで、13人は通帳を譲り渡すなどの「助長犯」だった。
被害を防ぐには、電子マネーを扱うコンビニの協力が欠かせない。
県警は複数回、高額購入をする客がいたら、詐欺を疑って利用目的を尋ねるよう各店舗に求めている。7月1日から県内全てのコンビニ約500店を巡回し、積極的な声掛けを促す。
安全・安心まちづくり推進室の大熊建国(たてくに)室長(52)は「被害は水際で阻止できる。県民の財産を守るため、協力をお願いしたい」と話している。大分合同新聞