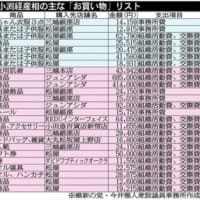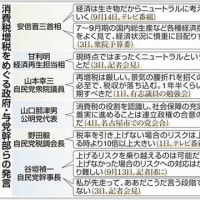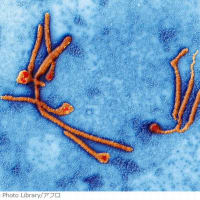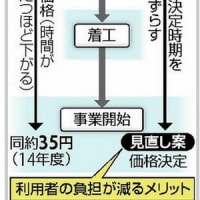http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140604568.html へのリンク
2014年6月4日(水)21:03
産経新聞
動画投稿サイト「FC2」のライブ配信サービスで、性行為の映像を配信したとして、京都府警は6月3日夜、公然わいせつの疑いで、大阪市北区豊崎の自称ライブチャット配信業、松本隆志容疑者(30)と、兵庫県宝塚市の短大生の女(19)を現行犯逮捕した。京都府警によるといずれも容疑を認め、松本容疑者は「有料配信で稼げるお金が多かった。(FC2は)海外のサーバーなので大丈夫だと思った」と供述している。違法なライブ配信を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕するのは全国初だという。
松本容疑者はインターネット上で「帽子君」を名乗り、複数の女性との性行為の映像を配信。平成25年12月から約3千万円の売り上げを得ていたという。
2人の逮捕容疑は3日夜、大阪市北区の松本容疑者の自宅マンションで、性行為中の映像をインターネットで配信。自身の下半身を露出し、不特定多数に閲覧可能な状態としたとしている。
警察によると、松本容疑者は、自宅マンションにカメラを設置した撮影用の部屋を複数用意しており、知人がスカウトした女性との会話や性行為の映像を、女性と同意の上で、ライブ配信。一部を有料配信としており、平成25年12月~26年6月で約3千万円の入金があったという。松本容疑者は「多いときで1日数十万の入金があった」と供述している。
松本容疑者は「帽子君ワールド」というブログを運営し、配信スケジュールなどを書き込んでおり、平成25年秋ごろ、捜査員がサイバーパトロールで発見。捜査員がライブ配信中であることを確認した上で、撮影現場に突入し、現行犯逮捕した。
2人のほか、同様にFC2を使って性行為や自慰行為の映像をライブ配信したとして、三重、高知、島根、山口の各県警は3~4日、同容疑で30~50代の男女4人を逮捕した。
「10リツイートで晒す」自分の裸を投稿する10代少女たちの“異様”http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140605520.html へのリンク
2014年6月5日(木)12:03
産経新聞
投稿サイトの「ツイッター」で、18歳未満とみられる少女らが自身の裸体を撮影し、投稿する行為が後を絶たない。自らの発言を追う「フォロワー」の獲得が目的のようだ。児童買春・児童ポルノ禁止法に抵触するが、犯行の主体が児童本人であるため、捜査当局も摘発には積極的ではないといわれる。ただ、軽い気持ちで投稿したログ(記録)は瞬く間に拡散するだけなく、半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”となっていく。少女らの将来を台無しにしないためにも予防教育が欠かせない。
「10リツイートいったら晒(さら)す」
たまたま他人のツイートを閲覧していると、こういうつぶやきが画面に表示されてくる。発信源のユーザーをみてみると、顔にあどけなさを残す10代とみられる少女が自分の胸を撮影し、黒塗り修正した写真を投稿していた。たちまち複数のフォロワーがリツイート(同じ内容をつぶやくこと)。少女は反響に満足しながら“約束通り”無修正の画像を投稿した。ツイッターにはこうした投稿が横行している。
リツイートの多い投稿は必然的に人目に触れ、注目度が高まる。国立情報学研究所の岡村久道・客員教授(情報学)は「目立ちたいという心情から行われ、実際に願望を満たせる環境になってしまっている」と指摘する。手軽に画像の撮影・送信ができるスマートフォン(高機能携帯電話)の普及に伴い、類似の事例は後を絶たない。
これらの投稿は、児童買春・児童ポルノ禁止法で禁じた、製造、公然陳列に該当する。ただ、児童福祉犯罪に詳しい奥村徹弁護士は「同法では児童はあくまで被害者の立場を想定している。捜査当局には同法で児童を摘発したくない葛藤があるとみられ、なかなか踏み切れないことが多い」と説明する。
同法をめぐっては平成21年に、自分の下半身を携帯電話で撮影しメールで男に送信した女子高校生3人が神奈川県警に摘発された事例があるが、金銭目的で悪質性が高かったことが判断材料になっており、児童側の摘発はほとんど行われていない。
一方、奥村弁護士によると、これらの画像を18歳未満と認識してリツイートしたり、「胸を見せて」などの要求をしたりしたフォロワーが、同法違反に問われる可能性は高いという。
ツイッター社は、利用規約で児童ポルノに関するコンテンツを禁止。独自に違法投稿の調査を行い、発見次第アカウント凍結の措置をとっているが「最も有効な方法はユーザーからのリポート」(広報担当者)といい、人の目に触れる前の発見は難しいのが実態だ。
実際、違法投稿した少年少女には、別の投稿で素顔の写真を掲載していたり、学校の制服を着ている場合もある。入力した住所、氏名、連絡先などの個人情報は設定次第で誰でも閲覧可能で、人物の特定は比較的容易のため、のちのちの進学や就職に影響する可能性がある。
スマートフォン(高機能携帯電話)を使っている場合は、GPS(衛星利用測位システム)機能で位置情報が分かる。パソコンでもネット上の住所「IPアドレス」で大まかな位置を把握でき、自宅だと住所が漏れることあるため、脅迫など事件に巻き込まれることもある。
岡村氏は「リスクを十分に認識させるため、児童に対して違法投稿をさせない教育、啓発を、家庭や学校で進めることが重要だ」と訴えている。