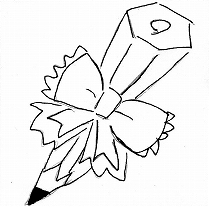本文詳細↓
お酒であれば、カクテルでもワインでもビールでもウイスキーでもなんでも平気で飲むくせに、こと食になると、アダムの好みは年頃の人間の女の子と大差ない。けど残念、僕は辛党だった。
「あ、こらっ! そっちではないぞトルル! あっちじゃ! フルーツとパンケーキの楽園(パラダイス)へ行くにはあっちの道を行かねばならぬぞ!」
僕の頭の上に居場所を移したアダムはそう言って僕の髪を引っ張ったけど、無視した。そう思うんなら、自分で歩けばいい。
「だからそっちではないと言っておるだろおぉぉ!」
安くて温かくて美味しい食事というのは、やっぱりいつでも幸せな気分にしてくれる。おまけに、考案中の新メニューというのも食べさせてもらえて、僕は満足顔で食事処を出た。一方、僕の肩の上で器用に腹這いになっているアダムは、口を開けて外の空気をいまだ熱冷めやらぬ口内に送りつつ、苛立った声で言った。
「おぬしのその強靭な舌だけは、何年経っても理解できぬわ」
そんな恨みがましい目で見られても、どんな味か聞きもせずに口に入れたアダムの自業自得だと思う。
若い人間の店主がくれた小ぶりの肉団子だった。噛んだとたん、熱い肉汁と一緒に指先まで痺れが伝わるような辛みという名の痛みが、口の中いっぱいに広がった。僕は美味しいと思ったんだけどな。