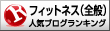この状況のなか、政治の力、そして政治家の思考回路がどうなっているのだろう、というようなことに、つい思いが巡る。
緊急事態宣言とならび提示された補償案で、日本政府は困窮のレベルに線引きをしようとする。納得がいかない。
ハンガリーでは首相権限で緊急事態宣言が無期限延長が出来るようになったという。イスラエルでは議会閉鎖まで起きそうになったが阻止されたと知った。
民主主義は大丈夫だろうか。みんなが感染と失業の恐怖にさらされる現在について、力をもつ人たちの本音はどうなのだろう。不安になる。
かたや、コロナ対策の一環としてベーシックインカムの導入を意識し始めている政治家がアメリカやイギリスやスペインなどに出てきているという報道が見られ、驚いた。UBIがどの程度の実現性や影響があるかはまだわからないけれど、この状況下だからこそ意味ある政治実験になると思う。
僕が教えているダンスの一つにオイリュトミーというのがあるが、これを創案したルドルフ・シュタイナーは、芸術や教育の実践とならんで社会や政治に対する意見が多数あることでも知られてきた。その思想の中で僕は「経済の友愛化」という考え方に興味をもってきた。お金とは何か、ということを考えずにいられないからだ。
いかにしてお金を稼ぐか、ということにアタマを悩ませてきたが、お金の役割は何なのか、ということを、もっと考えなければならない。いま経済は競争の道具になっているが、元々は、お金というものは助け合いのための発明だったのではないかと僕は想像する。
いまここにきて、UBIの可能性も含め、このコロナ状況は、友愛と経済の関係をさぐってゆく通過点にもなるのではないかと、思えてならない。政治と私たちの関係に加え、私たち一人一人が経済に対する考え方を変えてゆくチャンスかもしれない。
非常事態を背景に、各国が、そして各国それぞれの国民一人一人が、政治と経済と国民の関係をめぐって、何かしら考えざるを得ない日々がめぐっている。新しい社会について真剣に考える時期が突然に来た、そう思えてならない。地球規模で、だれもが同じことに困り、同じことを解決しようとしている。
人と人は、いかに助け合うことが出来るか。というミッションを世界中が共有してゆくことになると思う。
危機の時代には友愛精神が試されるにちがいない。そして、おなじくらいに、危機の時代は全体主義を生みやすい。
ひじょうにびみょうな状況を、僕らは漂っているのかもしれない。
ウイルス状況のなかで、国民の声を、世界の声を、人間の声を、政治家はどのような思いで聴いているのだろうか。
国家と国民と経済の関係については、どのみち変化を考えなければならない地点に来ていたのかもしれない。もう、資本主義の競争社会のままでは未来は明るくないのでは、なんてことも、とても思う。
いま僕らが困り果てながら考えていることすべてが、未来を構築する導線になるのではないか、とも思える。
新しい時代は、いつも困難から生まれてきた。
lesson 櫻井郁也ダンスクラス
stage 櫻井郁也/十字舎房:ダンス公演情報