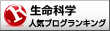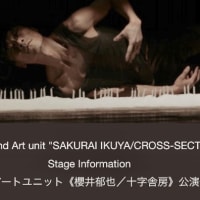【全身を鼓膜に】
2/11は「音楽オイリュトミー」のレッスンを行いました。この日の参加者は6名。
音の響きを全身に反映し、音楽と一心同体になるための練習です。
オイリュトミーは響きの身体芸術と呼ばれている通り、音楽や言語の響きを全身運動に置き換えるダンスです。そのメソッドは、全身を鼓膜のようにすることでもあります。言語オイリュトミーといって、ことばを踊る時には全身を喉のように呼吸/発声器官として見立て、音楽オイリュトミーでは体を楽器のように見立てて共振したりエネルギーを放射したりします。つまり、オイリュトミーでは身体を共鳴体として捉えるわけです。
この日はまず、ピアノを囲んで輪になってもらいました。そして、僕が弾く音の高さ低さを感じ、即座に全身のアップダウンでシンクロしてゆく練習。次に音階(ドレミファ・・・)に対応する「型」を用いた「聴音」、つまり今鳴った音を聴き分ける練習。運動しながら音感をつけてゆく練習で、うまく動けたときは笑顔がこぼれ、わからないときは「え~っ、もう一回弾いてくださ~い」と悲鳴が。低いド(C)の音は地面に力を注ぎ込むように、一音上がってレ(D)の音は重心もふわりと上げて翼を開くように両腕を解放、などなど・・・。エネルギーの放射やゆらぎを象徴した「型」の数々は美しく、動いていて気分がスッキリします。また、この練習を根気よく重ねてゆくと、音がカラダの中で光のスペクトルみたいに変容する体験が始まります。そうすればしめたもの。身体と音感が出来てきた証拠です!
基礎練習のあとは、楽譜を配って、今日から踊る曲の解説、譜面の読み方、振付けを少し進行。およそ3ヶ月で一曲仕上がるペース。いまこのクラスは初歩をやっているので、まずはハ長調、音楽のイロハというところ。五線譜の読み方も音の名前も全部復習しなおしながら自分たちの踊る音楽を理解してゆきます。小学生のころみたいに・・・。それで選んだ曲は、モーツァルト作曲の「キラキラ星の主題による12の変奏」という曲です。誰しも親しみのある「キラキラ星」の唄が、創意工夫によって見事な音の万華鏡に変化してゆくという、モーツァルトの絶品。音楽の魔術というか、変身変容のおもしろさを全身体験してほしくて選びました。この曲を踊ることを通じて、踊り心とクラシック音楽の基本的な素養を身につけたいと思います。(PS:金曜のダンスクラスや火曜の舞踏クラスでは現代の斬新な音楽を用いるのに対して、このクラスではバロック・古典派・ロマン派の音楽が多いです)
さて、動いたり、唄ってみたり、僕の弾くピアノの鍵盤をじっと眺めてみたり。踊るだけでなく音楽を丸ごと学ぶのが、オイリュトミー独特の練習法です。一曲踊れるようになった時には、その曲の楽譜も精神もちゃんと理解できるように。
そしてピアニストにも加わってもらい、あわせ稽古。流れる音楽に乗って、踊り踊って・・・。だんだんと体が温まるにつれて集中力も高まり、一緒に踊っている人同士の息が合ってゆきます。ピアニストも含め、みなで一つの呼吸を共有しているような感じです。このような状態はオイリュトミー独特の感触で、僕らは「ひびく」と呼んでいます。「もっと、ひびいて!」と言いながら練習を進める時、それは単にたくさん動くということではなく、より深く結びついてゆこうとするようなバランス感覚の高め方を磨くわけです。
【魂の呼吸】
ところで、「バランス感覚」というのは、シュタイナーの「12感覚論」に依拠する用語で、多様さのなかに調和できるスタンスをキャッチしてゆく感性のことですが、音楽や舞踊には古来この感性を呼び覚ますメカニズムが宿っていると言われています。伝説のダンサー、イサドラ・ダンカンの主張する「テレプシコラ」という概念もこれに近しい気がします。踊りに親しみ、踊りの稽古を重ねることは、周囲と自分とを溶け合わせる努力を重ねること。そして、競争を放棄し、あるがままの存在の仕方を受け入れてゆく修行でもあると思います。それはまた、実社会では、人と人が互いに感じ合って結びついてゆく技術にもつながるような気がしてなりません。このような方向性を非常に重視した練習法や人間についての思索が、オイリュトミーの稽古法には凝縮されています。
現在ほとんどの芸術は自分自身の内面を他者に伝えるようになっていますが、オイリュトミーは逆の視点をもっていて、ひたすら他者の内面を理解しようとして踊ります。(これを、創案者シュタイナーは「客観の舞踊」と表現し、ニーチェの言葉を借りるならば「アポロン的な態度」の踊りと言えます)僕は自分の意見を言うことが先行してしまい、他の人の言葉にじっと耳を傾けることが苦手でした。それで、18歳から29歳までオイリュトミーの稽古を習い、さまざまな言葉や音楽にどっぷり全身を浸す体験を重ねるうち、ずいぶんアタマもココロも丸くなっていった気がします。ひたすら聴いて正確に反応する。これは他者の心に自分の肉体を開くということでもあるのかもしれません。単純なことかもしれませんが「いろんな人がいて、いろんな魂があって、世界が成り立っている。多様さのなかに生きている一人が私なんだ。」ということが、じわっと感じられるようになりました。それは、「泣いてもいい、笑ってもいい、怒ってもいい」という、「自分もまた多様であって良い」という、自己存在への許しにもつながっているような気がします。だから喜怒哀楽がハッキリして、メリハリのある人間に少しだけ近づけた気がします。それで、アーティストとして活動する今も、クラスを組んでオイリュトミーの稽古を楽しんでいるのだと思います。オイリュトミーは、単なる踊りの訓練ではなくて、人間らしさを恢復するための「魂の呼吸法」なのではないかと、いまあらためて感じています。
初心者よりメンバー募集中クラス参加方法・問合せなど
2/11は「音楽オイリュトミー」のレッスンを行いました。この日の参加者は6名。
音の響きを全身に反映し、音楽と一心同体になるための練習です。
オイリュトミーは響きの身体芸術と呼ばれている通り、音楽や言語の響きを全身運動に置き換えるダンスです。そのメソッドは、全身を鼓膜のようにすることでもあります。言語オイリュトミーといって、ことばを踊る時には全身を喉のように呼吸/発声器官として見立て、音楽オイリュトミーでは体を楽器のように見立てて共振したりエネルギーを放射したりします。つまり、オイリュトミーでは身体を共鳴体として捉えるわけです。
この日はまず、ピアノを囲んで輪になってもらいました。そして、僕が弾く音の高さ低さを感じ、即座に全身のアップダウンでシンクロしてゆく練習。次に音階(ドレミファ・・・)に対応する「型」を用いた「聴音」、つまり今鳴った音を聴き分ける練習。運動しながら音感をつけてゆく練習で、うまく動けたときは笑顔がこぼれ、わからないときは「え~っ、もう一回弾いてくださ~い」と悲鳴が。低いド(C)の音は地面に力を注ぎ込むように、一音上がってレ(D)の音は重心もふわりと上げて翼を開くように両腕を解放、などなど・・・。エネルギーの放射やゆらぎを象徴した「型」の数々は美しく、動いていて気分がスッキリします。また、この練習を根気よく重ねてゆくと、音がカラダの中で光のスペクトルみたいに変容する体験が始まります。そうすればしめたもの。身体と音感が出来てきた証拠です!
基礎練習のあとは、楽譜を配って、今日から踊る曲の解説、譜面の読み方、振付けを少し進行。およそ3ヶ月で一曲仕上がるペース。いまこのクラスは初歩をやっているので、まずはハ長調、音楽のイロハというところ。五線譜の読み方も音の名前も全部復習しなおしながら自分たちの踊る音楽を理解してゆきます。小学生のころみたいに・・・。それで選んだ曲は、モーツァルト作曲の「キラキラ星の主題による12の変奏」という曲です。誰しも親しみのある「キラキラ星」の唄が、創意工夫によって見事な音の万華鏡に変化してゆくという、モーツァルトの絶品。音楽の魔術というか、変身変容のおもしろさを全身体験してほしくて選びました。この曲を踊ることを通じて、踊り心とクラシック音楽の基本的な素養を身につけたいと思います。(PS:金曜のダンスクラスや火曜の舞踏クラスでは現代の斬新な音楽を用いるのに対して、このクラスではバロック・古典派・ロマン派の音楽が多いです)
さて、動いたり、唄ってみたり、僕の弾くピアノの鍵盤をじっと眺めてみたり。踊るだけでなく音楽を丸ごと学ぶのが、オイリュトミー独特の練習法です。一曲踊れるようになった時には、その曲の楽譜も精神もちゃんと理解できるように。
そしてピアニストにも加わってもらい、あわせ稽古。流れる音楽に乗って、踊り踊って・・・。だんだんと体が温まるにつれて集中力も高まり、一緒に踊っている人同士の息が合ってゆきます。ピアニストも含め、みなで一つの呼吸を共有しているような感じです。このような状態はオイリュトミー独特の感触で、僕らは「ひびく」と呼んでいます。「もっと、ひびいて!」と言いながら練習を進める時、それは単にたくさん動くということではなく、より深く結びついてゆこうとするようなバランス感覚の高め方を磨くわけです。
【魂の呼吸】
ところで、「バランス感覚」というのは、シュタイナーの「12感覚論」に依拠する用語で、多様さのなかに調和できるスタンスをキャッチしてゆく感性のことですが、音楽や舞踊には古来この感性を呼び覚ますメカニズムが宿っていると言われています。伝説のダンサー、イサドラ・ダンカンの主張する「テレプシコラ」という概念もこれに近しい気がします。踊りに親しみ、踊りの稽古を重ねることは、周囲と自分とを溶け合わせる努力を重ねること。そして、競争を放棄し、あるがままの存在の仕方を受け入れてゆく修行でもあると思います。それはまた、実社会では、人と人が互いに感じ合って結びついてゆく技術にもつながるような気がしてなりません。このような方向性を非常に重視した練習法や人間についての思索が、オイリュトミーの稽古法には凝縮されています。
現在ほとんどの芸術は自分自身の内面を他者に伝えるようになっていますが、オイリュトミーは逆の視点をもっていて、ひたすら他者の内面を理解しようとして踊ります。(これを、創案者シュタイナーは「客観の舞踊」と表現し、ニーチェの言葉を借りるならば「アポロン的な態度」の踊りと言えます)僕は自分の意見を言うことが先行してしまい、他の人の言葉にじっと耳を傾けることが苦手でした。それで、18歳から29歳までオイリュトミーの稽古を習い、さまざまな言葉や音楽にどっぷり全身を浸す体験を重ねるうち、ずいぶんアタマもココロも丸くなっていった気がします。ひたすら聴いて正確に反応する。これは他者の心に自分の肉体を開くということでもあるのかもしれません。単純なことかもしれませんが「いろんな人がいて、いろんな魂があって、世界が成り立っている。多様さのなかに生きている一人が私なんだ。」ということが、じわっと感じられるようになりました。それは、「泣いてもいい、笑ってもいい、怒ってもいい」という、「自分もまた多様であって良い」という、自己存在への許しにもつながっているような気がします。だから喜怒哀楽がハッキリして、メリハリのある人間に少しだけ近づけた気がします。それで、アーティストとして活動する今も、クラスを組んでオイリュトミーの稽古を楽しんでいるのだと思います。オイリュトミーは、単なる踊りの訓練ではなくて、人間らしさを恢復するための「魂の呼吸法」なのではないかと、いまあらためて感じています。
初心者よりメンバー募集中クラス参加方法・問合せなど