こんにちは♪
昨日、友だちのコメントの中で、
「認知症の予防はできないのか?」という
質問がありました。
私はこのブログを立ち上げた時、
生活習慣病と認知症とは
何らかの因果関係があるように考え、
「お袋の認知症日記」をカテゴリの中に入れました。
専門医師ではないので、
生活習慣病と認知症の関わりを
このブログで記したことはありませんが、
専門医の友人から追記として
認知症の予防としては、
生活習慣病の予防、老化の対応が必要
と仰っています。
少子高齢社会に入っている現在、
私も含めて、認知症を発症する人は
今後も増える一方でしょうから、
自分たちができることがあれば、
今から対策しておくべきではないでしょうか。
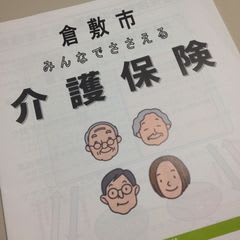
下記は先日の専門医の友人からのコメントです。
認知症の「予防」という面からいうと、
原因不明(いろいろな要素はわかってきていますが)で
細胞が減少していくことは今の所どうすることもできませんが、
そこに「加齢」「動脈硬化」という現象が
大きく関与していることは確かです。
そういう意味で、糖尿病は血管の老化を進行させるため、
認知症を悪化させやすい、
認知症を発症させやすいと言えます。
私が診ている認知症患者さんも
かなりの確率で糖尿病の治療中です。
同様に、高血圧、喫煙も予防治療すべき生活習慣病です。
高コレステロール血症などの
脂質異常症と認知症の関連は強くはありませんが、
慢性的な脳循環低下、動脈硬化に関与するので
予防治療管理するにこしたことはありません。
米国の論文でしたか、
極論すると認知症の予防、治療は運動しかない、
というものがありました。
それは極端なのですが、要するに生活習慣病の予防、
老化の対応が必要であることは間違いありません。
また、楽器などの手、指を使う作業、仕事をしていると
認知症になりにくいという報告があり、尤もだと思います。
60の手習いでもいいから、
合唱でもするとか、ピアノ、アコーディオン、ハーモニカなど
音を出すのが難しくない楽器を始めるのもいいかもしれません。
あと10年経つと65才以上の5人に1人、
700万人の認知症患者がいるだろうと推測されています。
あと10年経つと高齢者である私にも他人事ではありません。
もともとやっていたピアノ、フルートに加え、
最近はヴァイオリン、笙、篳篥となんでも手を出して、
老化を予防?しております。
こんなに認知症を発症する人が増えてきた
原因のひとつに、
現代の食文化が影響している気がしてなりません。
ポチっといただけると嬉しいです♪
励みにさせていただきます
↓↓![]()













