おれが、チビだったころ、おれたちは、山のなかの掘っ立て小屋に住んでいた。
その山は、まるで 「姥捨て山」 のような、人の寄りつかない さみしい山だった。
おれたち家族は、まるで、世間からうち捨てられたかのように、隔絶されて生きていた。 ... ような気がする。 うちには、テレビもなく、ラジオもなく、新聞もなく、本もなく、「姥捨て山」 のルールのなかで、侘しく生きていた。 する遊びといえば、兄弟で相撲をとるくらいだった。
うちは、貧乏だった。 絵に描いたような。 親父は、学歴もなく、金もなく、運もない男だったのだ。 いや、貧乏というのは、仕方がない。 親父の生まれた家が貧乏だったのだから。
子どものおれから見て、親父は、決して頭は悪くない、いや、むしろ頭の回転はいいほうだと思うが、家が貧乏だったために、学校に上がれず、中学を卒業と同時に働きに出されたのだ。
負けん気だけは強いせいで、行く先々で衝突し、仕事が長つづきしたことがなかったらしい。
二十五のとき、お袋と出会い、結婚した。
そのころはペットブームだったとかで、その流れに便乗して、友だちと、犬専門のペットショップを始めたが、思ったようには商売が回らず、結局借金をかかえる羽目になっただけだったという。 友だちは、借金を残したまま、姿をくらましたそうだ。
運には見放されていた親父だが、子宝に恵まれた。 おれは、四男だった。 下には、妹がひとり、いる。
食べ盛りの五人の子どもをかかえた親父は、莫大な借金に埋もれそうな失意のなかで、元手のかからない商売をはじめることにした。
そんなうまい話があるのか、と思うかもしれないが。
なにをおっぱじめたかというと、山に入って、クワガタムシやカブトムシを捕まえ、それを、昆虫専門のペットショップに売りはじめたのだ。 なにせ、「姥捨て山」 だから、虫だのなんだのは、腐るほどいる。 二、三時間山に入れば、何十匹、何百匹という虫を捕まえられた。
そのうち、ペットショップに売るのがあまり効率が良くないと悟った親父は、じぶんで虫を卸すことを思いついた。
お惣菜用のビニールパックみたいなのに、虫と、砂糖水を含ませた脱脂綿を入れ、ホッチキスで止める。 そして、空気穴をいくつか開けてやる。 こうして、じぶんで捕まえた虫をじぶんで梱包し、じぶんで車に積んで、じぶんで売りに出かけはじめた。
子どもたちは、貴重な戦力だ。 夏場は、家族みんなで、汗をかきながら、梱包作業に励んだ。
おれと三人の兄貴たちで、だれがいちばん早く梱包ができるかを競い合ったことがあった。 いちばん早く、百個梱包できたものが、アイスを独り占めできるのだ。 テレビも漫画もない家で、たのしみといえば、そんなことくらいしかなかったのだ。 一個十円くらいの安くて、水っぽい、味のないアイスだったが、おれたちにとっては、なににもかえがたいご馳走だった。
しかし、兄貴たちは、決して、おれには勝たせてくれなかった。 どんなズルをしてでも、ぜったいに。
親父譲りの負けず嫌いで、なんとか、一度だけでも勝ちたい、もうアイスがどうこうという話ではなく、ただ兄貴たちに勝ちたい、と思ったおれは、必死で空気穴を開けていたとき、「目打ち」 で、思い切り、じぶんの左手の人差し指に穴を開けた。 あのときの痛みを思い出すと、いまでも、臍をまさぐられるような心持ちがする。 お袋に痛みを訴えたら、つばをぺっとつけてくれた。 親父は、「バカヤロウ」 と言った。 二度と、空気穴開けはすまい、と思った瞬間だった。
夏以外の季節は、虫の商売ができないので、春だったら山菜を、秋だったらきのこを売った。 元手をなるべくかけないのが、わが家のならわしだった。
学校には、親父のポンコツ車で送ってもらっていた。 虫を卸しに行く途中で、落っことしてもらい、卸しから帰ってきたら、拾ってもらう。
それが、姥捨て山と社会とをつなぐ、唯一の手段だった。
おれたちにとって、登下校や、放課後などというものは、車の四角い窓から見える、代わり映えしない風景のことを意味していた。 座り心地のわるい車のシートに、延々と揺られることを意味していた。
授業が終わると、いつやって来るかわからぬ親父を、じっとじっと、待った。 兄弟でふざけながら、あるいは、ひとりぽつねんと。 待っているあいだ、教科書を読んだ。 本など買ってもらえなかったから。 教科書くらいしか、読むものがなかったのだ。 教科書を、繰り返し、繰り返し、何度も読んで、教科書から題材を得て、じぶんで物語を考えたり、唱歌のつづきを考えたりしたものだった。
たまに同級生の女の子が、憐れみの表情を浮かべて、「まだお父さん、来ないの?」 とたずねてくることがあって、はずかしくて、顔中の毛穴が開きそうなくらい顔が上気したりした。 ひざの破けた、兄貴のお下がりのズボンの、ほつれた糸をじっと見つめながら、おれは、じっとくやしさをこらえていた。
小学四年のとき、山の下の町に、「マクドナルド」 ができた。
夕方、親父の車に拾われて、国道を通り過ぎながら、はじめてマクドナルドの看板を見たとき、おれの胸は高鳴った。 いったいどんなうまいものが売られているのだろう、と。
がごんがごんと揺れながら、あの 「M」 の看板を遠目に眺め、いつか、あそこで、腹いっぱいになるまで、たらふくハンバーガーというものを喰ってみたいと思っていた。
そのうち、おれは、親の財布から、こっそり金を頂戴するようになった。 札を抜き取ると ばれると思い、毎日、小銭をちょっとずつもらっていたのだ。
そうして、半年かけて、三千円たまったとき、おれは、「家出」 を敢行することにした。
学校帰り、いつも親父に拾ってもらう学校まえのバス停で、おれは、親父を待たずに、バスに乗り込んだ。 そして、国道沿いの 「マクドナルド」 を一心に目指した。
どきどきしながら、「M」 の看板を通り抜け、おれは、ぎこちなさをかくすように、勢いよく店のなかに入った。 そして、いざ、ハンバーガーを喰おう、と思ったのだが、どうしていいのかわからず、ことばを失って、茫然と立ち尽くした。 まるで、じぶんが入りこんではいけない、場違いなところへ来てしまったような気がして、泣き出したいような衝動にかられた。
おれには、姥捨て山がお似合いだ。 こんなところに来ちゃいけなかったんだ。
と思い、帰ろうとしたら、店のカウンターから、きれいな女の人が出てきて、おれに、小さい紙コップを差し出した。 おれはよくわからず、その紙コップを受け取った。 コーラが入っていた。 あのとき飲んだコーラの、舌を刺すような感覚は、一生わすれられないくらい、記憶のなかに残っている。
コーラをくれたおねえさんに笑顔で手招きされ、おれは、誘われるまま、そのおねえさんのところまで行き、なにがなんだかよくわからないまま、注文し、言われた金額を払い、差し出されたトレイを持って、てきとうに空いている席に座った。 同じ学校のやつがいるか、と見回してみたが、見知った顔はなかった。 なんとなく、じぶんだけが、ちょっと大人びたことをしているような気がして、誇らしくなった。
いざ、どきどきしながら、箱をあけて、あこがれのハンバーガーのかぶりついた。 はじめて食べたハンバーガーの味は、うまかったのか、まずかったのかは、よく憶えていない。 ただ、これが、ハンバーガーというものか!と、とにかく感動したのを憶えている。 はじめて食べたフライドポテト、シェイクというものも、よくわからないけれど、こんな食べものが存在していたのか、と、ただただ、感激がこみ上げてくるばかりだった。
おれは、さっきのおねえさんのところに行き、ハンバーガーとポテトとシェイクをもうひとつずつ頼んだ。
ああ。 二度目に食べたときは、舌が慣れたのか、なんてうまい食べものなのだろう、と思った。 そして、三度目に食べたとき、決意した。 もう山には帰らず、ここに残ろう、と。 ここで働かせてもらえば、毎日ハンバーガーが食べられる。 ものをつくるのは、慣れている。 チビのころから、仕事をやらされてきたから、手先は器用だ。 ハンバーガーをつくって、一生、ここにいよう。 ここにいれば、あの笑顔のすてきなおねえさんのそばにいられる ... と思うと、夢がふくらんだ。
おねえさんのところに行って、シェイクをもう一杯注文しようとしたら、おねえさんのかわりにえらそうな男が出てきた。 いろいろ質問されたが、めんどうなので、てきとうなことをこたえた。
調子に乗って、もう一杯シェイクを買い、五杯目のシェイクを飲みながら、店のなかであれこれ空想にふけっていたら。 ふと見上げると、なぜか親父がおれの目のまえに立っていた。 親父は、渋い顔をして、「バカヤロウ」 と言って、おれを頭からなぐりつけた。 一撃でふっとばされたおれは、痛みよりも、あのおねえさんのまえでなぐられたことに腹が立った。 おれはとっさに、おねえさんのほうを見た。 おねえさんは、悲痛な表情で、おれのことをじっと見ていた。 その目が、おれをかっとさせた。 結局おれは、みんなから憐れまれなければ ならないのか、と。 それで、親父に思いきり襲いかかったのだが、あっさりと二撃目を浴びて、店の外のポンコツ車に押し込まれてしまった。
帰りの車のなかで、親父にたっぷりとしぼられた。 ちょっとずつ小銭がなくなっているから、なにごとかと思っていたら、こんなところで、ハンバーガーなんか喰って使っちまうとはと。 そんなことない、あんなうまいもの、おれははじめて食べた。 と言っても、親父は聞く耳を持たなかった。 結局、おれの 「家出」 は、数時間に終わり、夢は夢のまま、姥捨て山の掘っ立て小屋に吸い込まれていった。
けれど、その日の晩は、兄貴たちを出し抜いて、先んじてハンバーガーを食べたであろうことに興奮して、一晩中眠れなかった。 また金をためて、そして、あのおねえさんに会いに行こう、と思っていた。 今度は、憐れまれないような男になって、いつかまた、きっと、と ... 。
―― 数年後、体長十センチのオオクワガタの養殖に成功したわが家は、なるたけ元手をかけずに、自給自足でどんどん商売を拡大し ... 、甲虫業界のトップとなって、姥捨て山の掘っ立て小屋から、クワガタ御殿へと移住した。
幼いころ、兄貴たちとの勝負に負けつづけ、目打ちで指に穴を開けさえもしたおれだが、金をためる方法をあれこれ悶々と考えつづけていたせいか、商売能力だけは そなわってしまった。 そして、兄貴たちにようやく勝って、いま、親父の後釜として、甲虫屋の社長となった。
望むものは手に入れたはずだ。 買いたいものはなんでも買える。 喰いたいものも喰いたいだけ喰える。
けれど、いまだにあの 「M」 のマークを見ると胸が高鳴るおれの、ささやかな夢は、約三十年前、「マクドナルド」 で、おれに笑顔とコーラをくれたあのおねえさんが、どうなったかが知りたい、ということなのだ。
* 七月二十日は、「ハンバーガーの日」 (「マクドナルド」 の日本一号店が開店した日) とのことで書き上げたお話。 「マクドナルド」 びいきというわけではないけれど。
関連リンク:
・「マック占い」
(わたしは、「チキンタツタ」 ... )
・Slashdot Japan - 「毎日三食マクドナルドばかり食べると...」
BGM:
P. J. Harvey ‘Highway 61 Revisited’
(原曲は、Bob Dylan. P. J. のカバーは、かなりワイルドなアレンジで聴ける)
その山は、まるで 「姥捨て山」 のような、人の寄りつかない さみしい山だった。
おれたち家族は、まるで、世間からうち捨てられたかのように、隔絶されて生きていた。 ... ような気がする。 うちには、テレビもなく、ラジオもなく、新聞もなく、本もなく、「姥捨て山」 のルールのなかで、侘しく生きていた。 する遊びといえば、兄弟で相撲をとるくらいだった。
うちは、貧乏だった。 絵に描いたような。 親父は、学歴もなく、金もなく、運もない男だったのだ。 いや、貧乏というのは、仕方がない。 親父の生まれた家が貧乏だったのだから。
子どものおれから見て、親父は、決して頭は悪くない、いや、むしろ頭の回転はいいほうだと思うが、家が貧乏だったために、学校に上がれず、中学を卒業と同時に働きに出されたのだ。
負けん気だけは強いせいで、行く先々で衝突し、仕事が長つづきしたことがなかったらしい。
二十五のとき、お袋と出会い、結婚した。
そのころはペットブームだったとかで、その流れに便乗して、友だちと、犬専門のペットショップを始めたが、思ったようには商売が回らず、結局借金をかかえる羽目になっただけだったという。 友だちは、借金を残したまま、姿をくらましたそうだ。
運には見放されていた親父だが、子宝に恵まれた。 おれは、四男だった。 下には、妹がひとり、いる。
食べ盛りの五人の子どもをかかえた親父は、莫大な借金に埋もれそうな失意のなかで、元手のかからない商売をはじめることにした。
そんなうまい話があるのか、と思うかもしれないが。
なにをおっぱじめたかというと、山に入って、クワガタムシやカブトムシを捕まえ、それを、昆虫専門のペットショップに売りはじめたのだ。 なにせ、「姥捨て山」 だから、虫だのなんだのは、腐るほどいる。 二、三時間山に入れば、何十匹、何百匹という虫を捕まえられた。
そのうち、ペットショップに売るのがあまり効率が良くないと悟った親父は、じぶんで虫を卸すことを思いついた。
お惣菜用のビニールパックみたいなのに、虫と、砂糖水を含ませた脱脂綿を入れ、ホッチキスで止める。 そして、空気穴をいくつか開けてやる。 こうして、じぶんで捕まえた虫をじぶんで梱包し、じぶんで車に積んで、じぶんで売りに出かけはじめた。
子どもたちは、貴重な戦力だ。 夏場は、家族みんなで、汗をかきながら、梱包作業に励んだ。
おれと三人の兄貴たちで、だれがいちばん早く梱包ができるかを競い合ったことがあった。 いちばん早く、百個梱包できたものが、アイスを独り占めできるのだ。 テレビも漫画もない家で、たのしみといえば、そんなことくらいしかなかったのだ。 一個十円くらいの安くて、水っぽい、味のないアイスだったが、おれたちにとっては、なににもかえがたいご馳走だった。
しかし、兄貴たちは、決して、おれには勝たせてくれなかった。 どんなズルをしてでも、ぜったいに。
親父譲りの負けず嫌いで、なんとか、一度だけでも勝ちたい、もうアイスがどうこうという話ではなく、ただ兄貴たちに勝ちたい、と思ったおれは、必死で空気穴を開けていたとき、「目打ち」 で、思い切り、じぶんの左手の人差し指に穴を開けた。 あのときの痛みを思い出すと、いまでも、臍をまさぐられるような心持ちがする。 お袋に痛みを訴えたら、つばをぺっとつけてくれた。 親父は、「バカヤロウ」 と言った。 二度と、空気穴開けはすまい、と思った瞬間だった。
夏以外の季節は、虫の商売ができないので、春だったら山菜を、秋だったらきのこを売った。 元手をなるべくかけないのが、わが家のならわしだった。
学校には、親父のポンコツ車で送ってもらっていた。 虫を卸しに行く途中で、落っことしてもらい、卸しから帰ってきたら、拾ってもらう。
それが、姥捨て山と社会とをつなぐ、唯一の手段だった。
おれたちにとって、登下校や、放課後などというものは、車の四角い窓から見える、代わり映えしない風景のことを意味していた。 座り心地のわるい車のシートに、延々と揺られることを意味していた。
授業が終わると、いつやって来るかわからぬ親父を、じっとじっと、待った。 兄弟でふざけながら、あるいは、ひとりぽつねんと。 待っているあいだ、教科書を読んだ。 本など買ってもらえなかったから。 教科書くらいしか、読むものがなかったのだ。 教科書を、繰り返し、繰り返し、何度も読んで、教科書から題材を得て、じぶんで物語を考えたり、唱歌のつづきを考えたりしたものだった。
たまに同級生の女の子が、憐れみの表情を浮かべて、「まだお父さん、来ないの?」 とたずねてくることがあって、はずかしくて、顔中の毛穴が開きそうなくらい顔が上気したりした。 ひざの破けた、兄貴のお下がりのズボンの、ほつれた糸をじっと見つめながら、おれは、じっとくやしさをこらえていた。
小学四年のとき、山の下の町に、「マクドナルド」 ができた。
夕方、親父の車に拾われて、国道を通り過ぎながら、はじめてマクドナルドの看板を見たとき、おれの胸は高鳴った。 いったいどんなうまいものが売られているのだろう、と。
がごんがごんと揺れながら、あの 「M」 の看板を遠目に眺め、いつか、あそこで、腹いっぱいになるまで、たらふくハンバーガーというものを喰ってみたいと思っていた。
そのうち、おれは、親の財布から、こっそり金を頂戴するようになった。 札を抜き取ると ばれると思い、毎日、小銭をちょっとずつもらっていたのだ。
そうして、半年かけて、三千円たまったとき、おれは、「家出」 を敢行することにした。
学校帰り、いつも親父に拾ってもらう学校まえのバス停で、おれは、親父を待たずに、バスに乗り込んだ。 そして、国道沿いの 「マクドナルド」 を一心に目指した。
どきどきしながら、「M」 の看板を通り抜け、おれは、ぎこちなさをかくすように、勢いよく店のなかに入った。 そして、いざ、ハンバーガーを喰おう、と思ったのだが、どうしていいのかわからず、ことばを失って、茫然と立ち尽くした。 まるで、じぶんが入りこんではいけない、場違いなところへ来てしまったような気がして、泣き出したいような衝動にかられた。
おれには、姥捨て山がお似合いだ。 こんなところに来ちゃいけなかったんだ。
と思い、帰ろうとしたら、店のカウンターから、きれいな女の人が出てきて、おれに、小さい紙コップを差し出した。 おれはよくわからず、その紙コップを受け取った。 コーラが入っていた。 あのとき飲んだコーラの、舌を刺すような感覚は、一生わすれられないくらい、記憶のなかに残っている。
コーラをくれたおねえさんに笑顔で手招きされ、おれは、誘われるまま、そのおねえさんのところまで行き、なにがなんだかよくわからないまま、注文し、言われた金額を払い、差し出されたトレイを持って、てきとうに空いている席に座った。 同じ学校のやつがいるか、と見回してみたが、見知った顔はなかった。 なんとなく、じぶんだけが、ちょっと大人びたことをしているような気がして、誇らしくなった。
いざ、どきどきしながら、箱をあけて、あこがれのハンバーガーのかぶりついた。 はじめて食べたハンバーガーの味は、うまかったのか、まずかったのかは、よく憶えていない。 ただ、これが、ハンバーガーというものか!と、とにかく感動したのを憶えている。 はじめて食べたフライドポテト、シェイクというものも、よくわからないけれど、こんな食べものが存在していたのか、と、ただただ、感激がこみ上げてくるばかりだった。
おれは、さっきのおねえさんのところに行き、ハンバーガーとポテトとシェイクをもうひとつずつ頼んだ。
ああ。 二度目に食べたときは、舌が慣れたのか、なんてうまい食べものなのだろう、と思った。 そして、三度目に食べたとき、決意した。 もう山には帰らず、ここに残ろう、と。 ここで働かせてもらえば、毎日ハンバーガーが食べられる。 ものをつくるのは、慣れている。 チビのころから、仕事をやらされてきたから、手先は器用だ。 ハンバーガーをつくって、一生、ここにいよう。 ここにいれば、あの笑顔のすてきなおねえさんのそばにいられる ... と思うと、夢がふくらんだ。
おねえさんのところに行って、シェイクをもう一杯注文しようとしたら、おねえさんのかわりにえらそうな男が出てきた。 いろいろ質問されたが、めんどうなので、てきとうなことをこたえた。
調子に乗って、もう一杯シェイクを買い、五杯目のシェイクを飲みながら、店のなかであれこれ空想にふけっていたら。 ふと見上げると、なぜか親父がおれの目のまえに立っていた。 親父は、渋い顔をして、「バカヤロウ」 と言って、おれを頭からなぐりつけた。 一撃でふっとばされたおれは、痛みよりも、あのおねえさんのまえでなぐられたことに腹が立った。 おれはとっさに、おねえさんのほうを見た。 おねえさんは、悲痛な表情で、おれのことをじっと見ていた。 その目が、おれをかっとさせた。 結局おれは、みんなから憐れまれなければ ならないのか、と。 それで、親父に思いきり襲いかかったのだが、あっさりと二撃目を浴びて、店の外のポンコツ車に押し込まれてしまった。
帰りの車のなかで、親父にたっぷりとしぼられた。 ちょっとずつ小銭がなくなっているから、なにごとかと思っていたら、こんなところで、ハンバーガーなんか喰って使っちまうとはと。 そんなことない、あんなうまいもの、おれははじめて食べた。 と言っても、親父は聞く耳を持たなかった。 結局、おれの 「家出」 は、数時間に終わり、夢は夢のまま、姥捨て山の掘っ立て小屋に吸い込まれていった。
けれど、その日の晩は、兄貴たちを出し抜いて、先んじてハンバーガーを食べたであろうことに興奮して、一晩中眠れなかった。 また金をためて、そして、あのおねえさんに会いに行こう、と思っていた。 今度は、憐れまれないような男になって、いつかまた、きっと、と ... 。
―― 数年後、体長十センチのオオクワガタの養殖に成功したわが家は、なるたけ元手をかけずに、自給自足でどんどん商売を拡大し ... 、甲虫業界のトップとなって、姥捨て山の掘っ立て小屋から、クワガタ御殿へと移住した。
幼いころ、兄貴たちとの勝負に負けつづけ、目打ちで指に穴を開けさえもしたおれだが、金をためる方法をあれこれ悶々と考えつづけていたせいか、商売能力だけは そなわってしまった。 そして、兄貴たちにようやく勝って、いま、親父の後釜として、甲虫屋の社長となった。
望むものは手に入れたはずだ。 買いたいものはなんでも買える。 喰いたいものも喰いたいだけ喰える。
けれど、いまだにあの 「M」 のマークを見ると胸が高鳴るおれの、ささやかな夢は、約三十年前、「マクドナルド」 で、おれに笑顔とコーラをくれたあのおねえさんが、どうなったかが知りたい、ということなのだ。
* 七月二十日は、「ハンバーガーの日」 (「マクドナルド」 の日本一号店が開店した日) とのことで書き上げたお話。 「マクドナルド」 びいきというわけではないけれど。
関連リンク:
・「マック占い」
(わたしは、「チキンタツタ」 ... )
・Slashdot Japan - 「毎日三食マクドナルドばかり食べると...」
BGM:
P. J. Harvey ‘Highway 61 Revisited’
(原曲は、Bob Dylan. P. J. のカバーは、かなりワイルドなアレンジで聴ける)










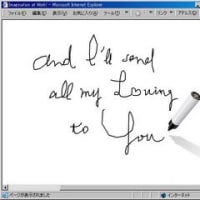



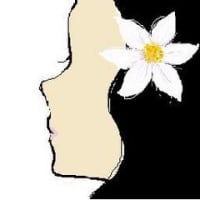










これ、なかなかの力作なんですよ♪
あとで、紹介しようと思っていたのに~。
(ほんとにほんとに)
わたしは、チーズでした♪
わくわくさせる感じが。
で、私は、
チキンタツタとチーズでしたよ、うふふ。
予告しただけのことは、ある。
これは、真似できないや。
予告などしてしまって、どうしよう?!と思っていたのですが ... 。
お読みくださってありがとうございます。
相変わらずな物語になってしまいましたが ... 。
新たな展開も検討中です ...
(それより、仕事をせねば ... )
# 占いの結果、やっぱり同じ?! うれしいです !
三十路のおいらは、お菓子なんかいくらでも「大人買い」できちゃうもんね。チョコレートもポテトチップスも好きなだけ買えるもんねっ!
大人っていいよね。
と、優越感に浸ってみました。
(もっとも、大人やってていいことって、あんまりないけどね。あ、エッチが出来ることもあるか...)
過去記事、読んでくださって(?)、うれしいです!
食玩、もはやコンビニの主力商品ですよね ... 。
しかも「大人買い」の ... 。
小さいころ、大人になったら、好きなおもちゃやお菓子を、好きなだけ買ってみたい! と思っていましたが、「大人買い」できるいまとなってみると、子どものころに感じたうれしさは、比べものにならなかったなあ、なんて。
> (もっとも、大人やってていいことって、あんまりないけどね。あ、エッチが出来ることもあるか...)
えっとお、それ以外にも、○×とか、$*%とか、いろいろ ... と返してみたり。
でも ... 、本心は、「宿題がなかったら、子どもに戻りたい!」 です!