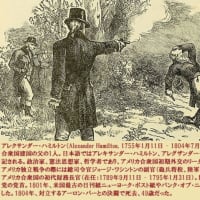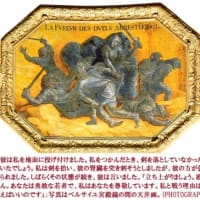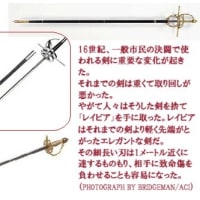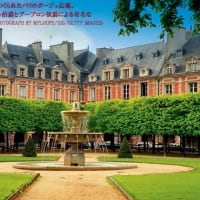== ナショナルジオグラフィック日本版より転載 ==
❇ 特殊装備を発注
1週間ほど前、2015年の北極圏探検で使用する装備の打ち合わせのために大阪に行ってきた。 最初に訪問したのは米国のアウトドアブランド、マーモットを日本で展開するデサント社である。
デサント社からは、2010年に『空白の五マイル』という本を書いて以降、衣類を中心に装備の提供を受けてきた。 北極圏の旅に関しても、2011年に初めて極北カナダで長い徒歩探検をしたとき以来、羽毛服やゴアテックスのジャケット、パンツなどを使わせてもらっている。 ただ、今回大阪に行ったのは既製品に関してではなく、次に私が計画している北極圏の特殊な旅で使う独自の装備を開発することが目的だった。
2015年3月から私はグリーンランド最北の村シオラパルクを根拠地に、1年間にわたる長い旅を計画している。テーマは極夜の探検。 北極圏は冬の間、地平線から太陽が昇らない極夜という季節を迎える。要するに長い夜の季節だ。 この夜の季節は、緯度が高くなり北極点に近くなればなるほど期間も長くなるし、そして暗闇の深さも増す。 私が滞在を予定しているシオラパルクは北緯77度47分にある世界最北の村のひとつで、11月下旬から2月中旬までのほぼ4カ月間、太陽が姿を現さない。 この長い夜の世界を、たった一人で誰にも会わずに橇を引いて旅をすることができたら、私は誰も知らない地球の裏の素顔を見ることができるだろう。 手短に述べると、それが私が考えている次の北極探検の全容である。
とはいえ、それが簡単なことではないことは分かっている。 私はこの計画を実行するにあたり、すでに2012年冬と2014年春に、それぞれカナダ・ケント半島とシオラパルクで予備探検みたいなのを行い、カナダでは実際に1カ月間、極夜の暗闇を歩いてみた。 その結果わかったのは、極夜という環境で長期間旅行を実行するためには、太陽が昇っている季節とはまったく異なる対策が必要になるということだった。
とりわけ衣類と寝袋に関しては非常にデリケートな対策が求められる。 太陽が出ないということは、要するに濡れたものを乾かせないということだ。 北極圏では空気が非常に乾燥していることは間違いないが、しかしそれでも長期間旅行をしていると、テントには自分たちの息や汗や炊事の水蒸気が固着して、どうしても湿っぽくなってくる。 その水分が、例えば羽毛服なんかに着くと、中の羽毛がへたってきて保温力がなくなっていく。 それが春の太陽が昇る季節なら、濡れたものを橇の外側に括り付けておけば歩いている間に自然と乾くが、極夜ではそれができないので、羽毛服は水分を吸って重くなるばかりで、寝袋にいたっては1カ月もテント生活をすると氷の塊のようになってしまう。
デサント社に相談したのは、極夜で長期間旅をしても濡れない防寒着だ。 正確にいうと濡れないというのは無理なので、濡れても水分を溜めこまない防寒着である。 羽毛や、あるいは化学繊維の綿系素材が入った防寒着だと、どうしても水分を中に溜めこんでしまい乾かなくなってしまう。 だったら綿系素材ではなく、フリースか毛布のようなもので作ったほうが、水分を外に発散するだろうからいいのではないか。 今年のグリーンランドの旅でそんなことを思いついた私は、帰国後すぐにデサント社の担当者と相談し特注品を作ってもらうことにした。 そのサンプルがこのほど出来上がり、サイズや細かい点の修正を伝えるため大阪に訪れたのである。
特注した防寒着は、米国の特殊部隊と繊維メーカーが共同開発した特殊素材を3枚重ねにし、外側に起毛したフリースを縫い合わせたものである。 少しサイズが小さかったのでそこは修正することにしたが、着心地は京都の老舗布団屋の高級毛布のような肌触りだった。 担当者によると、この特殊素材は非常に高価で、「こんな高いものを3枚も使ったら商品としてはとても成立しないので、こんな発想自体、ぼくらからは出てこない。 非常に面白い経験です」とのこと。 一瞬、皮肉を言われたのだろうかと思ったが、私は気にしないことにし、「思ったより出来上がりが軽かったので、この高級素材を3枚から4枚に増やしてくれませんか」と追加注文をお願いした。
また、デサント社には防寒着のほかに、ゴアテックスのジャケット、パンツといったハードシェルに代わる防風用のソフトシェルの特注品もお願いしており、そのサンプルの出来上がりについても話し合った。 ゴアテックスは防風性能は完璧なのだが、極地で使用するとどうしても透湿性に限界があるため、行動中に汗が内側で結露してしまう。 結露した水分は凍結するので、行動終了後にテントに入ると、シェルの内側が冷凍庫のように霜まみれになり、内側に着ているズボンや上着を濡らしてしまうのだ。
極地に限らず山でもジャングルでも、探検中に避けたいのはこの濡れによる不快感である。 そこで次はゴアテックスの代わりに防風性能の高い生地を使ったソフトシェルと、薄手のウインドブレーカーの開発を依頼している。 また、防寒ミトン(巨大な2本指の手袋)や靴の上に履くオーバーシューズ、荷物を入れるスタッフバッグなどなど、かなりの種類の特注品を頼んでおり、年明けには2回目のサンプルが出来上がる予定だ。
デサント社との打ち合わせが終わると、今度は総合アウトドアメーカーであるモンベル本社を訪問した。 モンベル社にお願いしているのは寝袋の特注品である。

寝袋の問題点は、寝ている間に身体から発散された汗が外に向かって放散していき、綿の内部の外気に触れるあたりで凍りついていくことだ。 そのため、いつも旅を始めてから2週間ぐらいで寝袋の綿の中に氷の塊ができはじめ、それがどんどん成長していき、1カ月を過ぎる頃になると寝袋の重さが5キロぐらいになっている。 羽毛ではなく化繊の寝袋を使っているので凍っても寒くはないのだが、それでも重くなるのは非常にストレスとなる。
モンベル社にお願いしたのは少し複雑な構造の寝袋である。 まず寝袋本体は羽毛と化繊の2層構造。これまでの経験から寝袋の内側は身体の熱で水分が放散されるので、常に乾いた状態にある。 そのため羽毛を使っても濡れることがないので保温力も落ちないはずだ。 一方、外側は放散した水分が凍りつくので、そちらは濡れても保温力の落ちない従来通りの化繊を使うことにした。
さらに外側から寝袋にかぶせる薄い化繊のオーバー寝袋も特注した。 これは、寝ている間に外に放散していく水分をわざと吸わせて、凍らせるためのものである。 寝袋本体が凍ってしまうと大きすぎて乾かせないが、薄いオーバー寝袋なら停滞時にテントのなかでコンロで乾かすことができるはず。 できるだけ頻繁に乾かせば、寝袋に巨大氷ができることもなくなるに違いない。 それが狙いである。
だんだんと装備が出来上がっていくと、いよいよ出発が近づいてきたという焦りのような気持ちが湧いてくる。 今までは極夜に行くと口では言ってきたが、かなり先の話だったので自分の中でも現実感に乏しかった。 それがこうやって具体的な準備が始まっていくと、嫌でも苦しい旅のことを考えざるを得なくなってくる。 極夜の闇の中を4カ月間も旅する。そんなことが本当に可能なのか。自分が旅立つ日が現実にやって来るのだろうか。 今回特注した装備が予期した効果を発揮してくれるのかも含め、様々なことを想像しただけで期待よりも不安で胸が苦しくなってくる。 旅のことはまだあまり考えたくないというのが、今の正直な気持ちだ。
===== 続く
※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行。
【 We are the WORLD 】
https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport
【 Sting Eenglishman in New_ York 】
http://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk
【 DEATH VALLEY DREAMLAPSE 2 】
※上記をクリック賜れば動画・ミュージックが楽しめます
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------
・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・
森のなかえ
================================================